太宰治-桜桃
- 格式:doc
- 大小:35.50 KB
- 文档页数:9
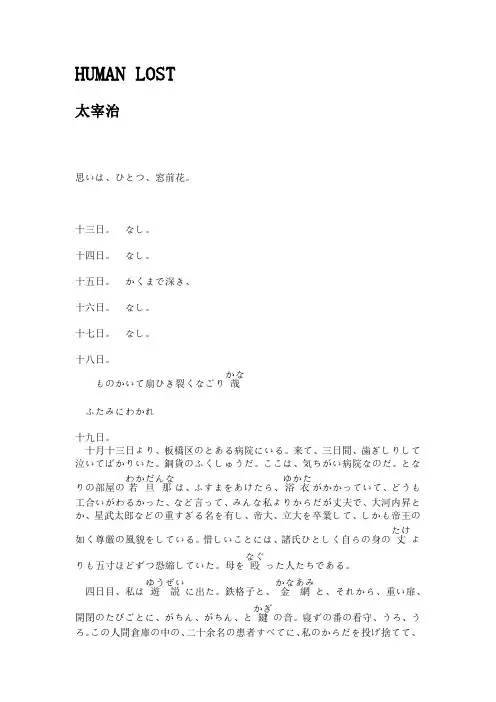
HUMAN LOST太宰治思いは、ひとつ、窓前花。
十三日。
なし。
十四日。
なし。
十五日。
かくまで深き、十六日。
なし。
十七日。
なし。
十八日。
ものかいて扇ひき裂くなごり哉かなふたみにわかれ十九日。
十月十三日より、板橋区のとある病院にいる。
来て、三日間、歯ぎしりして泣いてばかりいた。
銅貨のふくしゅうだ。
ここは、気ちがい病院なのだ。
となりの部屋の若旦那わかだんなは、ふすまをあけたら、浴衣ゆかたがかかっていて、どうも工合いがわるかった、など言って、みんな私よりからだが丈夫で、大河内昇とか、星武太郎などの重すぎる名を有し、帝大、立大を卒業して、しかも帝王の如く尊厳の風貌をしている。
惜しいことには、諸氏ひとしく自らの身の丈たけよりも五寸ほどずつ恐縮していた。
母を殴なぐった人たちである。
四日目、私は遊説ゆうぜいに出た。
鉄格子と、金網かなあみと、それから、重い扉、開閉のたびごとに、がちん、がちん、と鍵かぎの音。
寝ずの番の看守、うろ、うろ。
この人間倉庫の中の、二十余名の患者すべてに、私のからだを投げ捨てて、話かけた。
まるまると白く太った美男の、肩を力一杯ゆすってやって、なまけもの! と罵ののしった。
眼のさめて在る限り、枕頭の商法の教科書を百人一首を読むような、あんなふしをつけて大声で読みわめきつづけている一受験狂に、勉強やめよ、試験全廃だ、と教えてやったら、一瞬ぱっと愁眉しゅうびをひらいた。
うしろ姿のおせん様というあだ名の、セル着たる二十五歳の一青年、日がな一日、部屋の隅、壁にむかってしょんぼり横坐りに居崩いくずれて坐って、だしぬけに私に頭を殴られても、僕はたった二十五歳だ、捨てろ、捨てろ、と低く呟つぶやきつづけるばかりで私の顔を見ようとさえせぬ故、こんどは私、めそめそするな、と叱って、力いっぱいうしろから抱いてやって激しくせきにむせかえったら、青年いささか得意げに、放せ、放せ、肺病がうつると軽蔑して、私は有難ありがたく て泣いてしまった。
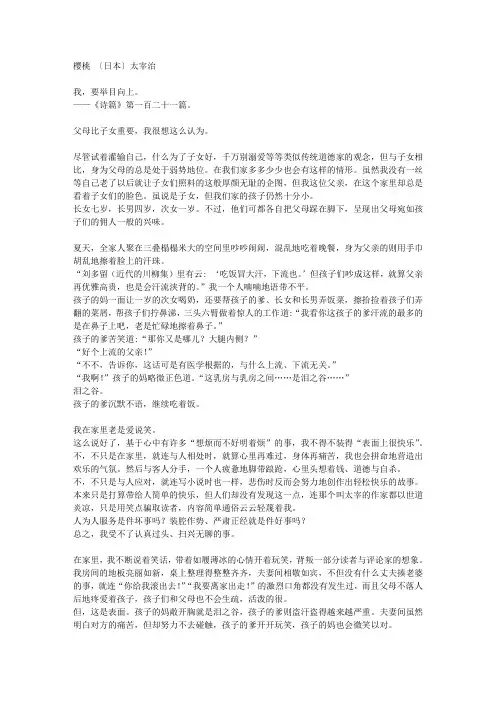
樱桃〔日本〕太宰治我,要举目向上。
——《诗篇》第一百二十一篇。
父母比子女重要,我很想这么认为。
尽管试着灌输自己,什么为了子女好,千万别溺爱等等类似传统道德家的观念,但与子女相比,身为父母的总是处于弱势地位。
在我们家多多少少也会有这样的情形。
虽然我没有一丝等自己老了以后就让子女们照料的这般厚颜无耻的企图,但我这位父亲,在这个家里却总是看着子女们的脸色。
虽说是子女,但我们家的孩子仍然十分小。
长女七岁,长男四岁,次女一岁。
不过,他们可都各自把父母踩在脚下,呈现出父母宛如孩子们的佣人一般的兴味。
夏天,全家人聚在三叠榻榻米大的空间里吵吵闹闹,混乱地吃着晚餐,身为父亲的则用手巾胡乱地擦着脸上的汗珠。
“刘多留(近代的川柳集)里有云: ‘吃饭冒大汗,下流也。
’但孩子们吵成这样,就算父亲再优雅高贵,也是会汗流浃背的。
”我一个人喃喃地语带不平。
孩子的妈一面让一岁的次女喝奶,还要帮孩子的爹、长女和长男弄饭菜,擦拾捡着孩子们弄翻的菜屑,帮孩子们拧鼻涕,三头六臂做着惊人的工作道:“我看你这孩子的爹汗流的最多的是在鼻子上吧,老是忙碌地擦着鼻子。
”孩子的爹苦笑道:“那你又是哪儿?大腿内侧?”“好个上流的父亲!”“不不,告诉你,这话可是有医学根据的,与什么上流、下流无关。
”“我啊!”孩子的妈略微正色道。
“这乳房与乳房之间……是泪之谷……”泪之谷。
孩子的爹沉默不语,继续吃着饭。
我在家里老是爱说笑。
这么说好了,基于心中有许多“想烦而不好明着烦”的事,我不得不装得“表面上很快乐”。
不,不只是在家里,就连与人相处时,就算心里再难过,身体再痛苦,我也会拼命地营造出欢乐的气氛。
然后与客人分手,一个人疲惫地脚带踉跄,心里头想着钱、道德与自杀。
不,不只是与人应对,就连写小说时也一样,悲伤时反而会努力地创作出轻松快乐的故事。
本来只是打算带给人简单的快乐,但人们却没有发现这一点,连那个叫太宰的作家都以世道炎凉,只是用笑点骗取读者,内容简单通俗云云轻蔑着我。
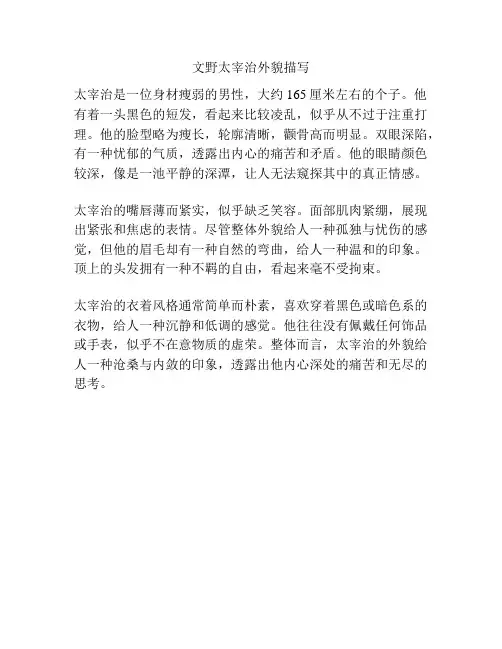
文野太宰治外貌描写
太宰治是一位身材瘦弱的男性,大约165厘米左右的个子。
他有着一头黑色的短发,看起来比较凌乱,似乎从不过于注重打理。
他的脸型略为瘦长,轮廓清晰,颧骨高而明显。
双眼深陷,有一种忧郁的气质,透露出内心的痛苦和矛盾。
他的眼睛颜色较深,像是一池平静的深潭,让人无法窥探其中的真正情感。
太宰治的嘴唇薄而紧实,似乎缺乏笑容。
面部肌肉紧绷,展现出紧张和焦虑的表情。
尽管整体外貌给人一种孤独与忧伤的感觉,但他的眉毛却有一种自然的弯曲,给人一种温和的印象。
顶上的头发拥有一种不羁的自由,看起来毫不受拘束。
太宰治的衣着风格通常简单而朴素,喜欢穿着黑色或暗色系的衣物,给人一种沉静和低调的感觉。
他往往没有佩戴任何饰品或手表,似乎不在意物质的虚荣。
整体而言,太宰治的外貌给人一种沧桑与内敛的印象,透露出他内心深处的痛苦和无尽的思考。
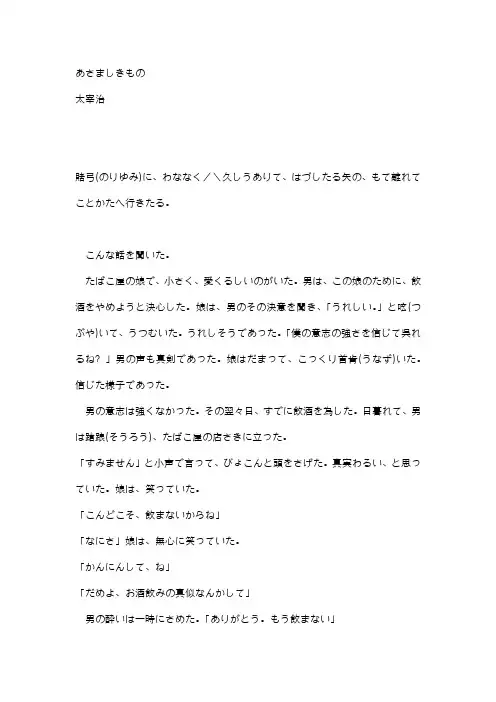
あさましきもの太宰治賭弓(のりゆみ)に、わななく/\久しうありて、はづしたる矢の、もて離れてことかたへ行きたる。
こんな話を聞いた。
たばこ屋の娘で、小さく、愛くるしいのがいた。
男は、この娘のために、飲酒をやめようと決心した。
娘は、男のその決意を聞き、「うれしい。
」と呟(つぶや)いて、うつむいた。
うれしそうであった。
「僕の意志の強さを信じて呉れるね?」男の声も真剣であった。
娘はだまって、こっくり首肯(うなず)いた。
信じた様子であった。
男の意志は強くなかった。
その翌々日、すでに飲酒を為した。
日暮れて、男は蹌踉(そうろう)、たばこ屋の店さきに立った。
「すみません」と小声で言って、ぴょこんと頭をさげた。
真実わるい、と思っていた。
娘は、笑っていた。
「こんどこそ、飲まないからね」「なにさ」娘は、無心に笑っていた。
「かんにんして、ね」「だめよ、お酒飲みの真似なんかして」男の酔いは一時にさめた。
「ありがとう。
もう飲まない」「たんと、たんと、からかいなさい」「おや、僕は、僕は、ほんとうに飲んでいるのだよ」あらためて娘の瞳(ひとみ)を凝視した。
「だって」娘は、濁りなき笑顔で応じた。
「誓ったのだもの。
飲むわけないわ。
ここではお芝居およしなさいね」てんから疑って呉(く)れなかった。
男は、キネマ俳優であった。
岡田時彦さんである。
先年なくなったが、じみな人であった。
あんな、せつなかったこと、ございませんでした、としんみり述懐して、行儀よく紅茶を一口すすった。
また、こんな話も聞いた。
どんなに永いこと散歩しても、それでも物たりなかったという。
ひとけなき夜の道。
女は、息もたえだえの思いで、幾度となく胴をくねらせた。
けれども、大学生は、レインコオトのポケットに両手をつっこんだまま、さっさと歩いた。
女は、その大学生の怒った肩に、おのれの丸いやわらかな肩をこすりつけるようにしながら男の後を追った。
大学生は、頭がよかった。
女の発情を察知していた。
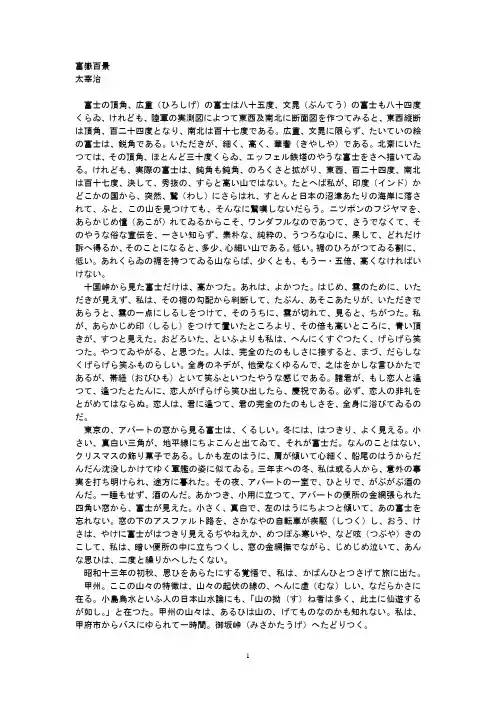
富嶽百景太宰治富士の頂角、広重(ひろしげ)の富士は八十五度、文晁(ぶんてう)の富士も八十四度くらゐ、けれども、陸軍の実測図によつて東西及单北に断面図を作つてみると、東西縦断は頂角、百二十四度となり、单北は百十七度である。
広重、文晁に限らず、たいていの絵の富士は、鋭角である。
いただきが、細く、高く、華奢(きやしや)である。
北斎にいたつては、その頂角、ほとんど三十度くらゐ、エッフェル鉄塔のやうな富士をさへ描いてゐる。
けれども、実際の富士は、鈍角も鈍角、のろくさと拡がり、東西、百二十四度、单北は百十七度、決して、秀抜の、すらと高い山ではない。
たとへば私が、印度(インド)かどこかの国から、突然、鷲(わし)にさらはれ、すとんと日本の沼津あたりの海岸に落されて、ふと、この山を見つけても、そんなに驚嘆しないだらう。
ニツポンのフジヤマを、あらかじめ憧(あこが)れてゐるからこそ、ワンダフルなのであつて、さうでなくて、そのやうな俗な宣伝を、一さい知らず、素朴な、純粋の、うつろな心に、果して、どれだけ訴へ得るか、そのことになると、多少、心細い山である。
低い。
裾のひろがつてゐる割に、低い。
あれくらゐの裾を持つてゐる山ならば、少くとも、もう一・五倍、高くなければいけない。
十国峠から見た富士だけは、高かつた。
あれは、よかつた。
はじめ、雲のために、いただきが見えず、私は、その裾の勾配から判断して、たぶん、あそこあたりが、いただきであらうと、雲の一点にしるしをつけて、そのうちに、雲が切れて、見ると、ちがつた。
私が、あらかじめ印(しるし)をつけて置いたところより、その倍も高いところに、青い頂きが、すつと見えた。
おどろいた、といふよりも私は、へんにくすぐつたく、げらげら笑つた。
やつてゐやがる、と思つた。
人は、完全のたのもしさに接すると、まづ、だらしなくげらげら笑ふものらしい。
全身のネヂが、他愛なくゆるんで、之はをかしな言ひかたであるが、帯紐(おびひも)といて笑ふといつたやうな感じである。
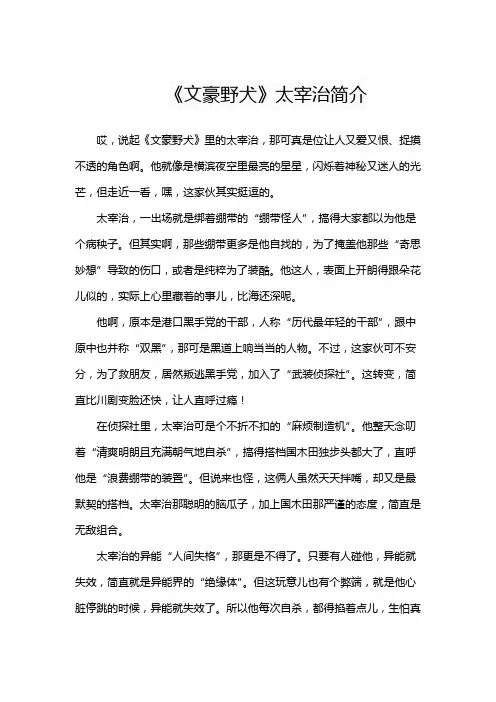
《文豪野犬》太宰治简介哎,说起《文豪野犬》里的太宰治,那可真是位让人又爱又恨、捉摸不透的角色啊。
他就像是横滨夜空里最亮的星星,闪烁着神秘又迷人的光芒,但走近一看,嘿,这家伙其实挺逗的。
太宰治,一出场就是绑着绷带的“绷带怪人”,搞得大家都以为他是个病秧子。
但其实啊,那些绷带更多是他自找的,为了掩盖他那些“奇思妙想”导致的伤口,或者是纯粹为了装酷。
他这人,表面上开朗得跟朵花儿似的,实际上心里藏着的事儿,比海还深呢。
他啊,原本是港口黑手党的干部,人称“历代最年轻的干部”,跟中原中也并称“双黑”,那可是黑道上响当当的人物。
不过,这家伙可不安分,为了救朋友,居然叛逃黑手党,加入了“武装侦探社”。
这转变,简直比川剧变脸还快,让人直呼过瘾!在侦探社里,太宰治可是个不折不扣的“麻烦制造机”。
他整天念叨着“清爽明朗且充满朝气地自杀”,搞得搭档国木田独步头都大了,直呼他是“浪费绷带的装置”。
但说来也怪,这俩人虽然天天拌嘴,却又是最默契的搭档。
太宰治那聪明的脑瓜子,加上国木田那严谨的态度,简直是无敌组合。
太宰治的异能“人间失格”,那更是不得了。
只要有人碰他,异能就失效,简直就是异能界的“绝缘体”。
但这玩意儿也有个弊端,就是他心脏停跳的时候,异能就失效了。
所以他每次自杀,都得掐着点儿,生怕真的一去不复返了。
不过啊,这家伙虽然爱自杀,但每次都死不了,真是让人哭笑不得。
除了这些,太宰治还是个不折不扣的“戏精”。
他特别喜欢戏弄别人,尤其是自己的搭档和朋友。
但你可别被他的外表给骗了,他内心其实是个非常温柔的人。
他对朋友那是没话说,尤其是对织田作之助,那叫一个深情厚谊。
织田作之助的死,对他打击很大,也是他叛逃黑手党的重要原因之一。
太宰治这个人啊,复杂得就像一本厚重的书,你永远不知道下一页会写什么。
他既冷漠又热情,既深沉又神秘,让人捉摸不透。
但正是这种矛盾与复杂,让他成为了《文豪野犬》中最具魅力的角色之一。
总之啊,太宰治就是这样一个让人又爱又恨的角色。
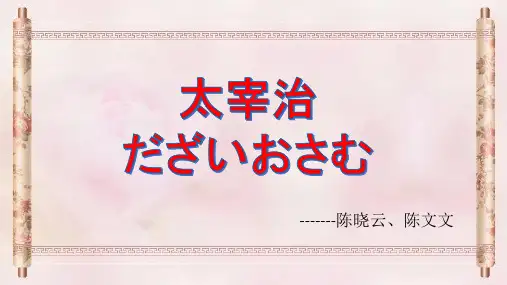
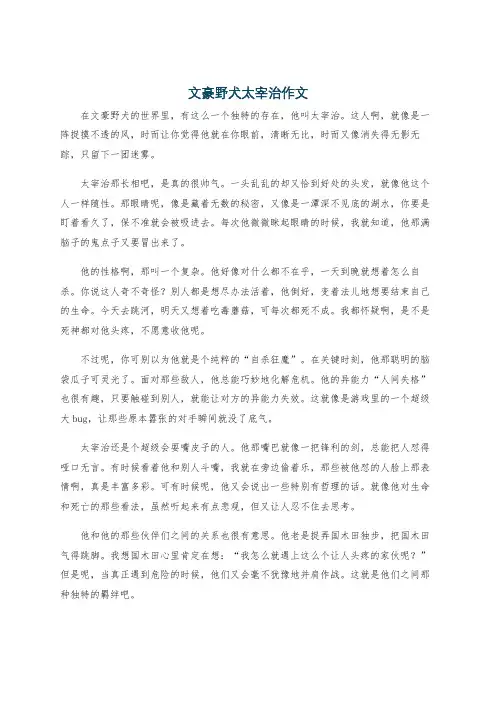
文豪野犬太宰治作文在文豪野犬的世界里,有这么一个独特的存在,他叫太宰治。
这人啊,就像是一阵捉摸不透的风,时而让你觉得他就在你眼前,清晰无比,时而又像消失得无影无踪,只留下一团迷雾。
太宰治那长相吧,是真的很帅气。
一头乱乱的却又恰到好处的头发,就像他这个人一样随性。
那眼睛呢,像是藏着无数的秘密,又像是一潭深不见底的湖水,你要是盯着看久了,保不准就会被吸进去。
每次他微微眯起眼睛的时候,我就知道,他那满脑子的鬼点子又要冒出来了。
他的性格啊,那叫一个复杂。
他好像对什么都不在乎,一天到晚就想着怎么自杀。
你说这人奇不奇怪?别人都是想尽办法活着,他倒好,变着法儿地想要结束自己的生命。
今天去跳河,明天又想着吃毒蘑菇,可每次都死不成。
我都怀疑啊,是不是死神都对他头疼,不愿意收他呢。
不过呢,你可别以为他就是个纯粹的“自杀狂魔”。
在关键时刻,他那聪明的脑袋瓜子可灵光了。
面对那些敌人,他总能巧妙地化解危机。
他的异能力“人间失格”也很有趣,只要触碰到别人,就能让对方的异能力失效。
这就像是游戏里的一个超级大bug,让那些原本嚣张的对手瞬间就没了底气。
太宰治还是个超级会耍嘴皮子的人。
他那嘴巴就像一把锋利的剑,总能把人怼得哑口无言。
有时候看着他和别人斗嘴,我就在旁边偷着乐,那些被他怼的人脸上那表情啊,真是丰富多彩。
可有时候呢,他又会说出一些特别有哲理的话。
就像他对生命和死亡的那些看法,虽然听起来有点悲观,但又让人忍不住去思考。
他和他的那些伙伴们之间的关系也很有意思。
他老是捉弄国木田独步,把国木田气得跳脚。
我想国木田心里肯定在想:“我怎么就遇上这么个让人头疼的家伙呢?”但是呢,当真正遇到危险的时候,他们又会毫不犹豫地并肩作战。
这就是他们之间那种独特的羁绊吧。
总的来说,太宰治就像是一颗独特的星星,在文豪野犬的天空中闪耀着属于他自己的光芒。
他的存在让整个故事充满了意想不到的惊喜和转折。
不管是他那些荒诞的自杀举动,还是他在战斗中的智慧和勇气,都让他成为了一个让人难以忘怀的角色。
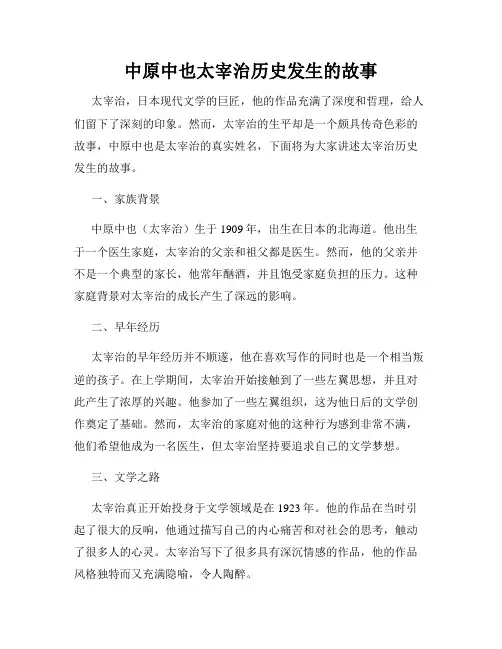
中原中也太宰治历史发生的故事太宰治,日本现代文学的巨匠,他的作品充满了深度和哲理,给人们留下了深刻的印象。
然而,太宰治的生平却是一个颇具传奇色彩的故事,中原中也是太宰治的真实姓名,下面将为大家讲述太宰治历史发生的故事。
一、家族背景中原中也(太宰治)生于1909年,出生在日本的北海道。
他出生于一个医生家庭,太宰治的父亲和祖父都是医生。
然而,他的父亲并不是一个典型的家长,他常年酗酒,并且饱受家庭负担的压力。
这种家庭背景对太宰治的成长产生了深远的影响。
二、早年经历太宰治的早年经历并不顺遂,他在喜欢写作的同时也是一个相当叛逆的孩子。
在上学期间,太宰治开始接触到了一些左翼思想,并且对此产生了浓厚的兴趣。
他参加了一些左翼组织,这为他日后的文学创作奠定了基础。
然而,太宰治的家庭对他的这种行为感到非常不满,他们希望他成为一名医生,但太宰治坚持要追求自己的文学梦想。
三、文学之路太宰治真正开始投身于文学领域是在1923年。
他的作品在当时引起了很大的反响,他通过描写自己的内心痛苦和对社会的思考,触动了很多人的心灵。
太宰治写下了很多具有深沉情感的作品,他的作品风格独特而又充满隐喻,令人陶醉。
四、心理健康问题然而,太宰治的创作天赋和精神状况之间存在着微妙的关系。
他时常陷入深思熟虑的状态,对存在和生活进行反思。
这种深度思考逐渐演变成了他的心理健康问题。
太宰治多次陷入抑郁和自杀的状态,他的作品中也常常流露出对死亡的思考。
然而,正是这种痛苦的经历使得太宰治的作品更加动人和真实。
五、晚年生活太宰治在日本文坛取得了巨大的成就,但他的晚年生活并不幸福。
他的家庭问题和精神状况持续困扰着他,使得他无法真正体验到自己作品所带来的成功和荣誉。
1965年,太宰治在一个风雨交加的夜晚离开了人世,结束了自己短暂而充满坎坷的一生。
六、影响和遗产太宰治的作品不仅仅在当代文坛赢得了极高的声誉,他的作品也在世界范围内产生了深远的影响。
他的作品被翻译成多种语言,被广泛传播,并且在电影、戏剧等领域进行了改编。
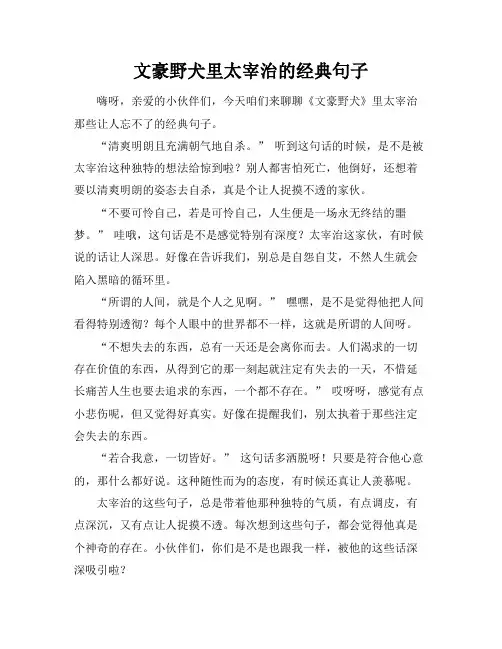
文豪野犬里太宰治的经典句子嗨呀,亲爱的小伙伴们,今天咱们来聊聊《文豪野犬》里太宰治那些让人忘不了的经典句子。
“清爽明朗且充满朝气地自杀。
” 听到这句话的时候,是不是被太宰治这种独特的想法给惊到啦?别人都害怕死亡,他倒好,还想着要以清爽明朗的姿态去自杀,真是个让人捉摸不透的家伙。
“不要可怜自己,若是可怜自己,人生便是一场永无终结的噩梦。
” 哇哦,这句话是不是感觉特别有深度?太宰治这家伙,有时候说的话让人深思。
好像在告诉我们,别总是自怨自艾,不然人生就会陷入黑暗的循环里。
“所谓的人间,就是个人之见啊。
” 嘿嘿,是不是觉得他把人间看得特别透彻?每个人眼中的世界都不一样,这就是所谓的人间呀。
“不想失去的东西,总有一天还是会离你而去。
人们渴求的一切存在价值的东西,从得到它的那一刻起就注定有失去的一天,不惜延长痛苦人生也要去追求的东西,一个都不存在。
” 哎呀呀,感觉有点小悲伤呢,但又觉得好真实。
好像在提醒我们,别太执着于那些注定会失去的东西。
“若合我意,一切皆好。
” 这句话多洒脱呀!只要是符合他心意的,那什么都好说。
这种随性而为的态度,有时候还真让人羡慕呢。
太宰治的这些句子,总是带着他那种独特的气质,有点调皮,有点深沉,又有点让人捉摸不透。
每次想到这些句子,都会觉得他真是个神奇的存在。
小伙伴们,你们是不是也跟我一样,被他的这些话深深吸引啦?。
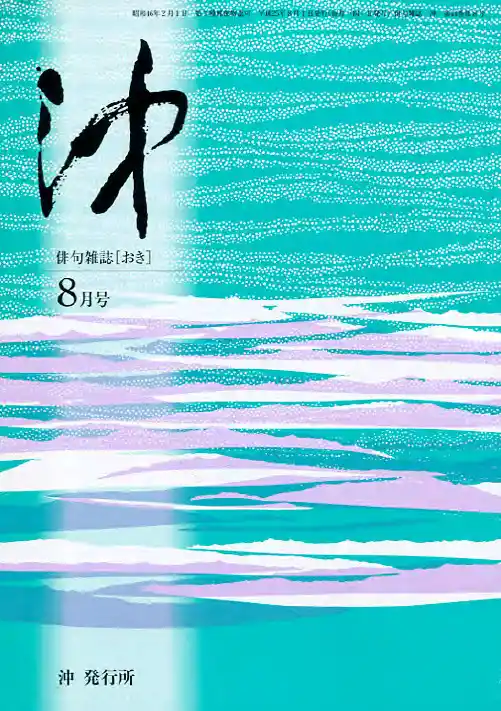
文豪野犬太宰治作文在文豪野犬的世界里,太宰治就像是一颗独特而又捉摸不透的星星。
这家伙啊,乍一看,就是个吊儿郎当的主儿。
那身标志性的沙色风衣,松松垮垮地披在身上,就像他那随性的性格一样。
头发呢,乱乱的,却又有一种别样的潇洒。
他整天脸上挂着似有似无的笑容,你根本猜不透他这个笑容背后到底是真的开心,还是又在算计着什么鬼点子。
太宰治的自杀癖好,那可真是让人又好气又好笑。
你说这人,怎么就老是想着各种办法去结束自己的生命呢?一会儿跳河,一会儿又玩些别的花样。
每次看到他折腾这些自杀的事儿,就感觉他像个调皮捣蛋却又让人忍不住操心的孩子。
不过呢,他每次自杀未遂后的反应也特别有趣,就像什么事儿都没发生一样,拍拍身上的灰,又继续他那神神秘秘的生活了。
他的聪明才智那也是相当惊人的。
在侦探社里,他就像是个智囊团的核心人物,虽然平时看着不靠谱,但一到关键时刻,那脑袋转得比谁都快。
那些复杂的案件,在他眼里就像是小孩子的谜题一样。
他总能从一些别人根本想不到的角度去分析问题,然后轻而易举地找到真相。
就好比他能从一个嫌疑人不经意间的小动作,或者是一句看似无关紧要的话里,挖掘出整个案件的关键线索。
太宰治和他身边的人相处起来也是特别有戏。
他和中也之间的相爱相杀简直就是一场精彩的大戏。
他俩只要一碰面,那空气中都弥漫着一种剑拔弩张又有点诙谐的气氛。
太宰治老是变着法儿地捉弄中也,而中也呢,虽然每次都被气得跳脚,但又拿太宰治没办法。
他们俩就像一对欢喜冤家,谁也离不开谁,缺了对方的话,这出戏可就没那么好看了。
还有他对待女性的态度,那也是很奇特。
他对女性总是有一种温柔的态度,不管是面对敌人还是朋友。
他那温柔的话语和绅士的举止,常常让女性们对他又爱又恨。
有时候他会利用女性的感情来达到自己的目的,但又好像在不经意间流露出一些真诚的情感。
在整个文豪野犬的故事里,太宰治就像是一阵捉摸不定的风。
他带着自己的神秘、幽默、智慧和那一点点让人无奈的任性,在横滨这个充满奇幻与危险的城市里穿梭。
駈込み訴え太宰治申し上げます。
申し上げます。
旦那さま。
あの人は、酷(ひど)い。
酷い。
はい。
厭(いや)な奴です。
悪い人です。
ああ。
我慢ならない。
生かして置けねえ。
はい、はい。
落ちついて申し上げます。
あの人を、生かして置いてはなりません。
世の中の仇(かたき)です。
はい、何もかも、すっかり、全部、申し上げます。
私は、あの人の居所(いどころ)を知っています。
すぐに御案内申します。
ずたずたに切りさいなんで、殺して下さい。
あの人は、私の師です。
主です。
けれども私と同じ年です。
三十四であります。
私は、あの人よりたった二月(ふたつき)おそく生れただけなのです。
たいした違いが無い筈だ。
人と人との間に、そんなにひどい差別は無い筈だ。
それなのに私はきょう迄(まで)あの人に、どれほど意地悪くこき使われて来たことか。
どんなに嘲弄(ちょうろう)されて来たことか。
ああ、もう、いやだ。
堪えられるところ迄は、堪えて来たのだ。
怒る時に怒らなければ、人間の甲斐がありません。
私は今まであの人を、どんなにこっそり庇(かば)ってあげたか。
誰も、ご存じ無いのです。
あの人ご自身だって、それに気がついていないのだ。
いや、あの人は知っているのだ。
ちゃんと知っています。
知っているからこそ、尚更あの人は私を意地悪く軽蔑(けいべつ)するのだ。
あの人は傲慢(ごうまん)だ。
私から大きに世話を受けているので、それがご自身に口惜(くや)しいのだ。
あの人は、阿呆なくらいに自惚(うぬぼ)れ屋だ。
私などから世話を受けている、ということを、何かご自身の、ひどい引目(ひけめ)ででもあるかのように思い込んでいなさるのです。
あの人は、なんでもご自身で出来るかのように、ひとから見られたくてたまらないのだ。
ばかな話だ。
世の中はそんなものじゃ無いんだ。
この世に暮して行くからには、どうしても誰かに、ぺこぺこ頭を下げなければいけないのだし、そうして歩一歩、苦労して人を抑えてゆくより他に仕様がないのだ。
关于太宰治樱花自杀语录
1、因为怯懦,所以逃避生命,以不抵抗在最黑暗的沉沦中生出骄傲,因为骄傲,所以不选择生,所以拒斥粗鄙的乐观主义。
——太宰治
2、责难我自杀,说我应该活下去,但又没有对我伸出任何援手,只知道一个劲儿批评我的家伙肯定是一个能够满不在乎地劝天皇陛下去开水果店的伟人。
——太宰治
3、早晨,我睁眼醒来翻身下床,又变成了原来那个浅薄无知、善于伪装的滑稽角色。
胆小鬼连幸福都会惧怕,碰到棉花都会受伤,有时也会被幸福所伤。
趁着还没有受伤,我想就这样赶快分道扬镳。
我又放出了惯用的逗笑烟幕弹。
——太宰治
4、日日重复同样的事,依循着与昨日无异的惯例。
若能避开猛烈的欢乐,自然也不会有很大的悲伤来访。
——太宰治
5、幸福感这种东西,会沉在悲哀的河底,隐隐发光,仿佛砂金一般。
——太宰治
6、无论多么永恒的形象,骨子里不过都是些卑劣粗俗之物。
——太宰治
7、因为她怀有对人的怜悯关爱之心,才会在无意识中做出关怀我的举动。
她眺望远方的样子,就像一幅画一样宁静安详。
——太宰治。
太宰治樱桃译文樱桃是太宰治的一篇短篇小说,这个故事讲述了一个孤独的男子想象着他的同伴和爱情,而在现实中他只有樱桃这个朋友。
故事的主人公是一个名叫清水的男子,他和一个年轻女子一起生活在一个小镇上。
生活的日子,清水觉得十分单调和乏味,但他却有着梦想和幻想。
清水喜欢孤独,他喜欢在房间里想象自己身边有伙伴和爱情。
他常常幻想着一个美丽的女子,要和他一起散步和奏琴,他也幻想着自己有很多朋友,和他们一起喝酒和聊天。
然而,这些幻想只是他自己心中的梦想,现实中他的生活却十分空虚。
他唯一的伙伴是一棵樱桃树,每年春天,他都会照顾这棵树,等待着它开花结果。
樱桃树开花的那一天,清水就和它一起品尝着美味的樱桃。
一个晚上,清水的梦想破灭了。
他听到房间外面有人在讲一个名叫春江的女子,是他所幻想的女子的真实存在。
他迫不及待地冲出房间,想要证实这个消息的真实性,结果他却被群众给嘲笑了。
清水心灰意冷地回到了自己的房间里,他重新回到了从前的生活,重新握紧了樱桃树上的樱桃。
太宰治在这篇小说中描绘了人们的孤独和对于幸福梦想的追寻。
人们往往被周围的生活环境和自身的状态所束缚,他们张望着未来,追求着幸福和爱情,但往往只有梦中的虚幻存在,没有现实中的真实伙伴。
樱桃树成为了清水的一个伙伴,它陪伴着他孤独的生活。
太宰治在这里通俗地描述了一个人的孤独。
而樱桃的象征也很易懂,它代表着清水寂寞的生活中唯一的喜悦与欣赏,是他梦幻与现实的连接点。
太宰治的文笔虽然简单,但深情地描绘了人们内心的孤独和渴求。
在梦境与现实之间,选择了无尽的孤独。
关于太宰治樱花自杀文案
1、金钱散尽,情缘两断。
2、所谓世间,不就是你吗?
3、不要绝望,就此告辞。
4、回首前尘,仅是耻辱的往事。
5、所谓世人其实就是某个人。
6、唯有尽力自持,不致癫狂。
7、荒谬和愚蠢在恋爱中是大忌。
8、生而为人,我很抱歉。
9、对我而言,人类的生活无从捉摸。
10、人世究竟指的是什么?人的复数?
11、浮萍人生似流水,何苦愁闷川边柳。
12、见一个爱一个的人,实谁都不爱。
13、生病的妻子,滯留的云,鬼芒草。
14、自己对人的恐惧感,扔在心底剧烈翻滚。
15、也许所谓的热情,就是无视对方的立场。
16、积是恋爱,人生一切都要趁机会,未免卑下。
17、多情的家伙总是惧怕那些令人厌烦的道德。
18、懦夫连幸福都害怕,碰到棉花也会受伤。
19、所谓的“孩还然人”,不上以是个人吗?
20、彼此轻视,却又互相往来,使得彼此愈来愈无趣。
大学本科毕业论文(设计)开题报告
学院:外国语学院专业:日语
论文题目太宰治『清貧譚』における女性像について
一、本论文的研究契机
本学期,昭和文学史选修课上,因发表阅读作品感想的需要,我开始接触太宰治的作品。
在阅读作品和查找资料的过程中,对太宰治充满迷幻色彩的一生萌生了兴趣,也产生了希望透过他的其他作品来窥探这个作家的内心世界的念头,于是便决定选择太宰治的作品作为毕业论文课题的研究内容。
另外,他的作品多以女性独白体的形式,或对女性形象较为细致的刻画,从这个角度,我们可以直接或者间接地窥见他个人的内心世界。
太宰治作品中有两部与中国有特殊渊源的短篇。
価し、戦争を起こった人、国などに対して不満をぶちまけるということは分かった。
キーワード:太宰治聊斎志異翻案作女性像
abstract
目次
はじめに。
………
第一章. 時代背景(太平洋戦争)と創作動機について。
……
第二章. 翻案作と原作の異同について。
…
第三章. 太宰治が『聊斎志異』から翻案した作品の女性像。
——『清貧譚』をめぐって。
…
1.中国の伝統的な女性像。
…
2.独立な思想を持つ現代的な女性像。
3.勇敢で、生存力の強い女性像。
…
第四章. 太宰治の後期作品における女性像。
1.母性的な女性。
………
2.新しい女性たち。
………
3.残酷な女性たち。
………
結び。
………
参考文献。
………
引用文献。
………
謝辞。
桜桃太宰治われ、山にむかいて、目を挙(あ)ぐ。
――詩篇、第百二十一。
子供より親が大事、と思いたい。
子供のために、などと古風な道学者みたいな事を殊勝らしく考えてみても、何、子供よりも、その親のほうが弱いのだ。
少くとも、私の家庭においては、そうである。
まさか、自分が老人になってから、子供に助けられ、世話になろうなどという図々しい虫(むし)のよい下心は、まったく持ち合わせてはいないけれども、この親は、その家庭において、常に子供たちのご機嫌(きげん)ばかり伺っている。
子供、といっても、私のところの子供たちは、皆まだひどく幼い。
長女は七歳、長男は四歳、次女は一歳である。
それでも、既にそれぞれ、両親を圧倒し掛けている。
父と母は、さながら子供たちの下男下女の趣きを呈しているのである。
夏、家族全部三畳間に集まり、大にぎやか、大混乱の夕食をしたため、父はタオルでやたらに顔の汗を拭(ふ)き、「めし食って大汗かくもげびた事、と柳多留(やなぎだる)にあったけれども、どうも、こんなに子供たちがうるさくては、いかにお上品なお父(とう)さんといえども、汗が流れる」と、ひとりぶつぶつ不平を言い出す。
母は、一歳の次女におっぱいを含ませながら、そうして、お父さんと長女と長男のお給仕をするやら、子供たちのこぼしたものを拭くやら、拾うやら、鼻をかんでやるやら、八面六臂(はちめんろっぴ)のすさまじい働きをして、「お父さんは、お鼻に一ばん汗をおかきになるようね。
いつも、せわしくお鼻を拭いていらっしゃる」父は苦笑して、「それじゃ、お前はどこだ。
内股(うちまた)かね?」「お上品なお父さんですこと」「いや、何もお前、医学的な話じゃないか。
上品も下品も無い」「私はね」と母は少しまじめな顔になり、「この、お乳とお乳のあいだに、……涙の谷、……」涙の谷。
父は黙して、食事をつづけた。
私は家庭に在(あ)っては、いつも冗談を言っている。
それこそ「心には悩みわずらう」事の多いゆえに、「おもてには快楽(けらく)」をよそわざるを得ない、とでも言おうか。
いや、家庭に在る時ばかりでなく、私は人に接する時でも、心がどんなにつらくても、からだがどんなに苦しくても、ほとんど必死で、楽しい雰囲気(ふんいき)を創(つく)る事に努力する。
そうして、客とわかれた後、私は疲労によろめき、お金の事、道徳の事、自殺の事を考える。
いや、それは人に接する場合だけではない。
小説を書く時も、それと同じである。
私は、悲しい時に、かえって軽い楽しい物語の創造に努力する。
自分では、もっとも、おいしい奉仕のつもりでいるのだが、人はそれに気づかず、太宰(だざい)という作家も、このごろは軽薄である、面白さだけで読者を釣る、すこぶる安易、と私をさげすむ。
人間が、人間に奉仕するというのは、悪い事であろうか。
もったいぶって、なかなか笑わぬというのは、善(よ)い事であろうか。
つまり、私は、糞真面目(くそまじめ)で興覚めな、気まずい事に堪え切れないのだ。
私は、私の家庭においても、絶えず冗談を言い、薄氷を踏む思いで冗談を言い、一部の読者、批評家の想像を裏切り、私の部屋の畳は新しく、机上は整頓(せいとん)せられ、夫婦はいたわり、尊敬し合い、夫は妻を打った事など無いのは無論、出て行け、出て行きます、などの乱暴な口争いした事さえ一度も無かったし、父も母も負けずに子供を可愛がり、子供たちも父母に陽気によくなつく。
しかし、これは外見。
母が胸をあけると、涙の谷、父の寝汗も、いよいよひどく、夫婦は互いに相手の苦痛を知っているのだが、それに、さわらないように努めて、父が冗談を言えば、母も笑う。
しかし、その時、涙の谷、と母に言われて父は黙し、何か冗談を言って切りかえそうと思っても、とっさにうまい言葉が浮かばず、黙しつづけると、いよいよ気まずさが積り、さすがの「通人」の父も、とうとう、まじめな顔になってしまって、「誰(だれ)か、人を雇いなさい。
どうしたって、そうしなければ、いけない」と、母の機嫌(きげん)を損じないように、おっかなびっくり、ひとりごとのように呟(つぶや)く。
子供が三人。
父は家事には全然、無能である。
蒲団(ふとん)さえ自分で上げない。
そうして、ただもう馬鹿げた冗談ばかり言っている。
配給だの、登録だの、そんな事は何も知らない。
全然、宿屋住いでもしているような形。
来客。
饗応(きょうおう)。
仕事部屋(しごとべや)にお弁当を持って出かけて、それっきり一週間も御帰宅にならない事もある。
仕事、仕事、といつも騒いでいるけれども、一日に二、三枚くらいしかお出来にならないようである。
あとは、酒。
飲みすぎると、げっそり痩(や)せてしまって寝込む。
そのうえ、あちこちに若い女の友達(ともだち)などもある様子だ。
子供、……七歳の長女も、ことしの春に生れた次女も、少し風邪をひき易(やす)いけれども、まずまあ人並。
しかし、四歳の長男は、痩せこけていて、まだ立てない。
言葉は、アアとかダアとか言うきりで一語も話せず、また人の言葉を聞きわける事も出来ない。
這(は)って歩いていて、ウンコもオシッコも教えない。
それでいて、ごはんは実にたくさん食べる。
けれども、いつも痩せて小さく、髪の毛も薄く、少しも成長しない。
父も母も、この長男について、深く話し合うことを避ける。
白痴、唖(おし)、……それを一言でも口に出して言って、二人で肯定し合うのは、あまりに悲惨だからである。
母は時々、この子を固く抱きしめる。
父はしばしば発作的に、この子を抱いて川に飛び込み死んでしまいたく思う。
「唖の次男を斬殺(ざんさつ)す。
×日正午すぎ×区×町×番地×商、何某(五三)さんは自宅六畳間で次男何某(一八)君の頭を薪割(まきわり)で一撃して殺害、自分はハサミで喉(のど)を突いたが死に切れず附近の医院に収容したが危篤(きとく)、同家では最近二女某(二二)さんに養子を迎えたが、次男が唖の上に少し頭が悪いので娘可愛さから思い余ったもの」こんな新聞の記事もまた、私にヤケ酒を飲ませるのである。
ああ、ただ単に、発育がおくれているというだけの事であってくれたら!この長男が、いまに急に成長し、父母の心配を憤り嘲笑(ちょうしょう)するようになってくれたら!夫婦は親戚(しんせき)にも友人にも誰にも告げず、ひそかに心でそれを念じながら、表面は何も気にしていないみたいに、長男をからかって笑っている。
母も精一ぱいの努力で生きているのだろうが、父もまた、一生懸命であった。
もともと、あまりたくさん書ける小説家では無いのである。
極端な小心者なのである。
それが公衆の面前に引き出され、へどもどしながら書いているのである。
書くのがつらくて、ヤケ酒に救いを求める。
ヤケ酒というのは、自分の思っていることを主張できない、もどっかしさ、いまいましさで飲む酒の事である。
いつでも、自分の思っていることをハッキリ主張できるひとは、ヤケ酒なんか飲まない。
(女に酒飲みの少いのは、この理由からである)私は議論をして、勝ったためしが無い。
必ず負けるのである。
相手の確信の強さ、自己肯定のすさまじさに圧倒せられるのである。
そうして私は沈黙する。
しかし、だんだん考えてみると、相手の身勝手に気がつき、ただこっちばかりが悪いのではないのが確信せられて来るのだが、いちど言い負けたくせに、またしつこく戦闘開始するのも陰惨だし、それに私には言い争いは殴(なぐ)り合いと同じくらいにいつまでも不快な憎しみとして残るので、怒りにふるえながらも笑い、沈黙し、それから、いろいろさまざま考え、ついヤケ酒という事になるのである。
はっきり言おう。
くどくどと、あちこち持ってまわった書き方をしたが、実はこの小説、夫婦喧嘩(ふうふげんか)の小説なのである。
「涙の谷」それが導火線であった。
この夫婦は既に述べたとおり、手荒なことはもちろん、口汚(くちぎたな)く罵(ののし)り合った事さえないすこぶるおとなしい一組ではあるが、しかし、それだけまた一触即発の危険におののいているところもあった。
両方が無言で、相手の悪さの証拠固めをしているような危険、一枚の札(ふだ)をちらと見ては伏せ、また一枚ちらと見ては伏せ、いつか、出し抜けに、さあ出来ましたと札をそろえて眼前にひろげられるような危険、それが夫婦を互いに遠慮深くさせていたと言って言えないところが無いでも無かった。
妻のほうはとにかく、夫のほうは、たたけばたたくほど、いくらでもホコリの出そうな男なのである。
「涙の谷」そう言われて、夫は、ひがんだ。
しかし、言い争いは好まない。
沈黙した。
お前はおれに、いくぶんあてつける気持で、そう言ったのだろうが、しかし、泣いているのはお前だけでない。
おれだって、お前に負けず、子供の事は考えている。
自分の家庭は大事だと思っている。
子供が夜中に、へんな咳(せき)一つしても、きっと眼(め)がさめて、たまらない気持になる。
もう少し、ましな家に引越して、お前や子供たちをよろこばせてあげたくてならぬが、しかし、おれには、どうしてもそこまで手が廻(まわ)らないのだ。
これでもう、精一ぱいなのだ。
おれだって、凶暴(きょうぼう)な魔物ではない。
妻子を見殺しにして平然、というような「度胸」を持ってはいないのだ。
配給や登録の事だって、知らないのではない、知るひまが無いのだ。
……父は、そう心の中で呟(つぶや)き、しかし、それを言い出す自信も無く、また、言い出して母から何か切りかえされたら、ぐうの音(ね)も出ないような気もして、「誰か、ひとを雇いなさい」と、ひとりごとみたいに、わずかに主張してみた次第なのだ。
母も、いったい、無口なほうである。
しかし、言うことに、いつも、つめたい自信を持っていた。
(この母に限らず、どこの女も、たいていそんなものであるが)「でも、なかなか、来てくれるひともありませんから」「捜せば、きっと見つかりますよ。
来てくれるひとが無いんじゃ無い、いてくれるひとが無いんじゃないかな?」「私が、ひとを使うのが下手(へた)だとおっしゃるのですか?」「そんな、……」父はまた黙した。
じつは、そう思っていたのだ。
しかし、黙した。
ああ、誰かひとり、雇ってくれたらいい。
母が末の子を背負って、用足しに外に出かけると、父はあとの二人の子の世話を見なければならぬ。
そうして、来客が毎日、きまって十人くらいずつある。
「仕事部屋のほうへ、出かけたいんだけど」「これからですか?」「そう。
どうしても、今夜のうちに書き上げなければならない仕事があるんだ」それは、嘘(うそ)でなかった。
しかし、家の中の憂鬱(ゆううつ)から、のがれたい気もあったのである。
「今夜は、私、妹のところへ行って来たいと思っているのですけど」それも、私は知っていた。