日本语教育でことばと文化をどう考えるか日本早稻田大学细川英雄
- 格式:doc
- 大小:45.50 KB
- 文档页数:3
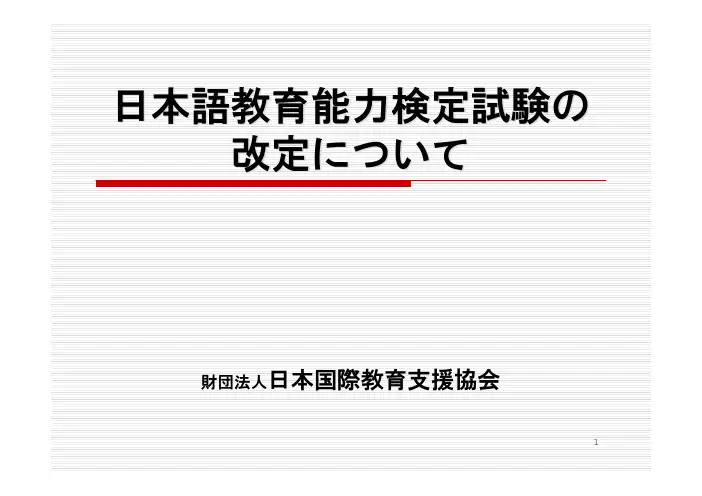
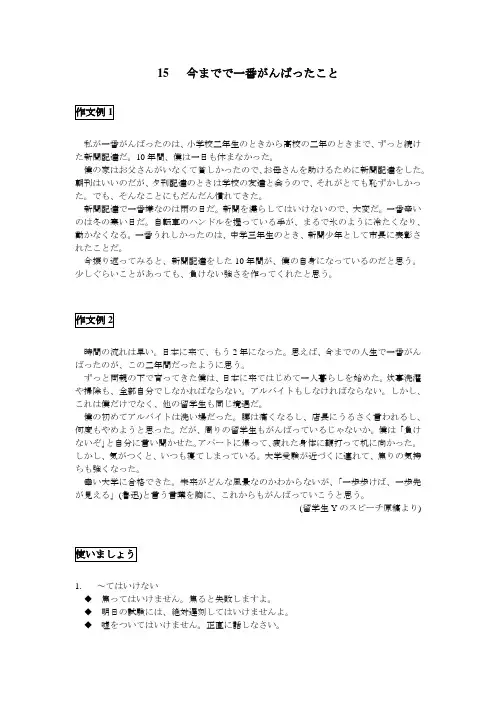
15今までで一番がんばったこと私が一番がんばったのは、小学校二年生のときから高校の二年のときまで、ずっと続けた新聞配達だ。
10年間、僕は一日も休まなかった。
僕の家はお父さんがいなくて貧しかったので、お母さんを助けるために新聞配達をした。
朝刊はいいのだが、夕刊配達のときは学校の友達と会うので、それがとても恥ずかしかった。
でも、そんなことにもだんだん慣れてきた。
新聞配達で一番嫌なのは雨の日だ。
新聞を濡らしてはいけないので、大変だ。
一番辛いのは冬の寒い日だ。
自転車のハンドルを握っている手が、まるで氷のように冷たくなり、動かなくなる。
一番うれしかったのは、中学三年生のとき、新聞少年として市長に表彰されたことだ。
今振り返ってみると、新聞配達をした10年間が、僕の自身になっているのだと思う。
少しぐらいことがあっても、負けない強さを作ってくれたと思う。
時間の流れは早い。
日本に来て、もう2年になった。
思えば、今までの人生で一番がんばったのが、この二年間だったように思う。
ずっと両親の下で育ってきた僕は、日本に来てはじめて一人暮らしを始めた。
炊事洗濯や掃除も、全部自分でしなかればならない。
アルバイトもしなければならない。
しかし、これは僕だけでなく、他の留学生も同じ境遇だ。
僕の初めてアルバイトは洗い場だった。
腰は痛くなるし、店長にうるさく言われるし、何度もやめようと思った。
だが、周りの留学生もがんばっているじゃないか。
僕は「負けないぞ」と自分に言い聞かせた。
アパートに帰って、疲れた身体に鞭打って机に向かった。
しかし、気がつくと、いつも寝てしまっている。
大学受験が近づくに連れて、焦りの気持ちも強くなった。
幸い大学に合格できた。
未来がどんな風景なのかわからないが、「一歩歩けば、一歩先が見える」(魯迅)と言う言葉を胸に、これからもがんばっていこうと思う。
(留学生Yのスピーチ原稿より)1.~てはいけない◆焦ってはいけません。
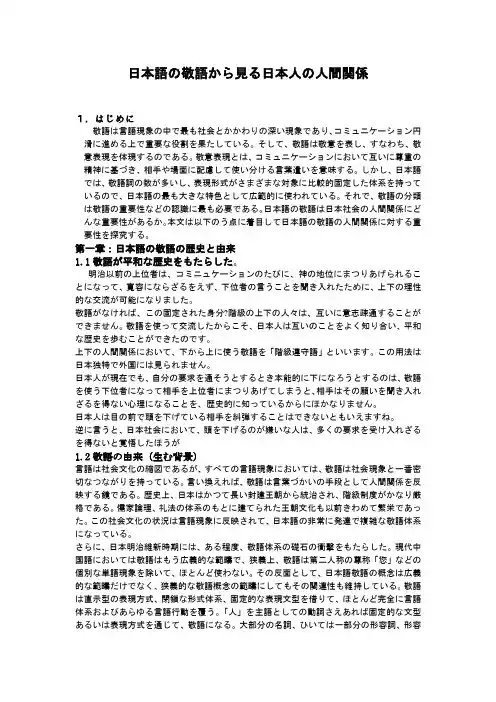
日本語の敬語から見る日本人の人間関係1.はじめに敬語は言語現象の中で最も社会とかかわりの深い現象であり、コミュニケーション円滑に進める上で重要な役割を果たしている。
そして、敬語は敬意を表し、すなわち、敬意表現を体現するのである。
敬意表現とは、コミュニケーションにおいて互いに尊重の精神に基づき、相手や場面に配慮して使い分ける言葉遣いを意味する。
しかし、日本語では、敬語詞の数が多いし、表現形式がさまざまな対象に比較的固定した体系を持っているので、日本語の最も大きな特色として広範的に使われている。
それで、敬語の分類は敬語の重要性などの認識に最も必要である。
日本語の敬語は日本社会の人間関係にどんな重要性があるか。
本文は以下のう点に着目して日本語の敬語の人間関係に対する重要性を探究する。
第一章:日本語の敬語の歴史と由来1.1敬語が平和な歴史をもたらした。
明治以前の上位者は、コミニュケーションのたびに、神の地位にまつりあげられることになって、寛容にならざるをえず、下位者の言うことを聞き入れたために、上下の理性的な交流が可能になりました。
敬語がなければ、この固定された身分?階級の上下の人々は、互いに意志疎通することができません。
敬語を使って交流したからこそ、日本人は互いのことをよく知り合い、平和な歴史を歩むことができたのです。
上下の人間関係において、下から上に使う敬語を「階級遵守語」といいます。
この用法は日本独特で外国には見られません。
日本人が現在でも、自分の要求を通そうとするとき本能的に下になろうとするのは、敬語を使う下位者になって相手を上位者にまつりあげてしまうと、相手はその願いを聞き入れざるを得ない心理になることを、歴史的に知っているからにほかなりません。
日本人は目の前で頭を下げている相手を糾弾することはできないともいえますね。
逆に言うと、日本社会において、頭を下げるのが嫌いな人は、多くの要求を受け入れざるを得ないと覚悟したほうが1.2敬語の由来(生む背景)言語は社会文化の縮図であるが、すべての言語現象においては、敬語は社会現象と一番密切なつながりを持っている。
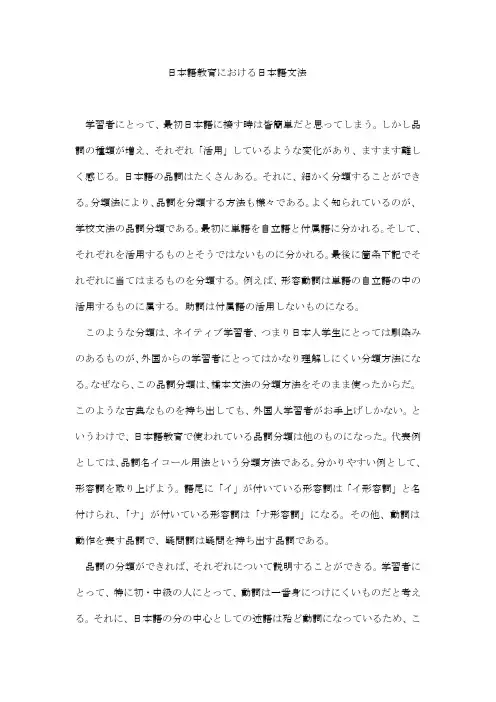
日本語教育における日本語文法学習者にとって、最初日本語に接す時は皆簡単だと思ってしまう。
しかし品詞の種類が増え、それぞれ「活用」しているような変化があり、ますます難しく感じる。
日本語の品詞はたくさんある。
それに、細かく分類することができる。
分類法により、品詞を分類する方法も様々である。
よく知られているのが、学校文法の品詞分類である。
最初に単語を自立語と付属語に分かれる。
そして、それぞれを活用するものとそうではないものに分かれる。
最後に箇条下記でそれぞれに当てはまるものを分類する。
例えば、形容動詞は単語の自立語の中の活用するものに属する。
助詞は付属語の活用しないものになる。
このような分類は、ネイティブ学習者、つまり日本人学生にとっては馴染みのあるものが、外国からの学習者にとってはかなり理解しにくい分類方法になる。
なぜなら、この品詞分類は、橋本文法の分類方法をそのまま使ったからだ。
このような古典なものを持ち出しても、外国人学習者がお手上げしかない。
というわけで、日本語教育で使われている品詞分類は他のものになった。
代表例としては、品詞名イコール用法という分類方法である。
分かりやすい例として、形容詞を取り上げよう。
語尾に「イ」が付いている形容詞は「イ形容詞」と名付けられ、「ナ」が付いている形容詞は「ナ形容詞」になる。
その他、動詞は動作を表す品詞で、疑問詞は疑問を持ち出す品詞である。
品詞の分類ができれば、それぞれについて説明することができる。
学習者にとって、特に初・中級の人にとって、動詞は一番身につけにくいものだと考える。
それに、日本語の分の中心としての述語は殆ど動詞になっているため、これから、動詞を中心として、日本語の文法を分析しよう。
橋本文法の動詞の分類表を使うと、外国人学習者に対して不明な部分がいくつかがある。
「終止形」と「連用形」など、名前の概念はその一つだと考える。
日本語学について心得のない学習者はおそらく上級レベルになっても分からないままだと考える。
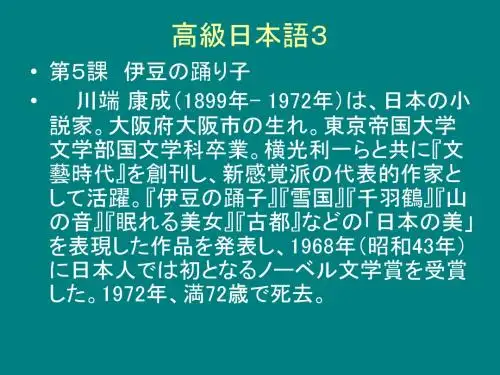
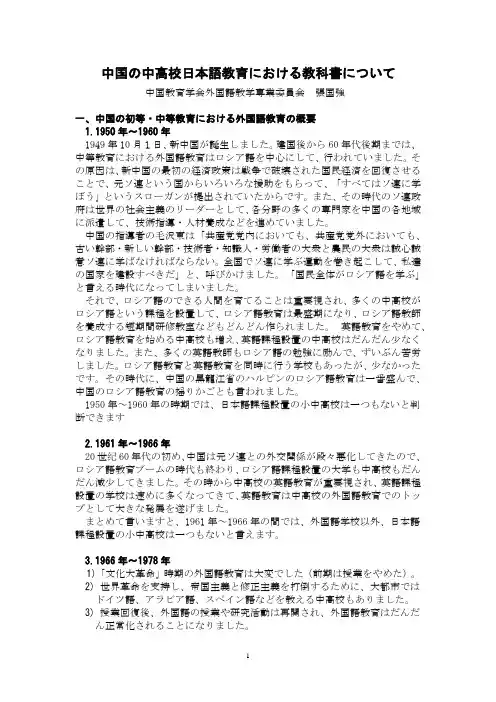
中国の中高校日本語教育における教科書について中国教育学会外国語教学専業委員会張国強一、中国の初等・中等教育における外国語教育の概要1.1950年~1960年1949年10月1日、新中国が誕生しました。
建国後から60年代後期までは、中等教育における外国語教育はロシア語を中心にして、行われていました。
その原因は、新中国の最初の経済政策は戦争で破壊された国民経済を回復させることで、元ソ連という国からいろいろな援助をもらって、「すべてはソ連に学ぼう」というスローガンが提出されていたからです。
また、その時代のソ連政府は世界の社会主義のリーダーとして、各分野の多くの専門家を中国の各地域に派遣して、技術指導・人材養成などを進めていました。
中国の指導者の毛沢東は「共産党党内においても、共産党党外においても、古い幹部・新しい幹部・技術者・知識人・労働者の大衆と農民の大衆は誠心誠意ソ連に学ばなければならない。
全国でソ連に学ぶ運動を巻き起こして、私達の国家を建設すべきだ」と、呼びかけました。
「国民全体がロシア語を学ぶ」と言える時代になってしまいました。
それで、ロシア語のできる人間を育てることは重要視され、多くの中高校がロシア語という課程を設置して、ロシア語教育は最盛期になり、ロシア語教師を養成する短期間研修教室などもどんどん作られました。
英語教育をやめて、ロシア語教育を始める中高校も増え、英語課程設置の中高校はだんだん少なくなりました。
また、多くの英語教師もロシア語の勉強に励んで、ずいぶん苦労しました。
ロシア語教育と英語教育を同時に行う学校もあったが、少なかったです。
その時代に、中国の黒龍江省のハルピンのロシア語教育は一番盛んで、中国のロシア語教育の揺りかごとも言われました。
1950年~1960年の時期では、日本語課程設置の小中高校は一つもないと判断できます2.1961年~1966年20世纪60年代の初め、中国は元ソ連との外交関係が段々悪化してきたので、ロシア語教育ブームの時代も終わり、ロシア語課程設置の大学も中高校もだんだん減少してきました。
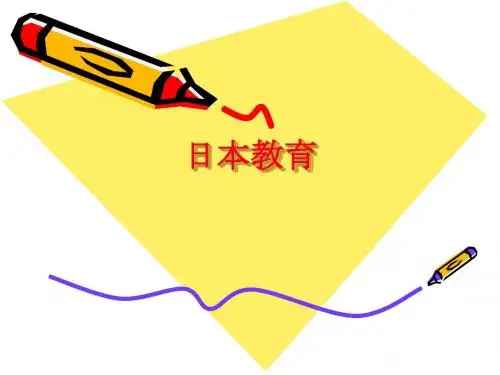
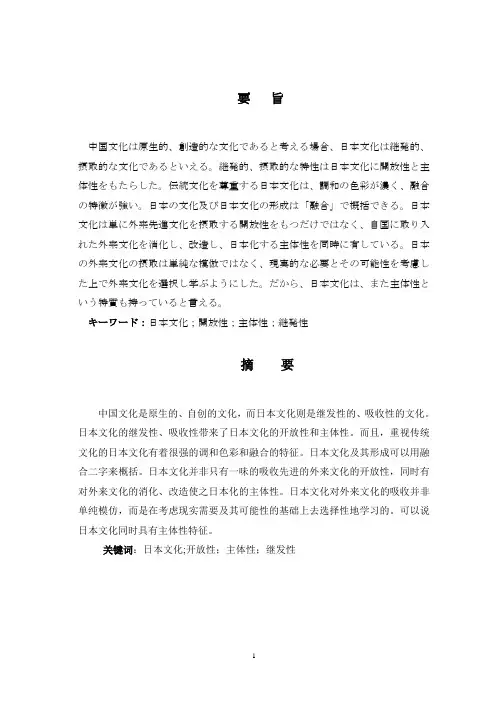
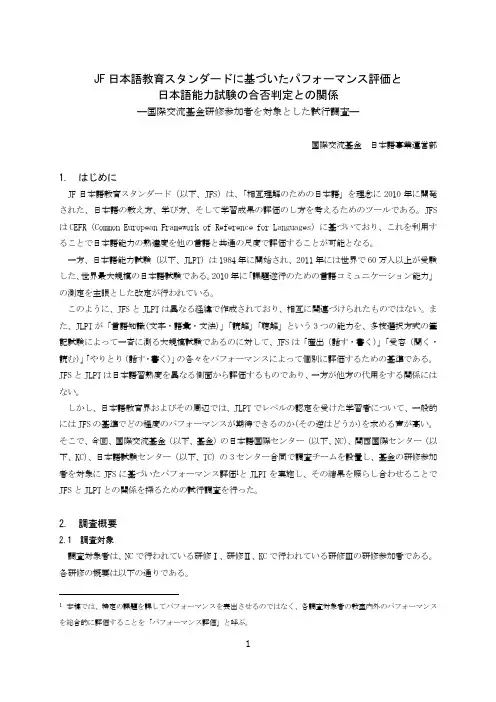
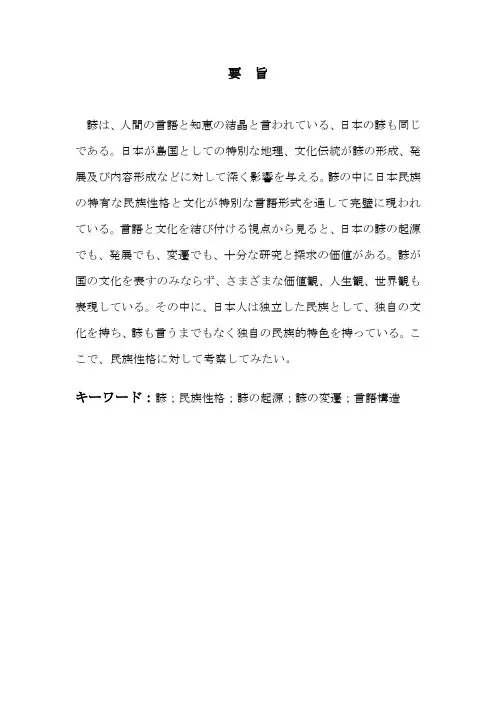
要旨諺は、人間の言語と知恵の結晶と言われている、日本の諺も同じである。
日本が島国としての特別な地理、文化伝統が諺の形成、発展及び内容形成などに対して深く影響を与える。
諺の中に日本民族の特有な民族性格と文化が特別な言語形式を通して完壁に現われている。
言語と文化を結び付ける視点から見ると、日本の諺の起源でも、発展でも、変遷でも、十分な研究と探求の価値がある。
諺が国の文化を表すのみならず、さまざまな価値観、人生観、世界観も表現している。
その中に、日本人は独立した民族として、独自の文化を持ち、諺も言うまでもなく独自の民族的特色を持っている。
ここで、民族性格に対して考察してみたい。
キーワード:諺;民族性格;諺の起源;諺の変遷;言語構造日本の諺から日本の民族性格を探求する第一章序論言語と文化は密接な関係がある。
どんな言語でも文化と離れて独立して存続することが出来ない。
言語は文化の中に存在すると同時に文化の基盤である。
だから、言語表現形式として一番の宝物挙げられる諺は、世界で最も豊富で多彩な成語、諺の大宝庫を持っている。
まず、私たち知るべきのは、日本の諺が庶民から生まれるものである。
諺には、人々の哀楽だけではなく、自然と人間の関係、動物、植物までなどの内容もふくめている。
人間の生活経験から作られたさまざまな知恵は、漢字で記録されではなく、諺の形式として口で代々に伝えていく。
今、私たち本で見た諺は、後輩の収集と整理したものである。
これは、めいめいのながい人生経験から悟った知恵と結晶である、ただの人生の教訓、処世の学問ではなく。
日本の国民も豊かな諺を持っているが、その中に外国からの諺もすくなくない。
もし、外国からの諺がないとしたら、日本人の民族性格も分からず、諺の中の借りる文化、外来文化も不自然になるだろう。
もう一つ強調したいのは、諺がいつも変わっていくということだ。
特に若者たちは現代の視点から理解と解釈している諺が新しい生命力を感じている。
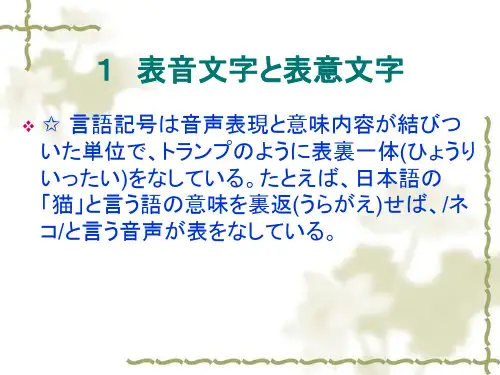
些細なことに投影される民族の精神近現代における日本の躍進の速さは、何につけ目を見張るものがある。
総合的な国力は日増しに強大になり、社会環境には秩序がある。
これは、日本独特の地理的環境がそうさせたと言うより、むしろ民族の精神が生み出した結果である。
私は日本へ行ったことはないが、幸い国内で訪中の日本人と交流を持ったことはある。
日本人が見せる"いちいち言うに値しないこと"に対する表現や反応から、その優れた国民の素質を伺うことができる。
また、民族としてのものの考え方もそこに投影されている。
あれは1999年の末のこと、中国視察に訪れた日本人を日本留学の経験者である従兄が接待することになり、私もそれに同行する機会を得た。
顔を合わせると直ぐ、彼ら日本人の笑顔は桜さながらに美しく綻んだ。
続いて握手、会釈、お辞儀をしながら「よろしくご指導ください」、「よろしくお願いします」というような中国語を話してきた。
本来こうしたマナーは語るに及ばないが、私はあることに気づいた。
彼らはその場にいた接待スタッフの全て、まだ16歳の私も含め、皆に対して同様の礼儀正しい言動をとり、面倒そうな様子は全く見せなかったのだ。
実際、他人から握手を求められたのは、あの時が初めてだった。
私は、突然大人になって他人様の尊敬を受け一人前の人間として認められたような感覚に囚われた。
この小さな出来事を後で従兄に話すと、それは日本民族が個々の生命を尊重していることの現れであると教えてくれた。
日本民族の観念の中では、全ての個体に「命」があり、いずれにも尊重される権利があるというのだ。
また、彼によると、日本は満開の桜のように、人と人との間では調和が重んじられ、相互に尊重し、誰もが自分の立ち位置を持っているという。
また、一行が休憩時にお茶を飲んでいた時のこと、接待側の一人が日本で買ったという壊れた日本製の腕時計を取り出し、国内には部品がないので、日本に持ち帰って修理してもらえないかと声をかけた。
调查报告年尐者日本語学習意識と環境についての調査張国強1.調査概要:予備班の生徒たちは11歳か12歳の年尐者で、どんな態度と方法で日本語を勉強しているか、また日本の何に興味・関心を持っているか、日本語教師としては日本語教育の目的を実現するために、学習者の日本語学習意識と環境を調べなければなりません。
それで,アンケート調査を行いました。
1~6は選択式,7は記入式で複数回答有りです。
2.調査企画:上海市日本語教育研究センター3.調査期間:2008年4月24日~2008年5月10日4.調査対象:甘泉外国語中学予備班の生徒(四つのクラス)5.調査方法:アンケートでの回答6.対象性別:男生徒72人、女生徒75人7.回答者数:147人アンケートの結果を以下に掲載いたします。
1.毎日日本語を読みますか。
「はい」と答えた人へ①いつ読みますか。
②どれぐらい読みますか。
③どのように読みますか。
「はい」と答えた人へ①いつ。
③聞く方法についてA.聞くだけB.テープについて読むC.ほかのことをしながら聞く「はい」と答えた人へ6.日本語学習の主な目的は?ア.留学イ.通訳になるウ.外交官になるエ.日本との貿易の仕事オ.日本で仕事をするカ.日本の大学に入るキ.中国にある日本の会社に入るク.日本語を使ってほかの仕事をするケ.旅行社に入るランキング7.日本の何に関心をもっていますか。
(主な三つのことを書いてください)1 はじめに筆者は、8年間にわたって小学校で外国児童の日本語授業に参加し、教育現場で問題に直面するたびに様々な研究や報告を参考にしてきた。
本稿では、1970年代後半から2004年までの研究で入手できたものを年代項に概観し、以下の疑問について考察する。
小学生、中学生を対象とする日本語教育である。
」<今までの研究対象者の年齢的特徴と母語による特徴>小学生対象の研究が多い(低学年は尐ない)。
幼児、中学生、高校生、それ以上は尐ない。
職場で日本語敬語の使用要旨:敬語は、日本語の最も顕著な特徴の一つであり、日本語を学ぶ時の非常に難しいところでもある。
特に職場に入ろうとしている私たちにとって、敬語の使う方法を了解したとしても、敬語をどうのように適切に使うか、さっぱい分からない。
いったい、職場での敬語の使用規則は何か。
違う種類の敬語はどの場合に使うか。
また、敬語を使う時によくある間違いは何か。
もし、職場でコミュニケーションを順調に進めたいとしたら、これらを注意すべきだを思う。
キーワード:敬語尊敬語謙譲語丁寧語始めに:日本語の敬語というのは、話し手と聞き手、および話題人物との間のさまざまな関係にもとづいて言葉の使い分けとその人間関係を明らかにする表現形式のことである。
敬語は日本人の思想感情、考え方、交際礼儀、人間関係を体現する文化精華であり、日本人の必要とする基本的なマーナである。
敬語をもっている日本人は、それがいることが空気のように当たり前に感じる。
だから、日本語会話に敬語がないことは不可能である。
ぴったりに敬語を使うことは日本語が上手に話せることのしるしだけでなく、日本人と有効的にコミュニケーションする鍵である。
1、職場での敬語の使用規則敬語の使用規則は主に以下の両面である。
1.1、上下関係上下関係、つまりポストの低い人はポストの高い人に、若者は年寄りに敬語を使うことである。
現在の日本はクラス制度を消したといっても、人と人との間に個人条件の差別によって、そんな上下関係もある。
例えば、毎日新聞社は皇太子と小和田雅子と結婚することを報道するとき、タイトルは「皇太子様と小和田雅子さん」。
これを見ると、その上下関係がすぐに分かる。
だから、私たちの地位の上でも、年齢の上でも、上の人に敬語を使うべきである。
でも、「うち」と「そと」との違いによって、上下関係は適切な変化をする。
その特別性を以下に説明する。
1.2、親疎関係親疎関係、つまり見知らぬ人と他人に敬語を使い、身内の人と親しい人に敬語を使わないことである。
日本語から見た日本人—日本人は「集団主義的」か—廣瀬幸生・長谷川葉子1.はじめに日本人は集団主義的である、というのが日本文化論において日本人を特徴づける最も顕著な見方である。
この見地から、日本人は自我意識に欠けるとか、日本社会は対立を避け和を尊ぶといった考え方も生じる。
この集団主義の見方は、文化人類学・社会学・社会心理学を始めとして多くの分野における日本研究に現われる(南1994、杉本・ロス1995などを参照)。
日本語の言語文化研究もその例外ではなく、日本語は集団主義と不可分の関係にある「ウチ・ソト」の概念によって特徴づけられるとする研究もある(Bachnik and Quinn 1994、牧野1996など)。
このような日本文化論は、よく知られているように、日本人・日本社会は特殊であり異質だという神話を生み出し、多くの日本人もまた、それを盲目的に信じ込んできたきらいがある。
しかし近年(特に80年代以降)、文化人類学や社会学などの分野で日本文化論が再考され、いわゆる日本特殊論あるいは日本異質論に対して批判を加える研究が発表されている(ベフ1987、杉本・ロス1995、濱口1996、青木1999など)。
1本稿では、言語研究の立場から、個の欠如とまで言われる日本人の集団性を検討し、そのような集団モデルは日本語の本質的特徴とは相容れないことを明らかにする。
もちろん、集団性を示唆すると思える現象が日本語に多いことは否定できないが、本稿で論じる重要な点は、そのような現象の背後に、実は、英語などの西洋語以上に、個の意識に根ざした言語体系が存在するということである。
2本稿の構成は次の通りである。
まず第2節で社会・文化モデルと言語との一般的な関係について述べ、第3節で、日本人に関する集団モデルとそれに基づく相対的で流動的な自己という考え方を、それを動機づけるとされる言語現象とともに概観する。
1さらにまた、Yoshino (1992) や吉野 (1997) のように、日本特殊論批判にも検討を加える論考もある。
日本語教育でことばと文化をどう考えるか早稲田大学大学院日本語教育研究科教授細川英雄1.ことばと文化の関係言語を学ぶためには文化の理解が必要というのは、おそらくだれでもが持っている常識なのかもしれません。
たとえば、日本語を学ぶためには、日本文化の知識が必要で、それが日本人の行動の仕方やものの考え方を理解することにつながる、という解釈は、それこそ多くの人たちに共通な現象だろうと思います。
しかし、本当にそれでいいのだろうか、という問いを、わたしは日本語を教えはじめてからずっと心に抱きつづけてきました。
この問いは、日本語教育において日本文化をどう捉えるか、という問題であり、日本語と日本文化の結びつきを考えることでした。
そして、それは、文化とは何か、という問いであるとともに、言語教育全体のことばと文化の関係を問い直すことでもあったのです。
2.「日本人らしさ」の日本語教育戦後から70年代ごろまでの日本語教育は、構造主義の影響を色濃く受けた「構造シラバス」と呼ばれる考え方が一般的で、文法を初級から積み上げていくという方法がとられてきました。
これは、日本の英語教育が長く採用してきた方法で、ことばの運用よりも、知識を重視し、構造を学習することで、その言語を知るという方法だといってもいいと思います。
文化の問題は、文学、歴史、建築、宗教など、主にそれぞれの分野の専門家に任されていました。
言語教育論としてこのころ紹介されたのが、池田摩耶子『日本語再発見』(三省堂新書1977)という本で、当時まだ新しい分野であった外国人のための日本語教育への導入として注目を集め、人気を呼びました。
池田は、日本語ネイティブ教師の立場から、日本語教師は言語学的知識とともに、日本文化に対する複眼的視野を持たなければならないと説き、母語話者としての内からの視点と同時に日本語学習者としての外からの視点を持つために、日本の文化を意識すること、学習者の文化を学ぶことが必要としています。
そして、外国人に日本語を教える際、文法や音声、表記などと同等に、日本語の背景にある日本人の発想や観念などにも、十分な注意を払わなければならないと述べています。
日本語が日本の文化として生まれて来た産物である以上、日本語の教育はすなわち日本の文化を外国人に教えること、すなわち「日本人らしさ」をどう教えるかであるとする考え方です。
3.予備知識としての「日本文化」80年代に入ると、コミュニケーション能力が問題にされるようになり、ことばを知識としてではなく、運用能力をつけようという考え方が一般的になってきました。
これは、コミュニカティブ・アプローチという考え方によるものです。
経済大国ニッポンの隆盛の影響もあり、学習者数が急増し、「文化」の問題も専門家だけに任せておくわけにはいかなくなったわけです。
学習者のニーズとしても、伝統的な日本の歴史・文学よりも、もっと現代的な、また日常的な日本人の生活の実態を知りたいという要求が強くなりました。
この考え方を明確に示したのが、ネウストプニー.J.V『外国人とのコミュニケーション』(岩波新書1982年)です。
この考え方は、アメリカの社会学者ハイムズの理論を元にしたもので、コミュニケーションには対象の国の社会・文化を知るための「社会文化能力」が必要という考え方に基づいています。
この立場では、「概念・機能シラバス」という考え方とも連動し、モデル・パターンを示すという方法がとられることがしばしばあります。
たとえば、ロールプレイなどのタスクを利用し、そのタスクをこなすことが実際の場面に役立つとしています(これは現在でも最先端の実践のようにして紹介されることがありますが)。
ここで問題なのは、日本語を理解するためには、日本人の行動様式やものの考え方を知り、それを実際のコミュニケーション場面の予備知識とする考え方です。
たしかに、日本人の行動パターンは、統計的な調査等によって示すことはできても、日本人すべてがそのように行動するわけではありません。
また、日本人の思考方法といっても、具体的に日本人すべてがどのように思考するのかというようなことはわかるはずはありません。
あくまでも傾向や特徴という形で示すことはできても、それ以上のものにはなり得ないからです。
ここに予備知識を用意するという発想そのものに問題があることになります。
4.「個の文化」への視点これまでは、社会という集団を1つの固定したまとまりの枠組みとした上で、ここに「文化」という営為およびそれに伴う事象があると捉えられてきました。
たとえば、物質・行動・精神のような分類や「見える」「見えない」のような区別も、すべてこの枠組みの中で行われてきています。
この考え方は、「文化」という、ある実体が存在し、それに対する共通の認識があるという解釈です。
しかし、「文化」が動態的であるという立場に立つと、この実体は何なのかということが問題となるでしょう。
流動的であるがその実体はあるのか、あるいは、実体がないからこそ流動的なのか。
この答えはまだ出ていません。
一方、人間の認識そのものが流動的であることは容易に判断できるでしょう。
認識とは個人の中にあるものであり、一人一人の価値観とも連動するものですから、認識の仕方や方法あるいはその表出がそれぞれ異なるのは考えてみれば当たり前のことなのです。
集団は、認識や判断の主体とはなり得ません。
集団が、ある意思を持つかのように見えるのは、擬人化や象徴化のような現象だと考えることができます。
つまり、個人の何らかの意図が自覚的あるいは無自覚的に反映しているわけです。
個人は自らを取り囲む、さまざまな社会の影響を受けつつ成長し、それぞれの社会は個人の考え方や立場を映し出す鏡として成立します。
もちろん、個人は環境としての社会の影響を受けつつ成長するわけですが、では、その環境としての社会が人間のすべてを決定してしまうかというと決してそうではありません。
そこから抜け出して、違う自分を発見し、創造的な解決を目指すことができる可能性を個人としては十分に持っています。
その役割を果たすのが、コミュニケーションという行為なのです。
だからこそ、この個人の創造性を引き出す役割を担っているコミュニケーション能力育成ということが、言語教育の目的となり得るのではないでしょうか。
5.教育実践活動としての実現へこのような考え方に立った場合、具体的な教育実践活動が大きく変容することになります。
なぜなら、「個の文化」として個人の中にあるものを学習/教育の課題とすることは、固定化した集団社会に関する知識・情報の受容ではなく、まず個人の中に備わっている力をどのようにして引き出すかということが当面の課題になるからです。
次に、そのインターアクションのプロセスにおいて他者の「文化」との協働をどのように創りあげていくか、ということが教育の理念として展開されるからです。
この図は、対象としての「情報」を取り込んで、それに対しての自分の「考えていること」の把握がはじまり、その「把握したもの」をどのようにして相手に伝達するかというプロセスを示したものです。
さらに、それに対する相手からの反応の確認があってはじめて、コミュニケーションが成立するという、個人の中の思考と表現の往還のための相互関係も表しています。
ここまで述べてきて、ようやく「日本語教育で日本文化を教える」という発想そのものに問い直しが必要となることにわたしたちは気づきます。
6.“言語学習の環境をつくる”ということことばの活動を生きたものとして考えようとするためには、その構造や体系を固定的なものとして原理追求的に分析するのではなく、むしろ人間一人一人がどのようにそれを身につけることができるのか、それにはどのような環境づくりが必要で、さらにそこで担当者はどのような支援ができるのか、といった視点が不可欠になります。
わたしの主張は、人は一人一人違う文化を持っている、それを国籍や民族で簡単に境界を引いてしまうのは危険だ、だから、必要なことは、まず人が一人一人持っている「文化」を引き出し、それを相互に議論していくことだ、というものです。
ですから、日本語教育は、そのような環境をどのようにつくるかということを考えなければならないと思います。
複数の民族や複数の言語が混ざり合ったからといって、簡単に多文化主義だなどということはできません。
言語教育がさまざまな制度や権力によって都合のよいように利用されてきたことは、日本語教育の戦前の歴史を見てもわかります。
最も重要なことは、そうした制度や権力に負けない、強くて柔軟な個人をことばの教室でどのように育成していくことができるかという思想なのです。
くわしい文献その他の問い合わせは次のホームページへ早稲田大学大学院日本語教育研究科言語文化教育研究室http://www.f.waseda.jp/hosokawa/【ことばと文化について考えるための参考文献】○日本語教育と日本事情の関係について、さらに詳しく知るためには:細川英雄『日本語教育と日本事情』明石書店1999○ことばと文化を統合する考え方の背景や歴史を体系的に知るためには:細川英雄『日本語教育は何をめざすか-言語文化活動の理論と実践』明石書店2002○ことばと文化を統合する具体的な教室実践を知るためには:細川英雄+NPOスタッフ『考えるための日本語-問題を発見・解決する総合活動型日本語教育のすすめ』明石書店2004○母語と第二言語の別を越えた日本語教育の実践を知るには:牲川波都季+細川英雄『わたしを語ることばを求めて-表現することへの希望』三省堂2004○日本語教育におけることばと文化の教育の現在の状況を知るためには:細川英雄編『ことばと文化を結ぶ日本語教育』凡人社2002このコーナーでは、これから研究を目指す海外の日本語の先生方のために、日本語学・日本語教育の研究について情報をおとどけしています。