日本文化 日本花道 ppt
- 格式:ppt
- 大小:5.14 MB
- 文档页数:18
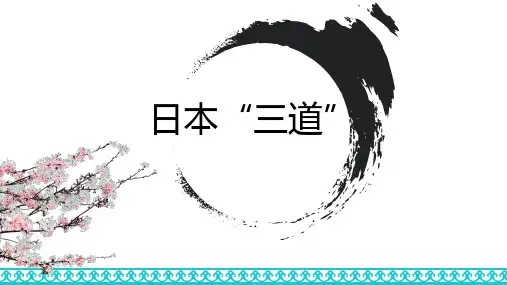




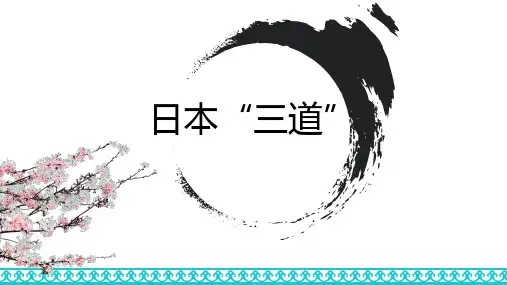

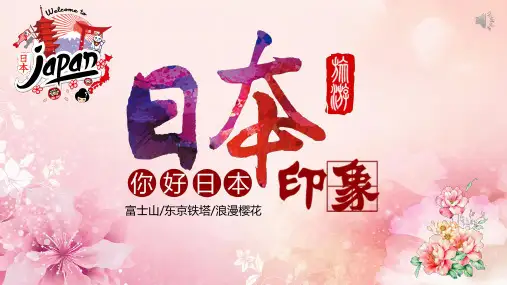
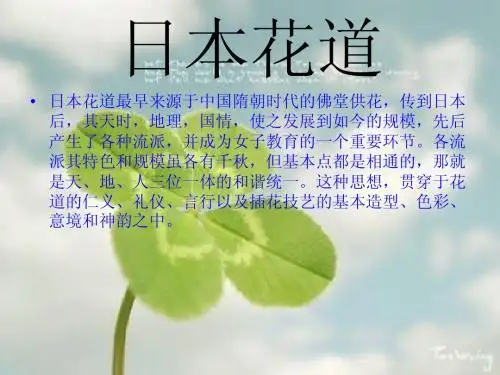

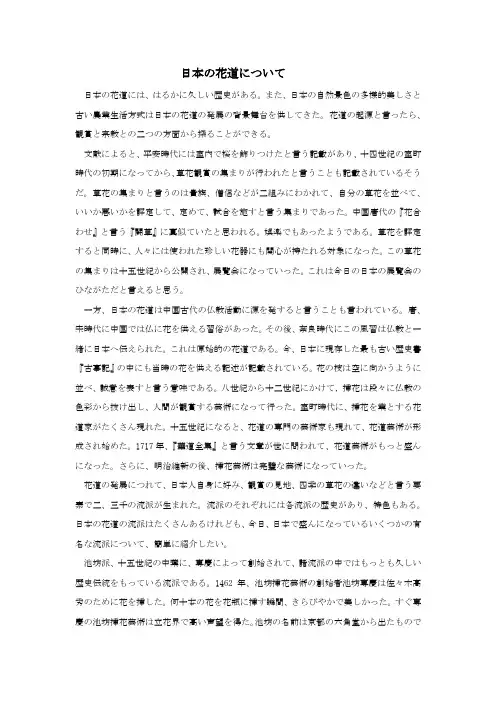
日本の花道について日本の花道には、はるかに久しい歴史がある。
また、日本の自然景色の多様的美しさと古い農業生活方式は日本の花道の発展の背景舞台を供してきた。
花道の起源と言ったら、観賞と宗教との二つの方面から探ることができる。
文献によると、平安時代には室内で桜を飾りつけたと言う記載があり、十四世紀の室町時代の初期になってから、草花観賞の集まりが行われたと言うことも記載されているそうだ。
草花の集まりと言うのは貴族、僧侶などが二組みにわかれて、自分の草花を並べて、いいか悪いかを評定して、定めて、試合を施すと言う集まりであった。
中国唐代の『花合わせ』と言う『闘草』に真似ていたと思われる。
娯楽でもあったようである。
草花を評定すると同時に、人々には使われた珍しい花器にも関心が持たれる対象になった。
この草花の集まりは十五世紀から公開され、展覧会になっていった。
これは今日の日本の展覧会のひながただと言えると思う。
一方、日本の花道は中国古代の仏教活動に源を発すると言うことも言われている。
唐、宋時代に中国では仏に花を供える習俗があった。
その後、奈良時代にこの風習は仏教と一緒に日本へ伝えられた。
これは原始的の花道である。
今、日本に現存した最も古い歴史書『古事記』の中にも当時の花を供える記述が記載されている。
花の枝は空に向かうように並べ、誠意を表すと言う意味である。
八世紀から十二世紀にかけて,挿花は段々に仏教の色彩から抜け出し、人間が観賞する芸術になって行った。
室町時代に、挿花を業とする花道家がたくさん現れた。
十五世紀になると、花道の専門の芸術家も現れて、花道芸術が形成され始めた。
1717年、『華道全集』と言う文章が世に問われて、花道芸術がもっと盛んになった。
さらに、明治維新の後、挿花芸術は完璧な芸術になっていった。
花道の発展につれて、日本人自身に好み、観賞の見地、四季の草花の違いなどと言う要素で二、三千の流派が生まれた。