研究计划书(日文版本)
- 格式:doc
- 大小:49.00 KB
- 文档页数:5
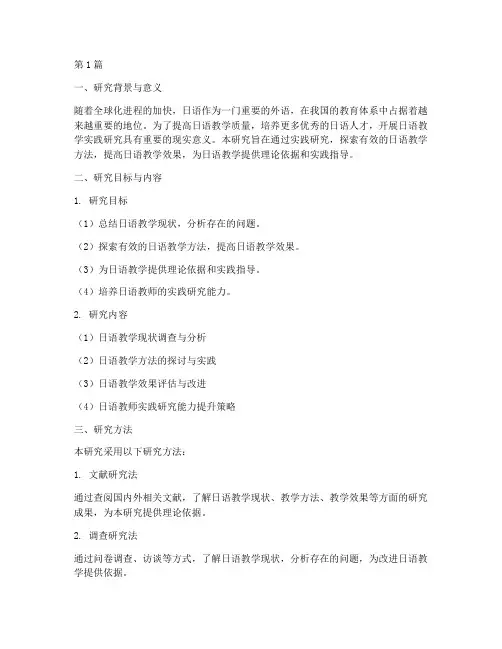
第1篇一、研究背景与意义随着全球化进程的加快,日语作为一门重要的外语,在我国的教育体系中占据着越来越重要的地位。
为了提高日语教学质量,培养更多优秀的日语人才,开展日语教学实践研究具有重要的现实意义。
本研究旨在通过实践研究,探索有效的日语教学方法,提高日语教学效果,为日语教学提供理论依据和实践指导。
二、研究目标与内容1. 研究目标(1)总结日语教学现状,分析存在的问题。
(2)探索有效的日语教学方法,提高日语教学效果。
(3)为日语教学提供理论依据和实践指导。
(4)培养日语教师的实践研究能力。
2. 研究内容(1)日语教学现状调查与分析(2)日语教学方法的探讨与实践(3)日语教学效果评估与改进(4)日语教师实践研究能力提升策略三、研究方法本研究采用以下研究方法:1. 文献研究法通过查阅国内外相关文献,了解日语教学现状、教学方法、教学效果等方面的研究成果,为本研究提供理论依据。
2. 调查研究法通过问卷调查、访谈等方式,了解日语教学现状,分析存在的问题,为改进日语教学提供依据。
3. 实验研究法选取一定数量的日语学习者作为实验对象,进行不同教学方法的对比实验,评估教学效果。
4. 案例研究法选取具有代表性的日语教学案例,分析其成功经验和存在的问题,为日语教学提供借鉴。
四、研究步骤1. 准备阶段(第1-2周)(1)确定研究课题,制定研究计划。
(2)查阅相关文献,了解日语教学现状。
(3)确定研究对象,收集相关数据。
2. 实施阶段(第3-10周)(1)进行日语教学现状调查与分析。
(2)开展日语教学方法的探讨与实践。
(3)进行实验研究,评估教学效果。
(4)撰写案例研究报告。
3. 总结阶段(第11-12周)(1)对研究结果进行总结与分析。
(2)撰写研究论文,提交研究成果。
五、预期成果1. 学术成果(1)形成一篇关于日语教学实践研究的学术论文。
(2)撰写一篇日语教学案例研究报告。
2. 实践成果(1)提出改进日语教学的具体措施。
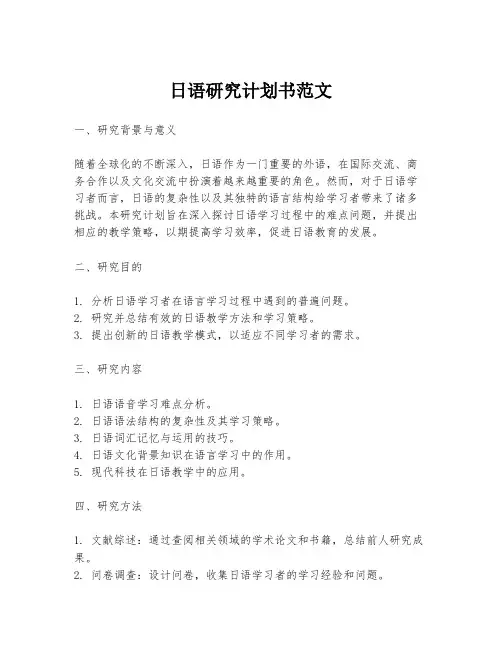
日语研究计划书范文一、研究背景与意义随着全球化的不断深入,日语作为一门重要的外语,在国际交流、商务合作以及文化交流中扮演着越来越重要的角色。
然而,对于日语学习者而言,日语的复杂性以及其独特的语言结构给学习者带来了诸多挑战。
本研究计划旨在深入探讨日语学习过程中的难点问题,并提出相应的教学策略,以期提高学习效率,促进日语教育的发展。
二、研究目的1. 分析日语学习者在语言学习过程中遇到的普遍问题。
2. 研究并总结有效的日语教学方法和学习策略。
3. 提出创新的日语教学模式,以适应不同学习者的需求。
三、研究内容1. 日语语音学习难点分析。
2. 日语语法结构的复杂性及其学习策略。
3. 日语词汇记忆与运用的技巧。
4. 日语文化背景知识在语言学习中的作用。
5. 现代科技在日语教学中的应用。
四、研究方法1. 文献综述:通过查阅相关领域的学术论文和书籍,总结前人研究成果。
2. 问卷调查:设计问卷,收集日语学习者的学习经验和问题。
3. 访谈法:与日语教师和学习者进行深入访谈,了解教学和学习过程中的具体情况。
4. 案例分析:选取具体的日语学习案例进行分析,探讨成功与失败的原因。
五、研究计划1. 第一阶段(1-2个月):完成文献综述,明确研究方向。
2. 第二阶段(3-4个月):设计并实施问卷调查和访谈,收集数据。
3. 第三阶段(5-6个月):对收集到的数据进行整理和分析。
4. 第四阶段(7-8个月):撰写研究报告,提出教学建议。
六、预期成果1. 形成一套系统的日语学习难点分析报告。
2. 提出创新的日语教学方法和学习策略。
3. 发表研究成果,为日语教育领域提供参考。
七、研究预算1. 资料购买费用。
2. 问卷调查和访谈的交通及通讯费用。
3. 数据分析软件购买或租赁费用。
4. 研究报告的撰写和发表费用。
八、结语本研究计划将为日语教育领域提供新的视角和方法,帮助学习者克服学习过程中的困难,提高日语学习效率。
希望通过本研究,能够为日语教育的发展做出贡献。
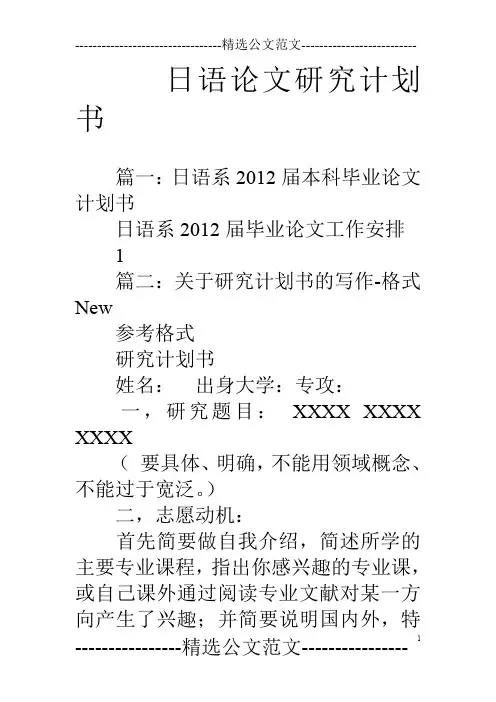
日语论文研究计划书篇一:日语系2012届本科毕业论文计划书日语系2012届毕业论文工作安排1篇二:关于研究计划书的写作-格式New参考格式研究计划书姓名:出身大学:专攻:一,研究题目:XXXX XXXX XXXX(要具体、明确,不能用领域概念、不能过于宽泛。
)二,志愿动机:首先简要做自我介绍,简述所学的主要专业课程,指出你感兴趣的专业课,或自己课外通过阅读专业文献对某一方向产生了兴趣;并简要说明国内外,特别是日本在此领域的研究水平,进而联系到留学日本大学院的理由;同时介绍目前的日语及英语水平。
三,研究经历:(如果有的话)1,过去一般研究的介绍,如毕业论文,毕业设计和发表论文的概要,课程设计、课程实习,及参加过的讲演比赛等等;2,就本课题做过哪些研究四,研究背景:(此部分非常重要,关系到研究计划书的逻辑主线,此部分关系到整个研究计划书的方向和质量)针对你感兴趣的研究方向确定关键词,并至少阅读6-8篇非常相近的本专业学术论文。
假如,要研究的题目确定为《日本跨国汽车公司直接投资对中国汽车产业重组与发展的影响--- 以丰田、本田、日产为中心》,则方法是:首先,选择关键词,在大学图书馆、公共图书馆的期刊数据库的收索引擎中进行收索,找到相关文献。
如,输入关键词,‘汽车产业重组’,‘日本汽车产业战略’,‘中国汽车产业战略’,‘日本跨国公司’、‘丰田汽车’等等,要不断变化相关联的关键词进行收索。
再快速阅读找到的文献摘要,筛选出符合你的研究方向的关键文献6-8篇。
对文献按照重要程度排序,集中阅读其中的3篇文献,在阅读引言时注意了解本课题目前的研究进展、得到哪些主要成果,作者是如何引出问题的,提出了哪些问题?进而通过阅读全文把握作者是用了什么方法、理论,如何解决了提出的问题,得到论文的何种结论。
3篇精细阅读后,你的脑子里对该课题方向有一个比较清晰的思考,再翻阅剩下的3-5篇相近文献,你可以概括出你要研究的课题,并能够指出还有哪些不足,或提出你认为本领域重要的问题,即你要研究的课题水到渠成了。
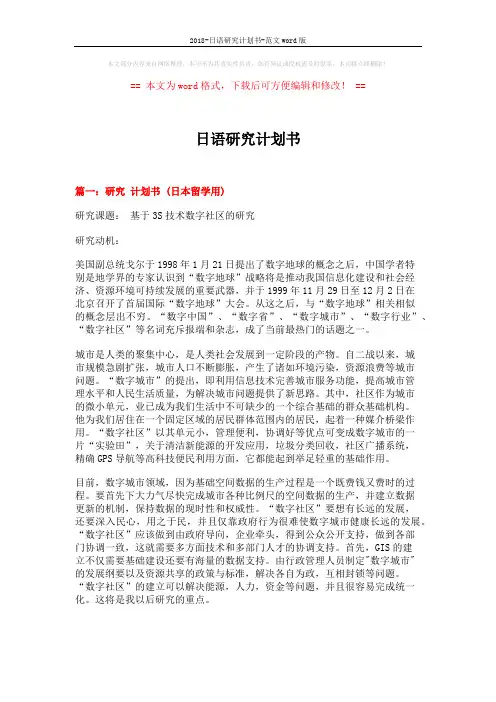
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==日语研究计划书篇一:研究计划书 (日本留学用)研究课题:基于3S技术数字社区的研究研究动机:美国副总统戈尔于1998年1月21日提出了数字地球的概念之后,中国学者特别是地学界的专家认识到“数字地球”战略将是推动我国信息化建设和社会经济、资源环境可持续发展的重要武器,并于1999年11月29日至12月2日在北京召开了首届国际“数字地球”大会。
从这之后,与“数字地球”相关相似的概念层出不穷。
“数字中国”、“数字省”、“数字城市”、“数字行业”、“数字社区”等名词充斥报端和杂志,成了当前最热门的话题之一。
城市是人类的聚集中心,是人类社会发展到一定阶段的产物。
自二战以来,城市规模急剧扩张,城市人口不断膨胀,产生了诸如环境污染,资源浪费等城市问题。
“数字城市”的提出,即利用信息技术完善城市服务功能,提高城市管理水平和人民生活质量,为解决城市问题提供了新思路。
其中,社区作为城市的微小单元,业已成为我们生活中不可缺少的一个综合基础的群众基础机构。
他为我们居住在一个固定区域的居民群体范围内的居民,起着一种媒介桥梁作用。
“数字社区”以其单元小,管理便利,协调好等优点可变成数字城市的一片“实验田”,关于清洁新能源的开发应用,垃圾分类回收,社区广播系统,精确GPS导航等高科技便民利用方面,它都能起到举足轻重的基础作用。
目前,数字城市领域,因为基础空间数据的生产过程是一个既费钱又费时的过程。
要首先下大力气尽快完成城市各种比例尺的空间数据的生产,并建立数据更新的机制,保持数据的现时性和权威性。
“数字社区”要想有长远的发展,还要深入民心,用之于民,并且仅靠政府行为很难使数字城市健康长远的发展。
“数字社区”应该做到由政府导向,企业牵头,得到公众公开支持,做到各部门协调一致,这就需要多方面技术和多部门人才的协调支持。
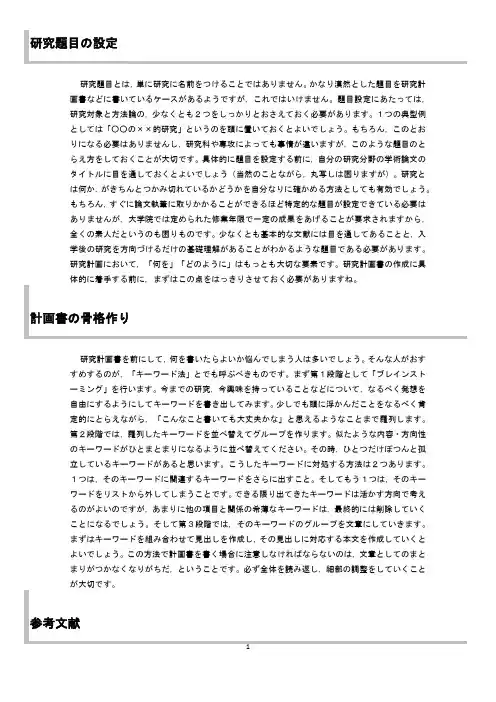
研究題目の設定研究題目とは,単に研究に名前をつけることではありません。
かなり漠然とした題目を研究計画書などに書いているケースがあるようですが,これではいけません。
題目設定にあたっては,研究対象と方法論の,少なくとも2つをしっかりとおさえておく必要があります。
1つの典型例としては「○○の××的研究」というのを頭に置いておくとよいでしょう。
もちろん,このとおりになる必要はありませんし,研究科や専攻によっても事情が違いますが,このような題目のとらえ方をしておくことが大切です。
具体的に題目を設定する前に,自分の研究分野の学術論文のタイトルに目を通しておくとよいでしょう(当然のことながら,丸写しは困りますが)。
研究とは何か,がきちんとつかみ切れているかどうかを自分なりに確かめる方法としても有効でしょう。
もちろん,すぐに論文執筆に取りかかることができるほど特定的な題目が設定できている必要はありませんが,大学院では定められた修業年限で一定の成果をあげることが要求されますから,全くの素人だというのも困りものです。
少なくとも基本的な文献には目を通してあることと,入学後の研究を方向づけるだけの基礎理解があることがわかるような題目である必要があります。
研究計画において,「何を」「どのように」はもっとも大切な要素です。
研究計画書の作成に具体的に着手する前に,まずはこの点をはっきりさせておく必要がありますね。
計画書の骨格作り研究計画書を前にして,何を書いたらよいか悩んでしまう人は多いでしょう。
そんな人がおすすめするのが,「キーワード法」とでも呼ぶべきものです。
まず第1段階として「ブレインストーミング」を行います。
今までの研究,今興味を持っていることなどについて,なるべく発想を自由にするようにしてキーワードを書き出してみます。
少しでも頭に浮かんだことをなるべく肯定的にとらえながら,「こんなこと書いても大丈夫かな」と思えるようなことまで羅列します。
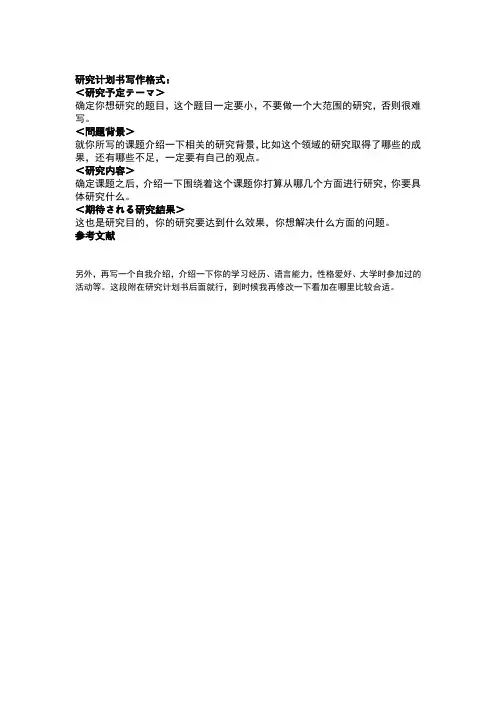
研究计划书写作格式:
<研究予定テーマ>
确定你想研究的题目,这个题目一定要小,不要做一个大范围的研究,否则很难写。
<問題背景>
就你所写的课题介绍一下相关的研究背景,比如这个领域的研究取得了哪些的成果,还有哪些不足,一定要有自己的观点。
<研究内容>
确定课题之后,介绍一下围绕着这个课题你打算从哪几个方面进行研究,你要具体研究什么。
<期待される研究結果>
这也是研究目的,你的研究要达到什么效果,你想解决什么方面的问题。
参考文献
另外,再写一个自我介绍,介绍一下你的学习经历、语言能力,性格爱好、大学时参加过的活动等。
这段附在研究计划书后面就行,到时候我再修改一下看加在哪里比较合适。
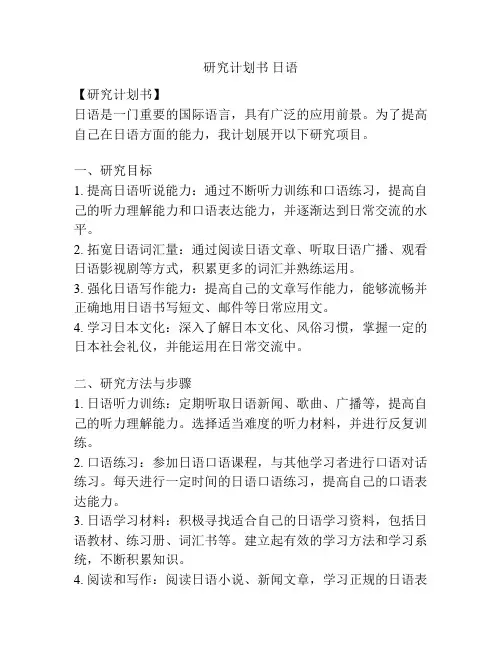
研究计划书日语【研究计划书】日语是一门重要的国际语言,具有广泛的应用前景。
为了提高自己在日语方面的能力,我计划展开以下研究项目。
一、研究目标1. 提高日语听说能力:通过不断听力训练和口语练习,提高自己的听力理解能力和口语表达能力,并逐渐达到日常交流的水平。
2. 拓宽日语词汇量:通过阅读日语文章、听取日语广播、观看日语影视剧等方式,积累更多的词汇并熟练运用。
3. 强化日语写作能力:提高自己的文章写作能力,能够流畅并正确地用日语书写短文、邮件等日常应用文。
4. 学习日本文化:深入了解日本文化、风俗习惯,掌握一定的日本社会礼仪,并能运用在日常交流中。
二、研究方法与步骤1. 日语听力训练:定期听取日语新闻、歌曲、广播等,提高自己的听力理解能力。
选择适当难度的听力材料,并进行反复训练。
2. 口语练习:参加日语口语课程,与其他学习者进行口语对话练习。
每天进行一定时间的日语口语练习,提高自己的口语表达能力。
3. 日语学习材料:积极寻找适合自己的日语学习资料,包括日语教材、练习册、词汇书等。
建立起有效的学习方法和学习系统,不断积累知识。
4. 阅读和写作:阅读日语小说、新闻文章,学习正规的日语表达方式。
通过阅读提高自己的日语阅读理解能力,并进行相关的写作练习。
5. 学习日本文化:阅读关于日本文化的书籍、收看日本综艺节目,深入了解日本文化与生活习惯。
并通过与日本人接触,了解他们的社会礼仪。
三、时间安排1. 日语听说训练:每天坚持听取日语材料,每周进行口语练习3次,每次1小时,持续一年时间。
2. 日语词汇积累:每天背诵新词10个,每周总结并巩固一次,持续一年时间。
3. 日语写作训练:每周写作练习一篇,每次1小时,持续一年时间。
4. 学习日本文化:每天阅读与日本文化相关的书籍、杂志等资料,每周观看一次日本综艺节目,持续一年时间。
四、预期成果1. 日语听力和口语能力得到明显提升,能够流利地进行日常对话和听取日语材料。
2. 词汇量得到扩充,掌握更多的日语表达方式和词汇,能够灵活运用。
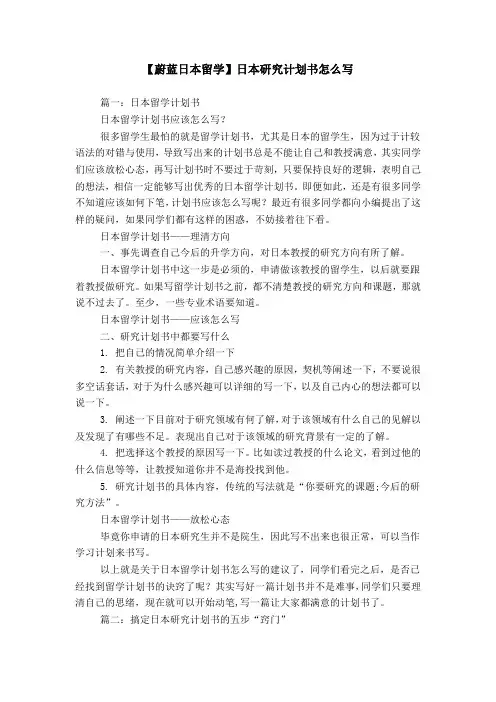
【蔚蓝日本留学】日本研究计划书怎么写篇一:日本留学计划书日本留学计划书应该怎么写?很多留学生最怕的就是留学计划书,尤其是日本的留学生,因为过于计较语法的对错与使用,导致写出来的计划书总是不能让自己和教授满意,其实同学们应该放松心态,再写计划书时不要过于苛刻,只要保持良好的逻辑,表明自己的想法,相信一定能够写出优秀的日本留学计划书。
即便如此,还是有很多同学不知道应该如何下笔,计划书应该怎么写呢?最近有很多同学都向小编提出了这样的疑问,如果同学们都有这样的困惑,不妨接着往下看。
日本留学计划书——理清方向一、事先调查自己今后的升学方向,对日本教授的研究方向有所了解。
日本留学计划书中这一步是必须的,申请做该教授的留学生,以后就要跟着教授做研究。
如果写留学计划书之前,都不清楚教授的研究方向和课题,那就说不过去了。
至少,一些专业术语要知道。
日本留学计划书——应该怎么写二、研究计划书中都要写什么1. 把自己的情况简单介绍一下2. 有关教授的研究内容,自己感兴趣的原因,契机等阐述一下,不要说很多空话套话,对于为什么感兴趣可以详细的写一下,以及自己内心的想法都可以说一下。
3. 阐述一下目前对于研究领域有何了解,对于该领域有什么自己的见解以及发现了有哪些不足。
表现出自己对于该领域的研究背景有一定的了解。
4. 把选择这个教授的原因写一下。
比如读过教授的什么论文,看到过他的什么信息等等,让教授知道你并不是海投找到他。
5. 研究计划书的具体内容,传统的写法就是“你要研究的课题;今后的研究方法”。
日本留学计划书——放松心态毕竟你申请的日本研究生并不是院生,因此写不出来也很正常,可以当作学习计划来书写。
以上就是关于日本留学计划书怎么写的建议了,同学们看完之后,是否已经找到留学计划书的诀窍了呢?其实写好一篇计划书并不是难事,同学们只要理清自己的思绪,现在就可以开始动笔,写一篇让大家都满意的计划书了。
篇二:搞定日本研究计划书的五步“窍门”搞定日本研究计划书的五步“窍门”1、把握目标研究室的研究内容把握目标研究室里的研究和计划着手的研究之间的契合度,并且确认这项研究是否已经完成以及是否有可能获得研究指导。
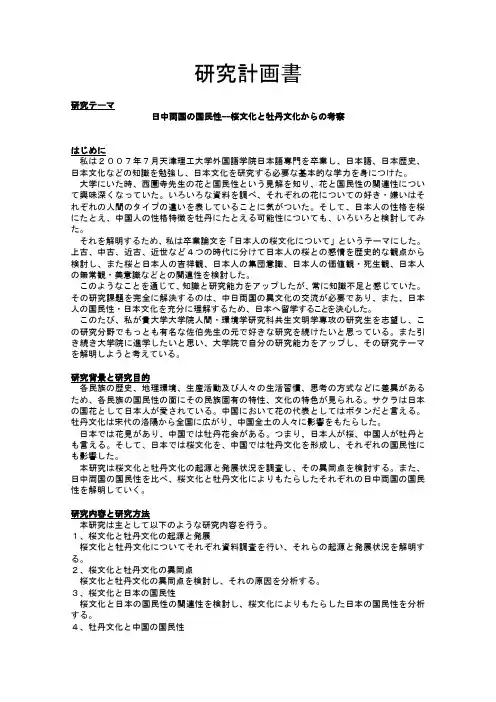
研究計画書研究テーマ日中両国の国民性--桜文化と牡丹文化からの考察はじめに私は2007年7月天津理工大学外国語学院日本語専門を卒業し、日本語、日本歴史、日本文化などの知識を勉強し、日本文化を研究する必要な基本的な学力を身につけた。
大学にいた時、西園寺先生の花と国民性という見解を知り、花と国民性の関連性について興味深くなっていた。
いろいろな資料を調べ、それぞれの花についての好き・嫌いはそれぞれの人間のタイプの違いを表していることに気がついた。
そして、日本人の性格を桜にたとえ、中国人の性格特徴を牡丹にたとえる可能性についても、いろいろと検討してみた。
それを解明するため、私は卒業論文を「日本人の桜文化について」というテーマにした。
上古、中古、近古、近世など4つの時代に分けて日本人の桜との感情を歴史的な観点から検討し、また桜と日本人の吉祥観、日本人の集団意識、日本人の価値観・死生観、日本人の無常観・美意識などとの関連性を検討した。
このようなことを通じて、知識と研究能力をアップしたが、常に知識不足と感じていた。
その研究課題を完全に解決するのは、中日両国の異文化の交流が必要であり、また、日本人の国民性・日本文化を充分に理解するため、日本へ留学することを決心した。
このたび、私が貴大学大学院人間・環境学研究科共生文明学専攻の研究生を志望し、この研究分野でもっとも有名な佐伯先生の元で好きな研究を続けたいと思っている。
また引き続き大学院に進学したいと思い、大学院で自分の研究能力をアップし、その研究テーマを解明しようと考えている。
研究背景と研究目的各民族の歴史、地理環境、生産活動及び人々の生活習慣、思考の方式などに差異があるため、各民族の国民性の面にその民族固有の特性、文化の特色が見られる。
サクラは日本の国花として日本人が愛されている。
中国において花の代表としてはボタンだと言える。
牡丹文化は宋代の洛陽から全国に広がり、中国全土の人々に影響をもたらした。
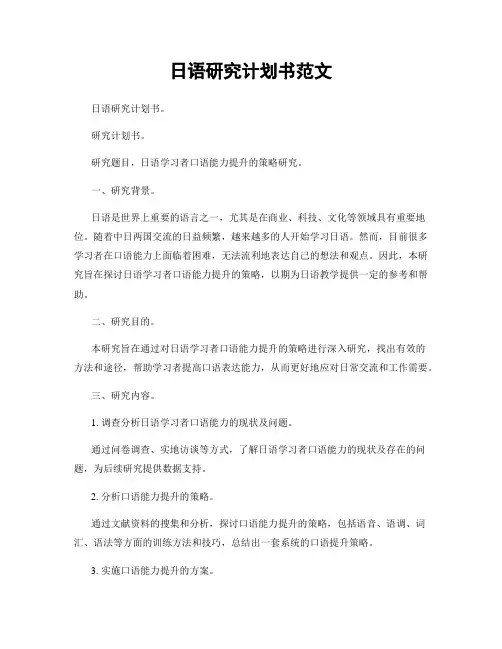
日语研究计划书范文日语研究计划书。
研究计划书。
研究题目,日语学习者口语能力提升的策略研究。
一、研究背景。
日语是世界上重要的语言之一,尤其是在商业、科技、文化等领域具有重要地位。
随着中日两国交流的日益频繁,越来越多的人开始学习日语。
然而,目前很多学习者在口语能力上面临着困难,无法流利地表达自己的想法和观点。
因此,本研究旨在探讨日语学习者口语能力提升的策略,以期为日语教学提供一定的参考和帮助。
二、研究目的。
本研究旨在通过对日语学习者口语能力提升的策略进行深入研究,找出有效的方法和途径,帮助学习者提高口语表达能力,从而更好地应对日常交流和工作需要。
三、研究内容。
1. 调查分析日语学习者口语能力的现状及问题。
通过问卷调查、实地访谈等方式,了解日语学习者口语能力的现状及存在的问题,为后续研究提供数据支持。
2. 分析口语能力提升的策略。
通过文献资料的搜集和分析,探讨口语能力提升的策略,包括语音、语调、词汇、语法等方面的训练方法和技巧,总结出一套系统的口语提升策略。
3. 实施口语能力提升的方案。
结合口语能力提升的策略,设计一套实施方案,包括口语训练课程、教学材料、教学方法等,进行实地教学实验,验证口语能力提升策略的有效性。
四、研究方法。
1.问卷调查法,通过设计问卷,对日语学习者进行调查,了解他们的口语能力现状及问题。
2.实地访谈法,通过对一定数量的日语学习者进行实地访谈,深入了解他们在口语学习过程中的困难和问题。
3.文献资料法,通过查阅相关文献资料,分析口语能力提升的策略,为研究提供理论支持。
4.实地教学实验法,设计口语能力提升的方案,进行实地教学实验,验证口语能力提升策略的有效性。
五、研究预期成果。
通过本研究,预计可以得出一套有效的口语能力提升策略,为日语学习者提供更好的口语学习方法和途径。
同时,也可以为日语教学提供一定的参考和借鉴,促进日语教学的改进和发展。
六、研究进度安排。
1. 第一阶段,进行问卷调查和实地访谈,了解口语能力现状及问题,收集相关数据。
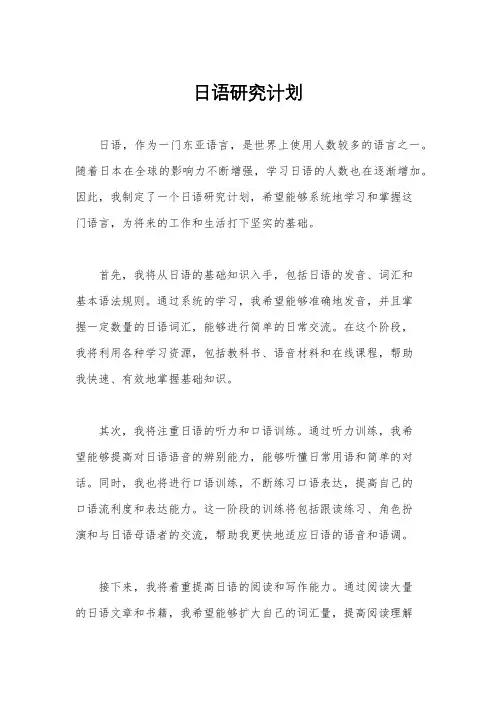
日语研究计划日语,作为一门东亚语言,是世界上使用人数较多的语言之一。
随着日本在全球的影响力不断增强,学习日语的人数也在逐渐增加。
因此,我制定了一个日语研究计划,希望能够系统地学习和掌握这门语言,为将来的工作和生活打下坚实的基础。
首先,我将从日语的基础知识入手,包括日语的发音、词汇和基本语法规则。
通过系统的学习,我希望能够准确地发音,并且掌握一定数量的日语词汇,能够进行简单的日常交流。
在这个阶段,我将利用各种学习资源,包括教科书、语音材料和在线课程,帮助我快速、有效地掌握基础知识。
其次,我将注重日语的听力和口语训练。
通过听力训练,我希望能够提高对日语语音的辨别能力,能够听懂日常用语和简单的对话。
同时,我也将进行口语训练,不断练习口语表达,提高自己的口语流利度和表达能力。
这一阶段的训练将包括跟读练习、角色扮演和与日语母语者的交流,帮助我更快地适应日语的语音和语调。
接下来,我将着重提高日语的阅读和写作能力。
通过阅读大量的日语文章和书籍,我希望能够扩大自己的词汇量,提高阅读理解能力。
同时,我也将进行写作训练,不断练习日语的书面表达,包括日记、短文和作文等。
在这一阶段,我将注重积累日语表达习惯和惯用语,提高自己的写作水平。
最后,我将进行综合能力的提高和实战训练。
通过参加日语考试、参与日语角色扮演和实际交流,我希望能够全面提高自己的日语能力。
在实践中不断总结经验,发现问题并加以解决,最终达到能够独立运用日语进行各种交流和沟通的水平。
总的来说,这个日语研究计划是一个系统、全面的学习过程,涵盖了日语的听、说、读、写各个方面。
通过坚持不懈地学习和训练,我相信自己一定能够掌握日语这门语言,为将来的工作和生活打下坚实的基础。
日语研究计划书研究计划书(700字)一、研究背景和意义日语是一种重要的国际语言,不仅在日本国内广泛使用,而且在世界范围内有广泛的影响力。
随着中日关系的进一步发展,日语的需求也不断增加。
然而,现阶段我们国内对于日语教学的研究还相对较少。
因此,本研究的目的是通过对日语教学方法的研究,提高我国日语教学水平,满足不断增长的日语学习需求。
二、研究的目标和内容本研究的主要目标是探索适合中国学生的日语教学方法,并根据实际需求进行相应调整和改进。
具体的研究内容包括以下几个方面:1. 教学方法研究:通过对比研究不同的日语教学方法,分析其优缺点,并寻找适合中国学生的教学方法。
2. 课程设计研究:针对不同层次的学生,根据他们的学习需求和特点,进行日语课程设计的研究,以提高学生的学习效果和兴趣。
3. 教材开发研究:根据实际需求,开发适合中国学生的日语教材,以便更好地满足他们的学习需求。
三、研究方法本研究主要采用实证研究方法,通过问卷调查、实验比较和教学实践等方式进行数据收集和分析。
具体的研究步骤包括:1. 调研:通过文献阅读和专家访谈等方式,调研已有的日语教学方法和研究成果。
2. 问卷调查:设计针对学生和教师的问卷调查,收集他们对于现有教学方法的评价和需求。
3. 实验比较:设计实验,比较不同教学方法在学生学习效果和兴趣方面的差异。
4. 教学实践:在实际教学中尝试使用不同的教学方法,并通过观察和记录分析教学效果。
四、预期成果及应用价值通过本研究,预期可以得出适合中国学生的日语教学方法,并根据实际需求进行相应调整和改进。
同时,还将开发出适合中国学生的日语教材,以提高他们的学习效果和兴趣。
这将对我国日语教育的发展起到积极的推动作用。
本研究的成果可以应用于日语教学机构和学校的日语教学中,帮助教师改进教学方法,提高教学效果。
同时,对于学生来说,本研究将提供更好的学习资源和方法,帮助他们更好地学习日语。
五、研究计划和进度安排本研究计划将按照以下进度进行实施:1. 第一年:调研和文献阅读,明确研究方向和目标。
日语研究计划书范文一、研究背景。
日语作为一门重要的东亚语言,不仅在日本国内有着广泛的使用,而且在世界范围内也有着相当大的影响力。
随着我国对外交流的不断深入,学习日语的人数也在逐年增加。
因此,对日语的研究和教学显得尤为重要。
二、研究意义。
1. 促进中日文化交流。
通过深入研究日语,可以更好地理解日本文化,促进中日两国之间的文化交流和友好关系。
2. 推动对日本经济的了解。
日本作为世界上重要的经济体之一,其经济发展对我国也有着重要的影响。
通过研究日语,可以更好地了解日本的经济状况和发展趋势,为我国的对外经济合作提供更多的可能性。
3. 丰富我国的语言资源。
学习日语不仅可以增加我国人民的语言技能,还可以为我国的语言资源增添新的元素,丰富我国的语言文化。
三、研究内容。
1. 日语语音、语法、词汇的研究。
通过对日语语音、语法和词汇的系统研究,可以更好地掌握日语的基本规律和特点,为日语教学提供更科学的理论支持。
2. 日语教学方法的探索。
针对不同学习者的特点和需求,探索更加有效的日语教学方法,提高日语教学的实效性和趣味性。
3. 日语与日本文化的关系。
通过对日语和日本文化的关系进行深入的研究,可以更好地理解日语的本质和特点,为日语教学提供更加全面的支持。
四、研究方法。
1. 文献资料法。
通过查阅大量的相关文献资料,了解前人的研究成果和观点,为本次研究提供理论支持。
2. 调查法。
通过实地调查和问卷调查的方式,了解学习者对日语学习的需求和困难,为日语教学方法的探索提供实际依据。
3. 实地考察法。
通过赴日本进行实地考察,深入了解日本的语言环境和文化氛围,为日语研究提供更为直观的材料。
五、预期成果。
1. 发表学术论文。
通过对日语的深入研究,预计可以在相关学术期刊上发表一系列学术论文,为日语研究领域贡献新的观点和成果。
2. 教学实践。
将研究成果运用到日语教学实践中,提高日语教学的效果和质量,培养更多的优秀日语人才。
3. 学术交流。
日语论文研究计划书篇一:日本研究计划书集合日本大学院研究生申请计划书①申请理由②研究欲望③标新立异的课题④具体的研究手段及方法⑤研究目的以及将来的目标⑥完成这篇研究计划书所参考的文献资料下面用例文讲解:本研究科を志望した動機、研究計画、卒業後のキャリアゴールについて書きなさい。
(1600文字程度) ①(志望動機)私は、介護関係の会社で5年間、営業に従事してきた。
業務で担当したほとんどの顧客は、在宅介護を基礎にしていたが、営業として医療や介護の充実を優先した結果、施設介護へ移行するようになった。
しかし、職務を通じて見えたのは、そのような施設介護サービス業が必ずしも顧客満足につながっておらず、解約されるケースが多く見られ、結果として企業と顧客両者の損失につながるジレンマに陥っているということであった。
このような状況を見るにつけ、顧客が真に望むような在宅介護サービスを提供できていないことを強く感じた。
②そこで、現職より一歩外に出て、本研究科で医療、介護、ビジネスの現状を客観的に見つめなおす必要があると考え、大学院への進学を決定した。
また今後、現事業をさらに大きく展開して、顧客ニーズを充実させるには、先進的なマーケティング手法を取り入れた経営を行うべきである。
これに加えて経営戦略、組織戦略、消費行動を学びマネジメントに活かしたいと考えている。
本研究科では、経営だけの視点や医療介護だけの視点でもない療法の視点を持ったヘルスケアマネジメントの勉強が可能であることも志望動機の一因である。
③(研究計画)本研究では、以上の問題意識を踏まえて、顧客が真に望む在宅介護サービスの実現性について検証したい。
医療介護ビジネス戦略を同時に実現するためには、顧客のニーズを汲み取り、そのニーズを実現できるようなイノベーションを生み出すネットワークの構築が必要であると考えている。
介護産業は民間に開放されてからまだ日が浅く、ほかの産業と比較しても、しっかりとした経営が行われているとは言い難い。
研究计划书日语工作目标1.提升编辑团队的专业水平编辑团队需要定期接受新的编辑技术和理念的培训,每季度至少组织两次专业培训活动,每次活动后需提交学习报告。
2.优化编辑流程当前的编辑流程存在一定效率问题,计划通过引入新的编辑软件和调整工作流程,提升编辑效率20%。
3.增强内容质量对于每一篇发布的文章,都需要进行多轮的审核和校对,确保内容的准确性和可读性。
工作任务1.编辑技术培训需要针对当前最新的编辑技术和理念,每季度组织至少两次的培训活动,每次活动时间为一天。
2.编辑流程优化需要针对当前的编辑流程进行深入的调研,找出存在的问题,然后引入新的编辑软件,调整工作流程。
3.内容质量控制对于每一篇发布的文章,都需要进行多轮的审核和校对,确保内容的准确性和可读性。
文章发布后,还需要对读者反馈进行收集,根据反馈对编辑工作进行改进。
任务措施1.技术培训实施为了提升编辑团队的专业水平,将组织定期的技术培训。
首先,通过市场调研确定当前编辑领域的最新技术和理念。
然后,设计培训课程,包括线上和线下相结合的方式,确保每位编辑都能参与并掌握新技术。
培训结束后,要求每位编辑提交学习报告,总结学习心得和在实际工作中的应用情况。
此外,将建立一个编辑技术交流小组,鼓励编辑们在工作中相互学习和分享经验。
2.编辑流程优化方案针对当前编辑流程中的效率问题,计划引入先进的编辑软件,并结合实际工作流程进行调整。
首先,将对现有编辑流程进行全面分析,识别瓶颈和改进点。
接下来,将研究并选择适合的编辑软件,通过与软件供应商的沟通合作,确保软件能够满足我们的需求。
在软件引入后,将对编辑团队进行培训,确保每位编辑都能熟练使用新软件。
最后,将新的编辑流程与现有工作流程进行对比分析,评估优化效果,并根据实际运行情况进行持续改进。
3.内容质量控制措施为了增强内容质量,将实施严格的内容审核和校对流程。
首先,将制定内容质量标准,包括准确性、可读性、逻辑性等方面。
然后,建立多轮审核制度,确保每篇文章在发布前都经过至少三轮的审核和校对。
研究計画書はじめに私は中国の大学で国家添乗員資格を取得し、卒業後、旅行会社に三年間勤務してきた。
具体的には旅行のプランを組む、フロントの対応、添乗員などの実務経験を積んでた。
上記の職務を通して、特に日本から来た観光客を案内する時、自分の日本語能力が不足と実感して、日本へ留学することを決心した。
以前から語学に格别の関心を持ち、日本で留学するうちに、本格的に日本語翻訳・通訳を勉強していきたいという願望が強まり、優秀な翻訳者となるのが今の私の夢である。
また、日本で四年間日本語の勉強と前の仕事の経験で、観光地の案内文の翻訳に関心を持ち、中国の観光地の案内文では日本人対して、真意が伝わらないという問題を認識している。
この問題に対して大学院で研究したいと考えている。
志望動機私が貴校の国際言語コミュニケーション専攻を志望するのは専門領域で活躍されている教授が集まっているからである、日中翻訳・通訳領域で第一級の活躍をしている塚本教授のご指導いただきたいと思っている。
また、先輩や専門学校の先生からも、日本初の大学院における「日中通訳翻・訳研究コース」として、強く勧めてくれた学校でもある。
これまでの学習内容現在日本外国語専門学校で日中通訳・翻訳を専攻し、来年3月に卒業する予定である。
学校では日本語だけでなく、幅広く勉強をしてきた。
地理、歴史、一般常識などの授業で日本の社会や文化をより深く理解できるようになった。
ITスキルズまたビジネス通訳の授業を通じて、ビジネス文書やメールが書けるようになり、PC入力で書類の作成もできる。
授業に積極的に取り込んできたおかげで、日本語N1、漢字検定準2級、ビジネス日本語検定J1、ワープロ3級などの資格を取り、翻訳・通訳をするための基礎力を修めた。
研究内容観光を通じて、民間交流が進めば、両国の緊張関係の緩和にも貢献できるので、やりがいがある。
中国の観光地に関する案内文は日本人が分かりづらい直訳が多く、なかなか歴史背景や文化的背景が正しく伝わりにくい。
研究计划书(推荐阅读)第一篇:研究计划书はじめに私は現在**大学外国語学院日本語学科の四年生で、2001年10月から日本国際教育協会(AIEJ)の奨学生として採用され、交換留学生として**大学へ留学にきている。
日本語は専攻として勉強してきて、優秀な成績を得たが、それはあくまでも語学の勉強であるしかない。
以前から経営学に格別の関心を持ち、それに関する本なども読んできたが、自分の将来の道の行方を考えた上で、やりがいのある学問である経営学を勉強しようと決意した。
準備として、大学二年の時から、副専攻として電子商務の勉強を始めた。
勉強しているうちに、経営学に対する論理的な理解を深め、本格的に勉強していくという願望を強めた。
情報社会と呼ばれる今の社会では、企業の経営も変貌しつつある。
私は情報通信を利用した企業の経営と、企業の国際経営を研究したい分野と考えている。
志望動機私が貴大学経済学部の研究生を志望するのはそれぞれの専門領域で第一級の活躍をしている教授が集まってきているからである。
また私は大学院に進学したいと思っているが、貴学部は大学院へ重点化したので、大学院での研究や、教育の道がもっと開かれていると考えられる。
そして、総合大学である東北大学は教育、研究の資源が豊かであり、所在地である仙台は学生を大切にする街であり、「学都」と呼ばれていれ、学習する環境がとてもいいと感じられる。
それに、先生の研究するテーマに興味があるので、ぜひ先生の元で勉強したいと思っている。
これまでの学習内容私は**大学では二年生から副専攻として電子商務の勉強をしており、履修した科目は国際貿易、ネットワーク経済学、電子商務概論、市場経営学、ネットワーク技術、ネットワーク通信などである。
それはコマースと情報通信技術の両分野から成り立たれている。
そして、選択授業として取った経済に関する科目は国際経済論、政治経済学、電子商務などの科目である。
一、研究テーマの説明大学四年間に、電子商取引の基礎知識を勉強している内に、インターネット・マーケティングに対して深い興味を持った。
しかし、大学の課程の中では電子商取引の一分野だけで、浅い知識しか勉強しなかったため、大学院ではインターネット・マーケティングについて、専門的な研究を行いたいと思っている。
同時に、中国では、中小企業は企業の総計の97%を占めるが、発展の現状は楽観的ではない。
融資してもらうのが困難なだけではなく、人材が欠如し、法律がまだ完全ではないなどの方面から考えると、中小企業の現状は厳しい状態である。
しかし、中国の電子商取引の急激な発展につれて、より多くの中小企業は電子商取引のメリットを認識し、独立でウェブサイトを作ったり、第三者のプラットフォームを基礎としてインターネット・マーケティングを行ったりしはじめた。
特に2003年に創設された淘宝網(タオバオ)という電子商取引のサイトが、中小企業のためにマーケティングを行う機会を提供し、大手企業との距離を近づけている。
大学の卒業論文では、中国中小企業の電子商取引の応用の現状について研究をしてきた。
中国の電子商取引の急速な発展につれて、より多くの日本中小企業が中国に進出をはじめ、「中国企業の動向調査」*1のデータによると、中国へ進出している企業は1万企業を超えている。
日本の中小企業と中国の中小企業は大きく違うところがあると思う。
まず、政策、資金の方面から見ると、日本政府は中小企業に対して、十分に支援していると思われる。
1963年の「中小企業基本法」、さらに「中小企業近代化促進法」の公布をはじめ、2011年の金融庁が提出した中小企業アジア進出に支援するなどの一連の政策*2によって、日本政府は中小企業にずっと金融上で支援している。
しかし、中国中小企業は不公平な現状に直面している。
銀行は資金の薄弱な中小企業にローンを貸したがらない。
政府は大手企業の発展だけを重視しているので、困った立場になっている中小企業は発展するのが困難であると思う。
次に、発展のモデルから言うと、日本中小企業は必ずしも規模の拡大を求めるのではなく、大手企業の産業チェーンの一部分を目指し、専門のレベルで細分化されていて、その小さな業界のトップになるという目標を立てている。
一方、中国の中小企業の発展モデルと管理の理念の上では、市場占有率と企業の生産額を非常に重視しており、企業を大きくするのが最大目標だと思っているが、日本の中小企業のように規模は小さくても高い専門技術を磨く会社は少ない。
私はその点が中国中小企業と日本中小企業の最大の違いだと思っている。
したがって私は、政策の上でも経営の理念でも、中国は日本の中小企業に学ぶべきだと思うので、これについて日本で研究したい。
一方、日本国内のニーズと人口の減少、円高の現状の下で、ますます日本中小企業は中国市場に目を向けている。
しかし、国内でどのように経営が成功していようと、中国に進出するためは、改めてマーケティング戦略を制定しなくてはいけない。
特に中国の電子商取引の環境の下、どのようにインターネット・マーケティングを行うのかが大学院で重点的に研究したい方向である。
私は、日本中小企業の経営の方法を学ぶだけではなく、年々増加している中国へ進出する日本中小企業にマーケティング戦略を提案したいと思う。
二、テーマについて調べたこと山下勇一教授の著書「Webマーケティング」*3では、「中国向けにWebサイトで商品を販売する方法」は、主に二つ方法があり、「独自のドメイン名を取得してWebショップを立ち上げる方法」と「中国電子商取引企業の電子モールの会員として出店する方法」という内容が書かれている。
「独自のドメイン名を取得してWebショップを立ち上げる方法」について、私は以下のメリットがあると思う。
企業の文化と商品の理念を効率的に宣伝して展示することができ、さらに、消費者の訪問のデータを記録できるし、それから消費者の特徴、訪問アプローチの発信源を統計、分析することができる。
そして、消費者と1対1でのコミュニケーションが実現するので、消費者のニーズ把握、商品の改善、戦略の変更をすることができ、マーケティングがもっと効率的に行われる。
デメリットといえば、まず、政策の方面から見ると、「Webマーケティング」に書かれているような*4法律の問題がある。
つまり、外国の企業にとって中国の電子商取引の法律に熟知する必要があり、非常に繁雑な手続きを必要とするのである。
さらに電子商取引のウェブサイトを設立するのは、アウトソーシングの方法を取ることができるが、設立後の管理と更新をする費用と専門の人材が相変わらず必要で、もっと重要なのは、消費者に自分の会社のウェブサイトを知ってもらうためには、それぞれ有名なウェブサイトで宣伝活動を行わなければならないということである。
その費用を軽視してはいけない。
「中国ウェブサイトのランキング」 というサイトでは、訪問者が一日平均14万人を超える有名なポータルサイト「新浪SINA」を例とすると、ウェブサイトの広告に費用は、小さな文字21字程で、一日で12万円。
それがトップページなら20万円ぐらいする。
したがって、目立つ広告を入れようと考えれば、相当に費用がかかる。
これは中小企業のウェブサイトを設立する前に必ず考慮しなければならない一つの要素である。
その他、物流面、取引の面、及びネットワークセキュリティの方面全部についてしっかりとした計画や対策をしてようやく、電子商取引のウェブサイトでの通販が実現できる。
一方、「中国電子商取引企業の電子モールの会員として出店する方法」を利用すると、次のメリットがある。
まず一つは、企業が担う電子取引のプロセスと資金の負担を減らせることだ。
第三者のプラットフォームを通して登録し、ウェブサイトに商品情報等をアップロードし、マーケティングを行うことができるからだ。
さらに物流面とウェブサイトの維持、取引の信用体系が第三者のプラットフォーム上で実現されているので、企業はいっそう集中して商品の開発や改善に力を入れることができる。
次に、迅速に第三者のプラットフォームが持つ消費者を獲得することができることだ。
最後に、アリババグループは海外企業と中国企業との交流と協力を推進して、外国企業のために「タオバオ」、「天猫」(テンモウ)で開店できる機会を提供している。
「天猫」を例とすると、企業が中国での法人資格を持っていれば、開店することができる。
アリババグループはこの法人資格の取得の問題を解決するために、交流会などの方法を利用して、外国企業が現地企業との協力を通じて、「天猫」で商品を販売することを実現させた。
同時に、欠点も持っている。
企業の文化や商品の展示が個性的にできず、「タオバオ」のフレームに従わなくてはいけない。
さらに、競合他社の中から、消費者の注意を引くのが容易ではない。
検索のトップページで消費者に見てもらうには合理的な価格水準と信用のレベルの高さがなければならない。
注意すべきは、2010年6月にヤフーと中国アリババグループのタオバオが「淘日本」を開設したことだ。
「淘日本」というのは、日本の「Yahoo!ショッピング」の商品を中国「タオバオ」から購入できるサイトだ。
しかし、現状は楽観的ではない。
言語面では、日本語から中国語へ人が翻訳するのではなく、翻訳ツールを利用するので商品についての説明が中国の消費者に誤解される可能性がある。
そして、消費者と企業の間の直接交流も言葉が通じない場合がある。
さらに高い運賃も消費者に購買意欲を失わせる。
上述の2種類の方法について、私はまず「中国電子商取引企業の電子モールの会員として出店する方法」を利用して行い、企業が資金の実力と一定の知名度を持った後、「独自のドメイン名を取得してWebショップを立ち上げる方法」を利用することを提案する。
資金、人材、法律、物流などの問題の方面から、中小企業の現状を考えると、「電子モールの会員として出店する方法」が比較的優位になれると思うからだ。
そして、「淘日本」の言語、運賃、サービス等の問題が改善すれば、日本中小企業が中国に進出するのに大きな助けになると見られる。
現状では、第三者のプラットフォームを利用する方法が優位を占めているが、将来を考えると、タオバオの国際化が進んでおり、急速に発展する国際貿易に伴い、中国の法律の政策も絶えず改善されるので、「淘日本」のような低コストの方法は非常に潜在力があると思う。
中国の政策が原因で、日本企業は国内のTwitter、Facebookなどを中国でうまく使うことができず、中国の有名なウェブサイトを利用しなければならない。
しかし、それを利用して、企業の文化と商品の宣伝を効果的に行うこともできる。
新浪微博(ウェイボー)の例をあげると、ウェイボーは中国のインターネットユーザーのうち、使用率は40.2%まで達し、約1.94億のユーザーが使用している。
ユーザーの心を捉えることができるなら企業にとって、大きいチャンスになる。
したがって、企業が適切なインターネット・マーケティング戦略を制定することができれば、企業の知名度を高めることができるだけではなくて、潜在的な消費者を「発見」することがもっと多くなるので企業のマーケティングの新戦力となるだろう。
三、入学後の研究計画研究を行うための必要な基礎知識を得るために、まず以下のような学習を行いたい。
1、日本中小企業の経営の現状についていろいろな本を読む。
2、中国インターネット・マーケティングに関する、より新しい情報の収集。
3、語学能力の向上。
論文の作成や専門的な文献を読むために日本語の専門的な用語を身につけたい。
英語の能力も大切だと考えるので、しっかり勉強する予定である。
論文執筆準備のプロセスとしては、まず日本の中小企業が中国で行っているマーケティング方法と効果を調べるために、アンケートや企業訪問等を行う。
その調査結果を分析して現状をまとめる。
その時点や将来の中国の電子商取引の状況を考えて、適切なマーケティングを提案したい。
参考文献*1帝国データバンク東京支社情報部「中国企業の動向調査」2010年10月http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p101005.pdf*2政府インターネットテレビ「政務三役に聞く中堅・中小企業のアジア進出支援策」2011年12月-online.go.jp/prg/prg4460.html*3山下勇一「Webマーケティング」東方通信社2010年3月*4*1の書物のP125 8行目~14行目*5中国网络協会「 访问者趋势」2012年1月/reach/Info.do?url=01王易见「中小企业进军电子商务市场外包或为主要依托」2011年12月/u/feitianhanxue/469889.shtml02CNNIC「第28次中国互联网络发展状况调查统计报告」2011年7月/research/bgxz/tjbg/201107/t20110719_22120.html03三柳英樹「ヤフーとタオバオが提携、中国商品が買える『Yahoo!チャイナモール』開設」2010年6月http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100602_371621.html04羊城晚报「东京新闻:日本商家瞄准中国淘宝」2011年12月/GB/157278/1660513.html05蒋丰「日企在华大“玩”微博的营销启示」2012年1月/roll/2012-01/2365236.html06高橋学「ウェイボー(微博)基軸の中国EC総合WEBマーケティング实例」2012年1月/2012/01/20664/。