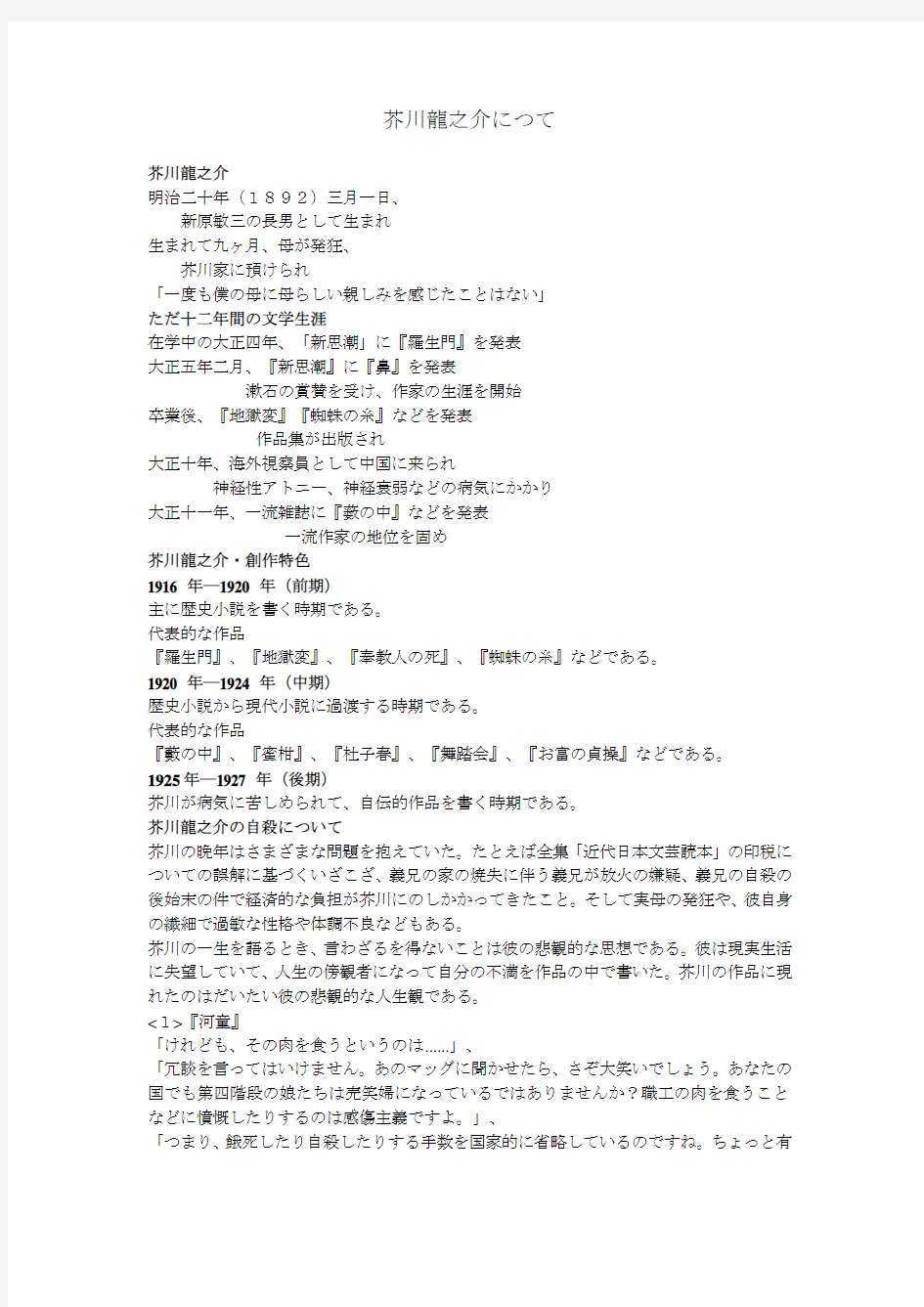
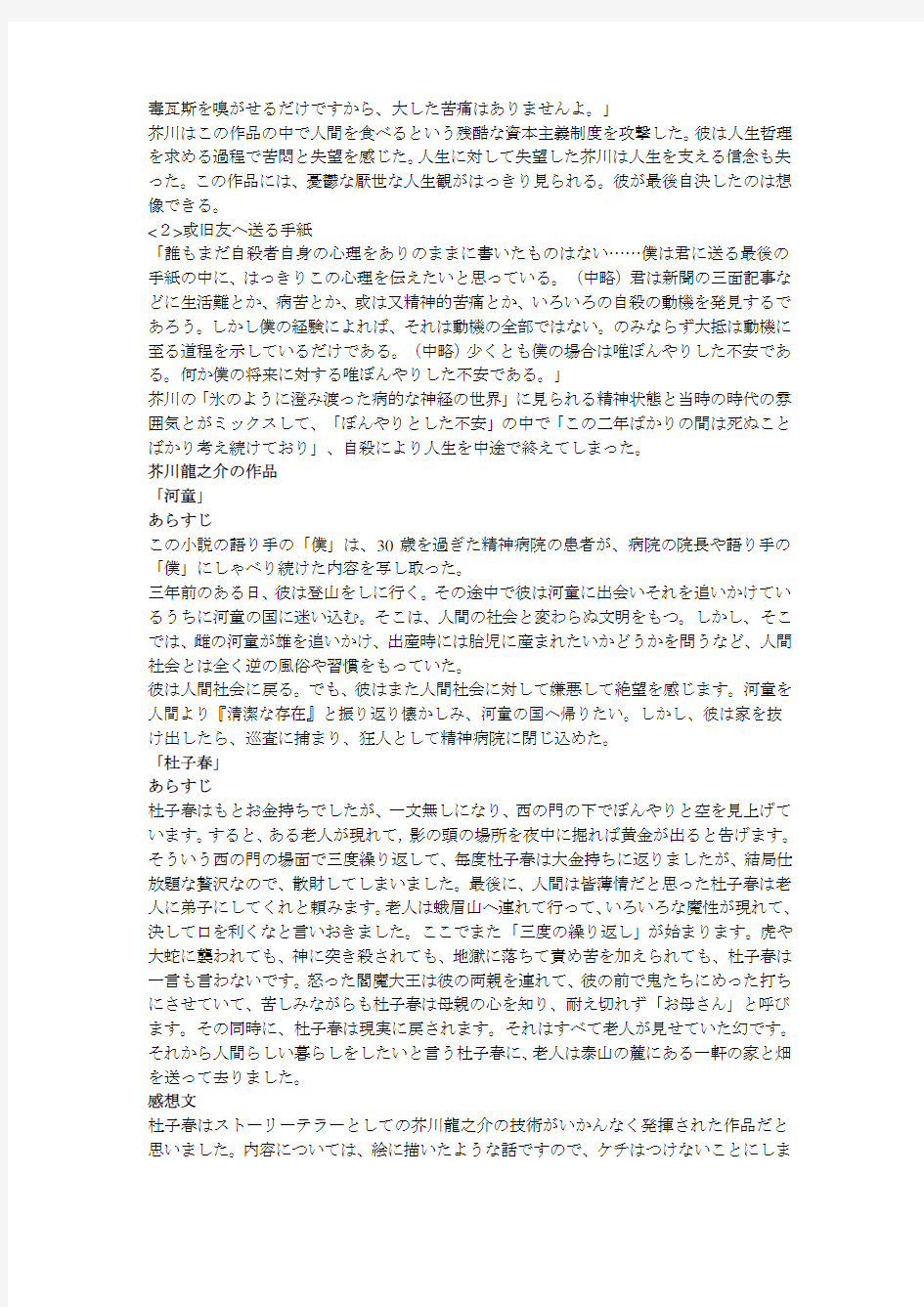
芥川龍之介につて
芥川龍之介
明治二十年(1892)三月一日、
新原敏三の長男として生まれ
生まれて九ヶ月、母が発狂、
芥川家に預けられ
「一度も僕の母に母らしい親しみを感じたことはない」
ただ十二年間の文学生涯
在学中の大正四年、「新思潮」に『羅生門』を発表
大正五年二月、『新思潮』に『鼻』を発表
漱石の賞賛を受け、作家の生涯を開始
卒業後、『地獄変』『蜘蛛の糸』などを発表
作品集が出版され
大正十年、海外視察員として中国に来られ
神経性アトニー、神経衰弱などの病気にかかり
大正十一年、一流雑誌に『薮の中』などを発表
一流作家の地位を固め
芥川龍之介?創作特色
1916 年―1920 年(前期)
主に歴史小説を書く時期である。
代表的な作品
『羅生門』、『地獄変』、『奉教人の死』、『蜘蛛の糸』などである。
1920 年―1924 年(中期)
歴史小説から現代小説に過渡する時期である。
代表的な作品
『藪の中』、『蜜柑』、『杜子春』、『舞踏会』、『お富の貞操』などである。
1925年―1927 年(後期)
芥川が病気に苦しめられて、自伝的作品を書く時期である。
芥川龍之介の自殺について
芥川の晩年はさまざまな問題を抱えていた。たとえば全集「近代日本文芸読本」の印税についての誤解に基づくいざこざ、義兄の家の焼失に伴う義兄が放火の嫌疑、義兄の自殺の後始末の件で経済的な負担が芥川にのしかかってきたこと。そして実母の発狂や、彼自身の繊細で過敏な性格や体調不良などもある。
芥川の一生を語るとき、言わざるを得ないことは彼の悲観的な思想である。彼は現実生活に失望していて、人生の傍観者になって自分の不満を作品の中で書いた。芥川の作品に現れたのはだいたい彼の悲観的な人生観である。
<1>『河童』
「けれども、その肉を食うというのは......」、
「冗談を言ってはいけません。あのマッグに聞かせたら、さぞ大笑いでしょう。あなたの国でも第四階段の娘たちは売笑婦になっているではありませんか?職工の肉を食うことなどに憤慨したりするのは感傷主義ですよ。」、
「つまり、餓死したり自殺したりする手数を国家的に省略しているのですね。ちょっと有
毒瓦斯を嗅がせるだけですから、大した苦痛はありませんよ。」
芥川はこの作品の中で人間を食べるという残酷な資本主義制度を攻撃した。彼は人生哲理を求める過程で苦悶と失望を感じた。人生に対して失望した芥川は人生を支える信念も失った。この作品には、憂鬱な厭世な人生観がはっきり見られる。彼が最後自決したのは想像できる。
<2>或旧友へ送る手紙
「誰もまだ自殺者自身の心理をありのままに書いたものはない……僕は君に送る最後の手紙の中に、はっきりこの心理を伝えたいと思っている。(中略)君は新聞の三面記事などに生活難とか、病苦とか、或は又精神的苦痛とか、いろいろの自殺の動機を発見するであろう。しかし僕の経験によれば、それは動機の全部ではない。のみならず大抵は動機に至る道程を示しているだけである。(中略)少くとも僕の場合は唯ぼんやりした不安である。何か僕の将来に対する唯ぼんやりした不安である。」
芥川の「氷のように澄み渡った病的な神経の世界」に見られる精神状態と当時の時代の雰囲気とがミックスして、「ぼんやりとした不安」の中で「この二年ばかりの間は死ぬことばかり考え続けており」、自殺により人生を中途で終えてしまった。
芥川龍之介の作品
「河童」
あらすじ
この小説の語り手の「僕」は、30歳を過ぎた精神病院の患者が、病院の院長や語り手の「僕」にしゃべり続けた内容を写し取った。
三年前のある日、彼は登山をしに行く。その途中で彼は河童に出会いそれを追いかけているうちに河童の国に迷い込む。そこは、人間の社会と変わらぬ文明をもつ。しかし、そこでは、雌の河童が雄を追いかけ、出産時には胎児に産まれたいかどうかを問うなど、人間社会とは全く逆の風俗や習慣をもっていた。
彼は人間社会に戻る。でも、彼はまた人間社会に対して嫌悪して絶望を感じます。河童を人間より『清潔な存在』と振り返り懐かしみ、河童の国へ帰りたい。しかし、彼は家を抜け出したら、巡査に捕まり、狂人として精神病院に閉じ込めた。
「杜子春」
あらすじ
杜子春はもとお金持ちでしたが、一文無しになり、西の門の下でぼんやりと空を見上げています。すると、ある老人が現れて,影の頭の場所を夜中に掘れば黄金が出ると告げます。そういう西の門の場面で三度繰り返して、毎度杜子春は大金持ちに返りましたが、結局仕放題な贅沢なので、散財してしまいました。最後に、人間は皆薄情だと思った杜子春は老人に弟子にしてくれと頼みます。老人は蛾眉山へ連れて行って、いろいろな魔性が現れて、決して口を利くなと言いおきました。ここでまた「三度の繰り返し」が始まります。虎や大蛇に襲われても、神に突き殺されても、地獄に落ちて責め苦を加えられても、杜子春は一言も言わないです。怒った閻魔大王は彼の両親を連れて、彼の前で鬼たちにめった打ちにさせていて、苦しみながらも杜子春は母親の心を知り、耐え切れず「お母さん」と呼びます。その同時に、杜子春は現実に戻されます。それはすべて老人が見せていた幻です。それから人間らしい暮らしをしたいと言う杜子春に、老人は泰山の麓にある一軒の家と畑を送って去りました。
感想文
杜子春はストーリーテラーとしての芥川龍之介の技術がいかんなく発揮された作品だと思いました。内容については、絵に描いたような話ですので、ケチはつけないことにしま
す。率直な、といいますか、勝手な感想としましては、地の文で、「大金持ちになれば御世辞を言い、貧乏人になれば口も利かない人間の人たちに比べると、何という有難い志でしょう」などと説明しちゃっていて、母の愛を強調し、質素などの美徳を称えるような話にしていますので、芥川龍之介はどこか、無理をして書いたような様子が伝わってくるという感じました。
「羅生門」
-下人の生き方「生」への考え-
羅生門は芥川龍之介によって書かれた歴史小説であり、大正4年、「新思潮」に柳川隆之介の名で発表された。彼が当時23歳の時である。彼は当時つらい失恋(祖父母による反対で失恋)をした。
そのため彼は、現実とかけ離れた愉快な世界が書きたかったと語っており、この作品がそうであったのではないかとされている。一見、この作品のどこが愉快なのかと疑問に思う人も少なくないだろう。彼は恋人である吉田弥生という女性と祖父母の反対を振り切り、本当なら駆け落ちすることもできたはずである。
しかし、昔は親が決めた家ごとの結婚がほとんどだった。そして自分は、その逆らった生き方ができなかった。
その点から下人には、自分と違った(世間に逆らった)生き方をとらせたかったため、下人を世間に反した(盗人)という道を小説の空想の中に歩ませたのではないかと考えられている。
この羅生門という作品は元々、「今昔物語」29巻弟18羅城門登上層見死人盗人語」による物だ。ここで、羅城門とされていることに違和感を感じる人がいるかもしれない。「羅城門」とは実際に平城京?平安京に存在した正門のことなのである。要は、今昔物語の話のShort Versionを芥川龍之介がたった半月の間に短編に仕立てた物であるということである。よくここまで短期間で話を深め広げたなぁと驚きを隠せない。
ではなぜ羅城門をわざわざ羅生門という名に変えたのか、このことについては後ほど述べていきたいと思う。
表現について
にきびという語の多用???現代に通ずる現代的な表現
元の作品において、時代は平安時代である。この時代にきびという物を気にする人はそういなかった。なぜなら昔はもっと深刻な疫病といった病が、はやっていたからである。現代のように抗生物質もない訳であり、人々も汚れた服、汚れた手である。この観点から、自意識が高く、自己中心的(自己中)だとうかがえる。
ニキビは若い人に多く、言い換えると未熟な人にできる、と、いうことである。
下人の醜い部分を象徴していたともとれる。
羅城門を羅生門とした理由
普通は羅城門を羅生門と名前を変える必要はない。しかし何故、芥川龍之介はわざわざ変えたのか。それは「生」を意識した作品が書きたかったからだろう。その理由は本文中に色濃く出ている。先ず、タイトルの変更したことの他に、「生」を持った動物、動物表現を用いた慣用句の多用であろう。からすやきりぎりすといった生物や、猫のように、ヤモリのようにといった表現であり、生への執着心、緊張感(薄気味悪さ)を表現している。「生」と言うコンセプトを書くつもりでなければこんなに文中に入れることはない。また、下人の生(盗人になって生き延びる)と死(飢え死に)の究極の選択を色濃く表現している。