日本节日
- 格式:doc
- 大小:72.50 KB
- 文档页数:7
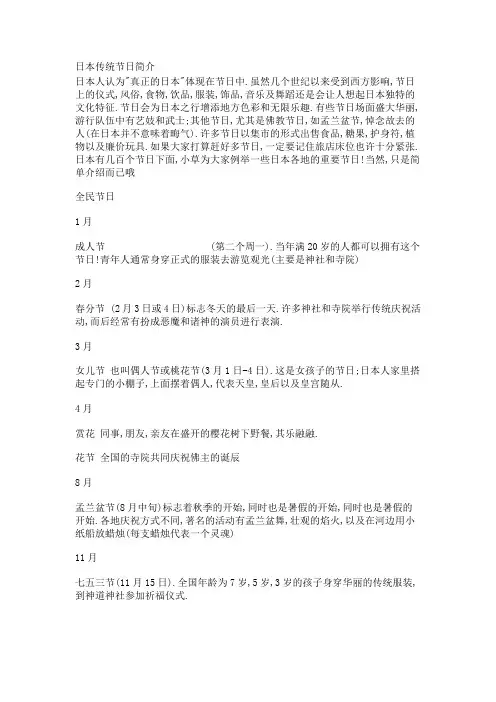
日本传统节日简介日本人认为"真正的日本"体现在节日中.虽然几个世纪以来受到西方影响,节日上的仪式,风俗,食物,饮品,服装,饰品,音乐及舞蹈还是会让人想起日本独特的文化特征.节日会为日本之行增添地方色彩和无限乐趣.有些节日场面盛大华丽,游行队伍中有艺妓和武士;其他节日,尤其是佛教节日,如孟兰盆节,悼念故去的人(在日本并不意味着晦气).许多节日以集市的形式出售食品,糖果,护身符,植物以及廉价玩具.如果大家打算赶好多节日,一定要记住旅店床位也许十分紧张.日本有几百个节日下面,小草为大家例举一些日本各地的重要节日!当然,只是简单介绍而已哦全民节日1月成人节 (第二个周一).当年满20岁的人都可以拥有这个节日!青年人通常身穿正式的服装去游览观光(主要是神社和寺院)2月春分节 (2月3日或4日)标志冬天的最后一天.许多神社和寺院举行传统庆祝活动,而后经常有扮成恶魔和诸神的演员进行表演.3月女儿节也叫偶人节或桃花节(3月1日-4日).这是女孩子的节日;日本人家里搭起专门的小棚子,上面摆着偶人,代表天皇,皇后以及皇宫随从.4月赏花同事,朋友,亲友在盛开的樱花树下野餐,其乐融融.花节全国的寺院共同庆祝佛主的诞辰8月孟兰盆节(8月中旬)标志着秋季的开始,同时也是暑假的开始,同时也是暑假的开始.各地庆祝方式不同,著名的活动有孟兰盆舞,壮观的焰火,以及在河边用小纸船放蜡烛(每支蜡烛代表一个灵魂)11月七五三节(11月15日).全国年龄为7岁,5岁,3岁的孩子身穿华丽的传统服装,到神道神社参加祈福仪式.东京1月出初式 (1月6日)消防队员们穿着某个时代的服装,沿着东京湾的晴海街游行在竹子梯子的顶端表演精彩的特技5月三社祭(5月17日左右).人们穿着某个时代的服装拥挤在浅草区的大街小巷.6月山王祭 (每年6月10日-16日).在日枝神社举行.每相隔一年,僧侣们会骑马,走在游行队伍的最前面,沿着浅草去主要街道游行.7月焰火节(7月最后一个周六)在浅草区的隅田川上举行.这是日本最盛大的焰火表演哦11月酉市 (11月中旬之前,每年时间不同)浅草区鹫神社和新宿区花园神社的夜市.夜市上出售装饰精美的竹耙子(祈求众神保佑多多赚钱)街上有精彩的通宵晚会,还有摊位出售酒,面条和叉烧肉.12月板羽市 (12月17-19日)这是千僧寺庆祝节日的通宵夜市.夜市上出售板羽球和用木刻印染的精美布料东京周边名胜4月镰仓节(4月第二个周日到第三个周日).集中在鹤冈的八幡宫,节日上的舞蹈和古代武士游行队伍非常富有特色.佩带武士勋章的弓箭手骑在马上格外引人注目.5月千人游行(5月17-18日)节日在日光的东照宫到达高潮.场面壮观,1000人穿着武士盔甲游行9月流马节(9月16日).在镰仓的八幡宫举行.最激动人心的是弓箭手的马上表演10月东照宫节(10月17日).这是日光东照宫的秋分节,身穿僧侣服装和武士服装的游行队伍极富特色11月大名游行(11月3日)盛装游行让人们想起了17世纪大名们沿着箱根汤本的东海道游行的场景北海道2月雪节(2月初)札幌雪节世界闻名,节日期间,巧夺天工,装饰美观的雪雕装点着市中心本州北部(东北地方)2月雪窖节(2月15日-16日)几个地方同时举行的儿童节,最有名的是秋田县横手地区的雪窖节.节日得名于节日中建造的雪窖;孩子们坐在温暖舒适的雪窖里,点燃蜡烛,旁边有一个火盆,用来煮甜酒,和别人一起分享.6月幼马节(6月15日)在盛冈市,养马人和卖马人愉快的牵着精心打扮的骏马游行,到SOZEN神社去祈福.8月睡魔节(8月1-7日)节日在青森市和宏前市同时举行,具有特色的是游行队伍中制作精美,绘画装饰一流的灯笼.竿灯节(8月4日-7日)在秋田市,游行队伍中最引人注目的是,男子举着挑着灯笼的木杆跳舞,将木杆不时的放在手上,肩上,下颌以及前额上.12月驱懒节(12月31日)在秋田县的男鹿半岛上举行.许多未婚男子身穿节日盛装,走门串户,告戒懒汉们,居民们用米糕和酒款待他们.本州中部(中部地方)3月丰收节(3月15日)犬山附近的田泻神社的丰收节最著名---该神社是日本仅存的40座生殖器崇拜时期的神社之一.游行队伍中竟然还有....不想说了....4月高山节(4月14-15日)节日主要在高山市的鹫神社举行.游行队伍中有12辆重型大货车,上面载12个屋台,屋台上有自动表演装置.5月鸬鹚捕鱼节(5月11日开始).从开始一直到10月15日,几乎每天都能起伏县的大量川上看到这种有趣的活动(如果正是旅游季节的话).船上点着火盆照亮,经过训练的鸬鹚借着亮光到水中捕鱼.10月高山市八幡宫节(10月9日-10日),主要在高山市八幡宫举行,该节日始于15世纪,漂亮的游车和神轿名不虚传.关西1月财神节(1月9-11日)在大阪LMAMIYA惠比须神社举行.成千上万的人参拜惠比须---财神,庇护商人,工人,渔家.妇女们身穿华丽的和服,坐着轿子游行若草山烧(1月15日)节日中火烧若草山(位于奈良公园内)上的草,以纪念两座寺院之间战争的结束.节日上还有热闹非凡的庆祝活动及焰火表演2月灯笼节(2月3日或4日)节日活动在奈良举行以迎接春天的到来.春日大社中所有的铜灯笼和石灯笼都被点燃3月取水节(3月1日-14日)自从公元9世纪以来,每年都在奈良的当代寺举行.最最激动人心的是3月12日那天,当水从若狭井里取出来的时候,手持火炬的人晃动火炬,星星点点,僧侣们则吹起螺号,场面格外动人.5月绿节(5月15日)在京都的下鸭神社和上茂神社举行.节日上,人们穿着华丽的服装,场面盛大,主要为了纪念来访的侍臣和僧侣.浮舟节(5月第三个周日)诗人,音乐家,舞蹈家身穿某个时代的服装,乘船在岚山大井川上表演.6月薪能节(6月1日-2日)点燃火炬标志着能乐表演的开始,演出在平安神社的露天剧场进行,主要演出艺术史上的主要剧目.播种节(6月14日).住吉神社举行,有12位佳丽主持的播种仪式.7月祗园节(整个7月,7月17日游行)这个著名的节日是为了9世纪突然结束的一场瘟疫,节日活动主要在京都的八坂神社举行.游行活动是节日的高潮,参加游行的人会穿着各式各样的衣服8月大字节(10月22日)庆祝活动伴随着焰火举行,京都市NYOIGA-DAKE的山坡上,火焰镂刻出巨大的[大]字10月时代节(10月22日)在京都的平安神社举行.庆祝活动最重要的部分是举行盛大的游行活动,游行者身穿各个时期的服装,庆祝794年京都市的建立.12月OKERA MAIRI 蝼蛄来节(12月31日)巨大的篝火于午夜在京都的八坂神社点燃,人们都从家里带来蜡烛,点燃新年里的第一把火.日本全国各个神社举行类似的活动本州西部(中国地方)2月EYO得(2月第三个周六)此节日是日本裸节在几个地方的别称(好奇怪的名字...),在冈山县西大寺市的西大寺举行.上百名年轻人只裹着缠腰布(......),在寺院的一座塔楼内比赛,看谁最先拿到两根魔杖.人们认为魔杖能保佑人一生幸运,通常由僧侣将魔杖扔到人群之中,活动拒绝参观...6月管弦乐节(农历6月17日,每年具体日期都会发生变化)庆祝活动在宫岛市的严岛神社举行,在装饰华丽的游船上展示古代宫廷舞蹈和音乐.8月和平纪念日(8月6日)在广岛,人们通过祷告,慰藉原子弹爆炸中遇难者的亡灵.10月吵架节(10月14-15日)在姬路市松原神社,抬轿的人分为几组,争抢着走道游行队伍的前列,尽力挤掉对手的神轿;活动非常有趣,但是也十分危险四国岛和濑户内海7月WAREI NATSU MATSURI 分割夏天的祭祀(7月23日-24日).宇和岛上有焰火表演,火炬游行以及斗牛活动8月阿波舞节(8月12-15日)德岛市男女老少穿着节日盛装尽情欢跳,数千名游客也加入其中,整个活动持续四天之久九州5月港节(5月3日-4日)福冈市的居民身穿节日盛装,装扮成神或者魔鬼,组成五颜六色的游行队伍,有些人还骑着马游行.7月博多祗园山笠(7月1-15日).最后一天是节日的高潮,在福冈市的街道上,人们分成若干组进行花车比赛,花车上有城堡模型,偶人,武士等10月Ok, let me talk something about the national holidays in Japan,The same as many other countries saturday and sunday are rest days in Japan, and there are some special daysare rest days too, this is the list1/01 -- New Year's DayThe second Monday in January -- Coming of Age Day2/11 -- National Foundation Day (It is very surprised that many Japanese don't know why they needn't work in this day.)3/21 -- Vernal Equinox Day4/29 -- Greenery Day5/03 -- Constitution Memorial Day5/04 -- National Holiday (No cause)5/05 -- Children's Day (So we can see golden week comes from the near holidays in May)The third Monday in July -- Marine DayThe third Monday in September -- Respect for the Aged Day9/22 -- National Holiday (No cause)9/23 -- Autumnal Equinox Day (That's why I needn't work yesterday)The second Monday in October -- Health and Sports Day (Many schools will have their athletic meeting)11/03 -- National Culture Day11/23 -- Labor Thanksgiving Day12/23 -- The Emperor's Birthday (for current emperor)In this site you will get a detail introduction,unfortunately it is wrote by Japanese.New Year "Shogatsu"As you know, the New Year holiday in Japan "shogatsu" is the absolute most celebrated of all holidays in Japan. There are scattered holidays throughout this period but most large companies (including mine), public offices and the like observe the holiday from about December 29 to January 4 and then again or onward to the second monday of January which is Comming of Age Day "seiji no hi" a national holiday. The days leading up to the New Year are some of the busisiest times of the year for everyone here as the Japanese believe in clearing out the past year in every way. It is also one of the most busiest travel seasons here as well so book early! But being the most busiest travel season has its benefits here in Tokyo as most people travel outside of Tokyo or to foreign destinations during this period and Tokyo is empty so its a nice time to visit. It's a bit chilly here but still a nice time to visit I think.Spring "Golden Week"Golden Week is a collection of four national holidays within seven days in Spring. In combination with well placed weekends and days off in between or a little bit before or after, the Golden Week becomes one of Japan's three busiest holiday seasons, besides New Year and the Obon week. As for the weather, it is one of the best times as the cherry blossoms are just about in full bloom and it's just perfect not too cold and not too hot just like the weather in Autumn now when the leaves turn color "kouyo" but unfortunately we really don't have long holiday periods during Autumn here. Anyway, back to Golden Week; trains, airports and sightseeing spots get very crowded during Golden Week, and accommodation in tourist areas can get booked out well in advance. The national holidays making up the Golden Week are; Showa Day (Showa no hi) on April 29 which is the birthday of former Emperor Showa, who died in the year 1989. Until 2006, Greenery Day (now May 4) used to be celebrated on this day, Constitution Day (Kenpo kinenbi) on May 3 which is when on this day in 1947 the new post war constitution was put into effect, Greenery Day (Midori no hi) on May 4 which until 2006, used to be celebrated on April 29, the birthday of former Emperor Showa. The day is dedicated to the environment and nature, because the emperor loved plants and nature. Before being declared Greenery Day, May 4 used to be a national holiday due to a law, which declares a day, that falls between two national holidays, a national holiday. Children's Day (Kodomo no hi) on May 5 when the Boy's Festival (Tango no Sekku) is celebrated. Families pray for the health and future success of their sons by hanging up carp streamers and displaying samurai dolls, both symbolizing strength, power and success in life. The Girl's Festival, by the way, is celebrated on March 3. In 2009, the weekends are placed slightly more favorably, creating a holiday of four consecutive days. Travel activity is anticipated to peak on May 2 with people leaving the large urban centers and on May 5 in the opposite direction. Increased traffic can also be expected on April 29 and May 4.Summer "Obon"The other long holiday here is Summer Break or "obon" but it's probably one of the worst times of the year to visit Japan because it is so humid and hot everyday dripping wet. The only good thing about visiting in during this season is to see one of the many only in summer fireworks "hanabi" festivals "matsuri" in fact many matsuri of all kinds including huge music events are all concentrated in the summer here. Obon is actually an annual Buddhist event for commemorating one's ancestors. It is believed that each year during obon, the ancestors' spirits return to this world in order to visit their relatives. Traditionally, lanterns are hang in front of houses to guide the ancestors' spirits, obon dances (bon odori) are performed, graves are visited and food offerings are made at house altars and temples. At the end of Obon, floating lanterns are put into rivers, lakes and seas in order to guide the spirits back into their world. The customs followed vary strongly from region to region. Obon is celebrated from the 13th to the 15th day of the 7th month of the year, which is July according to the solar calendar. However, since the 7th month of the year roughly coincides with August rather than Julyaccording to the formerly used lunar calendar, Obon is still celebrated in mid August in many regions of Japan, while it is celebrated in mid July in other regions. In Tokyo it is mostly celebrated in mid August and we usually have almost two weeks off. The Obon week in mid August is one of Japan's three major holiday seasons, accompanied by intensive domestic and international travel activities and increased accommodation rates. In 2008, the peak of the Obon travel season was between August 12 and 17.FlexibleBut all our holidays are pretty much flexible and can be taken either earlier or later depending on workload conditions. So I could even take my obon holiday in Autumn when the leaves turn color "kouyo" instead of the designated holiday period in mid August. Actually my schedule is quite flexible depending on workload conditions so let me know when you guys would like to visit so I can check my schedule and let you know1月1日元旦是新的一年中最初的一天,也是祈求在新的一年能幸运、幸福,和拟定这一年的计划的日子,这一天也到神社或附近的寺庙去做第一次的参拜。
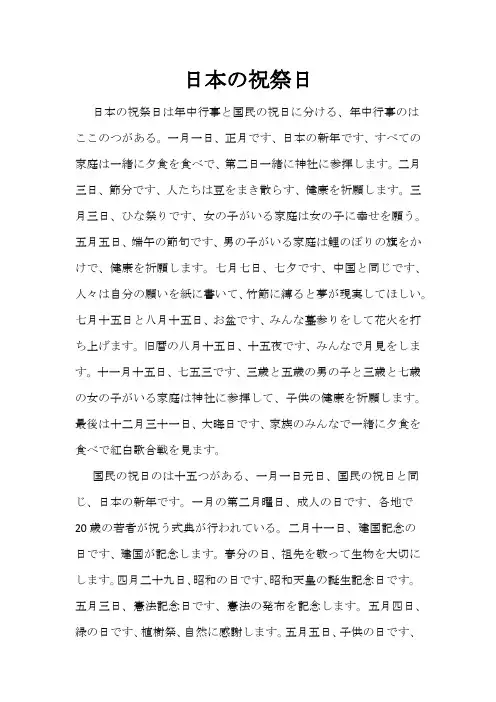
日本の祝祭日日本の祝祭日は年中行事と国民の祝日に分ける、年中行事のはここのつがある。
一月一日、正月です、日本の新年です、すべての家庭は一緒に夕食を食べで、第二日一緒に神社に参拝します。
二月三日、節分です、人たちは豆をまき散らす、健康を祈願します。
三月三日、ひな祭りです、女の子がいる家庭は女の子に幸せを願う。
五月五日、端午の節句です、男の子がいる家庭は鯉のぼりの旗をかけで、健康を祈願します。
七月七日、七夕です、中国と同じです、人々は自分の願いを紙に書いて、竹節に縛ると夢が現実してほしい。
七月十五日と八月十五日、お盆です、みんな墓参りをして花火を打ち上げます。
旧暦の八月十五日、十五夜です、みんなで月見をします。
十一月十五日、七五三です、三歳と五歳の男の子と三歳と七歳の女の子がいる家庭は神社に参拝して、子供の健康を祈願します。
最後は十二月三十一日、大晦日です、家族のみんなで一緒に夕食を食べで紅白歌合戦を見ます。
国民の祝日のは十五つがある、一月一日元日、国民の祝日と同じ、日本の新年です。
一月の第二月曜日、成人の日です、各地で20歳の若者が祝う式典が行われている。
二月十一日、建国記念の日です、建国が記念します。
春分の日、祖先を敬って生物を大切にします。
四月二十九日、昭和の日です、昭和天皇の誕生記念日です。
五月三日、憲法記念日です、憲法の発布を記念します。
五月四日、緑の日です、植樹祭、自然に感謝します。
五月五日、子供の日です、子供に幸せを願ってお母さんにお礼を言ます。
七月の第三月曜日、海の日です、海の恵みに感謝して、日本の繁栄を願います。
九月の第三月曜日、敬老の日です、各地で芸能活動をして記念品を贈る、そして、長年で社会に力を貢献するの老人に感謝て、健康長寿をお祈りします。
秋分の日、祖先を敬います。
十月第二月曜日、体育の日です、千九百六十四年十月十日に東京で行われるオリンピック運動会を記念して、スポーツ運動を提唱と、国民の健康を促進します。




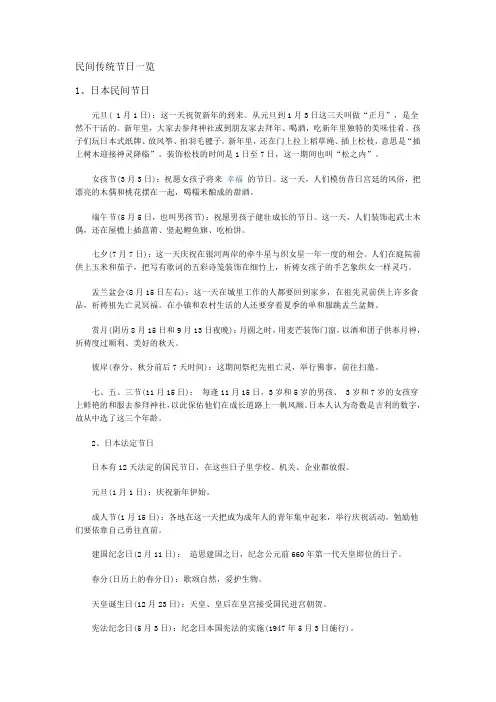
民间传统节日一览1、日本民间节日元旦( 1月1日):这一天祝贺新年的到来。
从元旦到1月3日这三天叫做“正月”,是全然不干活的。
新年里,大家去参拜神社或到朋友家去拜年、喝酒,吃新年里独特的美味佳肴。
孩子们玩日本式纸牌、放风筝、拍羽毛毽子。
新年里,还在门上拉上稻草绳、插上松枝,意思是“插上树木迎接神灵降临”。
装饰松枝的时间是1日至7日,这一期间也叫“松之内”。
女孩节(3月3日):祝愿女孩子将来幸福的节日。
这一天,人们模仿昔日宫廷的风俗,把漂亮的木偶和桃花摆在一起,喝糯米酿成的甜酒。
端午节(5月5日,也叫男孩节):祝愿男孩子健壮成长的节日。
这一天,人们装饰起武士木偶,还在屋檐上插菖莆、竖起鲤鱼旗、吃柏饼。
七夕(7月7日):这一天庆祝在银河两岸的牵牛星与织女星一年一度的相会。
人们在庭院前供上玉米和茄子,把写有歌词的五彩诗笺装饰在细竹上,祈祷女孩子的手艺象织女一样灵巧。
盂兰盆会(8月15日左右):这一天在城里工作的人都要回到家乡,在祖先灵前供上许多食品,祈祷祖先亡灵冥福。
在小镇和农村生活的人还要穿着夏季的单和服跳盂兰盆舞。
赏月(阴历8月15日和9月13日夜晚):月圆之时,用麦芒装饰门窗,以酒和团子供奉月神,祈祷度过顺利、美好的秋天。
彼岸(春分、秋分前后7天时间):这期间祭祀先祖亡灵,举行佛事,前往扫墓。
七、五、三节(11月15日):每逢11月15日,3岁和5岁的男孩、 3岁和7岁的女孩穿上鲜艳的和服去参拜神社,以此保佑他们在成长道路上一帆风顺。
日本人认为奇数是吉利的数字,故从中选了这三个年龄。
2、日本法定节日日本有12天法定的国民节日,在这些日子里学校、机关、企业都放假。
元旦(1月1日):庆祝新年伊始。
成人节(1月15日):各地在这一天把成为成年人的青年集中起来,举行庆祝活动,勉励他们要依靠自己勇往直前。
建国纪念日(2月11日):追思建国之日,纪念公元前660年第一代天皇即位的日子。
春分(日历上的春分日):歌颂自然,爱护生物。
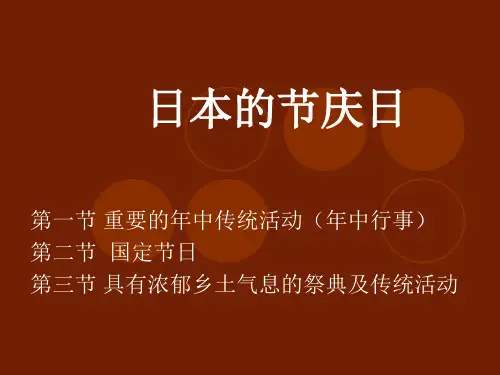
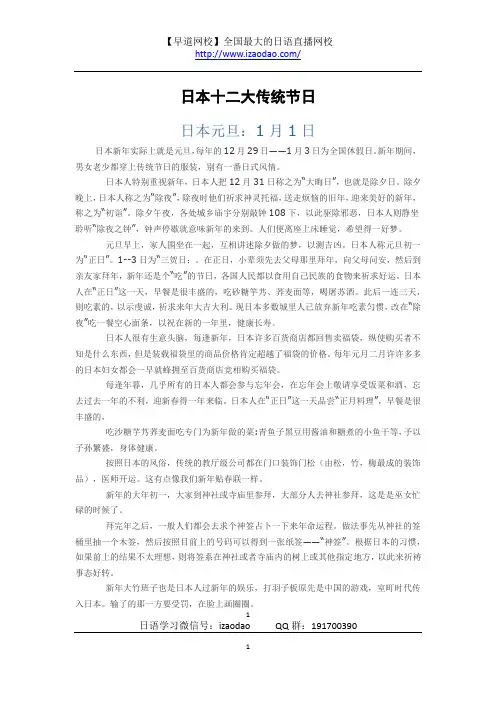
日本十二大传统节日日本元旦:1月1日日本新年实际上就是元旦,每年的12月29日——1月3日为全国休假日。
新年期间,男女老少都穿上传统节日的服装,别有一番日式风情。
日本人特别重视新年,日本人把12月31日称之为“大晦日”,也就是除夕日。
除夕晚上,日本人称之为“除夜”,除夜时他们祈求神灵托福,送走烦恼的旧年,迎来美好的新年,称之为“初诣”。
除夕午夜,各处城乡庙宇分别敲钟108下,以此驱除邪恶,日本人则静坐聆听“除夜之钟”,钟声停歇就意味新年的来到。
人们便离座上床睡觉,希望得一好梦。
元旦早上,家人围坐在一起,互相讲述除夕做的梦,以测吉凶。
日本人称元旦初一为“正日”。
1--3日为“三贺日:。
在正日,小辈须先去父母那里拜年,向父母问安,然后到亲友家拜年,新年还是个“吃”的节日,各国人民都以食用自己民族的食物来祈求好运。
日本人在“正日”这一天,早餐是很丰盛的,吃砂糖竽艿、荞麦面等,喝屠苏酒。
此后一连三天,则吃素的,以示虔诚,祈求来年大吉大利。
现日本多数城里人已放弃新年吃素匀惯,改在“除夜”吃一餐空心面条,以祝在新的一年里,健康长寿。
日本人很有生意头脑,每逢新年,日本许多百货商店都回售卖福袋,纵使购买者不知是什么东西,但是装载福袋里的商品价格肯定超越了福袋的价格。
每年元月二月许许多多的日本妇女都会一早就蜂拥至百货商店竞相购买福袋。
每逢年暮,几乎所有的日本人都会参与忘年会,在忘年会上敬请享受饭菜和酒,忘去过去一年的不利,迎新春得一年来临。
日本人在“正日”这一天品尝“正月料理”,早餐是很丰盛的,吃沙糖芋艿荞麦面吃专门为新年做的菜:青鱼子黑豆用酱油和糖煮的小鱼干等,予以子孙繁盛,身体健康。
按照日本的风俗,传统的教厅级公司都在门口装饰门松(由松,竹,梅最成的装饰品),医师开运。
这有点像我们新年贴春联一样。
新年的大年初一,大家到神社或寺庙里参拜,大部分人去神社参拜,这是是巫女忙碌的时候了。
拜完年之后,一般人们都会去求个神签占卜一下来年命运程。
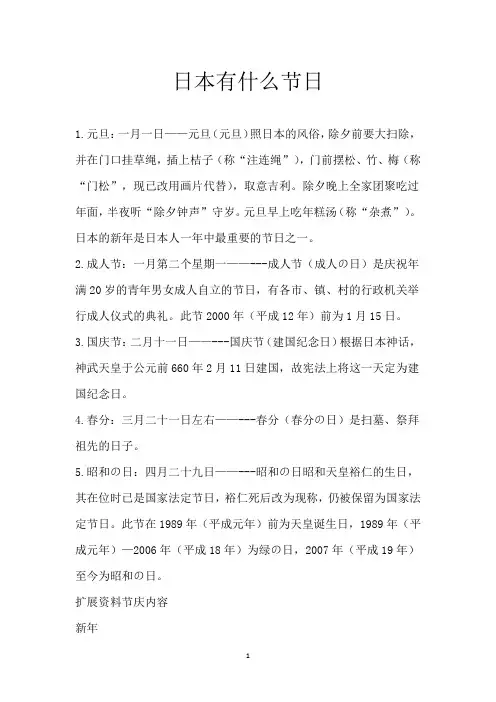
日本有什么节日1.元旦:一月一日——元旦(元旦)照日本的风俗,除夕前要大扫除,并在门口挂草绳,插上桔子(称“注连绳”),门前摆松、竹、梅(称“门松”,现已改用画片代替),取意吉利。
除夕晚上全家团聚吃过年面,半夜听“除夕钟声”守岁。
元旦早上吃年糕汤(称“杂煮”)。
日本的新年是日本人一年中最重要的节日之一。
2.成人节:一月第二个星期一——---成人节(成人の日)是庆祝年满20岁的青年男女成人自立的节日,有各市、镇、村的行政机关举行成人仪式的典礼。
此节2000年(平成12年)前为1月15日。
3.国庆节:二月十一日——---国庆节(建国纪念日)根据日本神话,神武天皇于公元前660年2月11日建国,故宪法上将这一天定为建国纪念日。
4.春分:三月二十一日左右——---春分(春分の日)是扫墓、祭拜祖先的日子。
5.昭和の日:四月二十九日——---昭和の日昭和天皇裕仁的生日,其在位时已是国家法定节日,裕仁死后改为现称,仍被保留为国家法定节日。
此节在1989年(平成元年)前为天皇诞生日,1989年(平成元年)—2006年(平成18年)为绿の日,2007年(平成19年)至今为昭和の日。
扩展资料节庆内容新年在日本的传统里,新年是感谢带来五谷丰登的神的时候,也是欢迎保佑自己的祖先神灵的时候。
日本人习惯在门的两旁悬挂松、竹和草绳,就是为了欢迎这些神和神灵。
一年之始,人们向神和祖先的灵表示感谢,并且祈祷新的一年有好收成。
对于日本人来讲,新年是一年当中最重要的节日。
许多人都在这个时候定计划、下决心。
新年贺卡新年期间,人们收到亲戚朋友和熟人寄来的贺卡,叫做“年贺状”(年贺状)。
2003年新年日本人寄出的贺卡大约是35亿张。
参拜寺庙在新年的日子里,亲友团聚,大家相约同去参拜神道教或者佛教的寺庙,这种活动叫做“初诣”。
如果去神道教的庙,人们会选择相对家庭来说处于“有利方位”的神庙。
参拜的目的也是乞求丰收和家庭平安。
参拜人数最多的是东京的明治神宫(2003年300万),其次千叶的成田川新修寺(265万),再次是是神奈川的川崎(260万)。
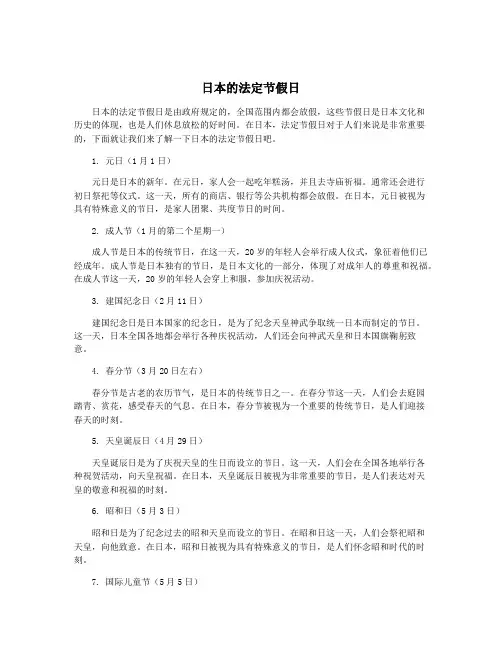
日本的法定节假日日本的法定节假日是由政府规定的,全国范围内都会放假,这些节假日是日本文化和历史的体现,也是人们休息放松的好时间。
在日本,法定节假日对于人们来说是非常重要的,下面就让我们来了解一下日本的法定节假日吧。
1. 元日(1月1日)元日是日本的新年。
在元日,家人会一起吃年糕汤,并且去寺庙祈福。
通常还会进行初日祭祀等仪式。
这一天,所有的商店、银行等公共机构都会放假。
在日本,元日被视为具有特殊意义的节日,是家人团聚、共度节日的时间。
2. 成人节(1月的第二个星期一)成人节是日本的传统节日,在这一天,20岁的年轻人会举行成人仪式,象征着他们已经成年。
成人节是日本独有的节日,是日本文化的一部分,体现了对成年人的尊重和祝福。
在成人节这一天,20岁的年轻人会穿上和服,参加庆祝活动。
3. 建国纪念日(2月11日)建国纪念日是日本国家的纪念日,是为了纪念天皇神武争取统一日本而制定的节日。
这一天,日本全国各地都会举行各种庆祝活动,人们还会向神武天皇和日本国旗鞠躬致意。
4. 春分节(3月20日左右)春分节是古老的农历节气,是日本的传统节日之一。
在春分节这一天,人们会去庭园踏青、赏花,感受春天的气息。
在日本,春分节被视为一个重要的传统节日,是人们迎接春天的时刻。
5. 天皇诞辰日(4月29日)天皇诞辰日是为了庆祝天皇的生日而设立的节日。
这一天,人们会在全国各地举行各种祝贺活动,向天皇祝福。
在日本,天皇诞辰日被视为非常重要的节日,是人们表达对天皇的敬意和祝福的时刻。
6. 昭和日(5月3日)昭和日是为了纪念过去的昭和天皇而设立的节日。
在昭和日这一天,人们会祭祀昭和天皇,向他致意。
在日本,昭和日被视为具有特殊意义的节日,是人们怀念昭和时代的时刻。
7. 国际儿童节(5月5日)国际儿童节是为了庆祝儿童的节日。
在这一天,孩子们会和家人一起举行各种庆祝活动,会有各种儿童节目,例如游戏、表演等。
在日本,国际儿童节是一个重要的节日,是人们向儿童送上祝福和关爱的时刻。
元旦(1月1日):日语中叫“元日”,亦即新年。
成人节(1月15日):庆祝年满20周岁的青年成为具有公民仅的“大人”的节日。
每到这一天,基层地方政府一般都将从前一年的4月2日至当年4月1日期间满20岁的青年男女集合起来举行成人仪式。
建国纪念日(2月11日):传说中神武天皇即位的日子,
春分节(3月21日前后):原为“春季皇灵祭”但基于政教分离原则改为现称,其含义亦改为“赞美自然,爱惜生物。
”
绿色纪念日(4月29日):昭和天皇裕仁的生日,裕仁死后改为现称。
宪法纪念日(5月3日):为纪念现行《日本国宪法》,1947年付诸实施而设立的节日。
儿童节(5月5日):原称端午节,吃粽子和柏饼(年糕),江户时代称男孩节,带有武家遗风,1948年改为现称。
敬老日(9月15日):1966年设立,其含义为“向多年为社会做出贡献的老年人表示敬意,祝老年人长寿”。
秋分节(9月23日前后):原为“秋季皇灵祭”,1948年改为现称,法定含义“缅怀祖先,悼念死者”。
体育节(10月10日):是1964年东京奥运会开幕的日子,1966年定为国家节日,意在鼓励人们“喜欢体育,锻炼健康体魄”。
文化节(11月3日):明治天皇睦仁的生日,1927年被定为“明治节”。
1948年改为现称,其宗旨是“热爱自由与和平,崇尚文化”。
勤劳感谢日(11月23日):原是举行“新尝祭”的日子,即天皇要在这一天举行将新收获的谷物奉献于诸神灵前的仪式。
1948年改为现称,法定宗旨是“尊重勤劳,祝贺生产,国民互相感谢”。
天皇诞辰(12月23日):现天皇明仁的生日,1988年即位后被定为国家节日。
日本的节日1、成人节:每年1月第2个星期一。
日本的成人节源于古代的成人仪礼,而日本古代的成人仪礼是受中国“冠礼”的影响。
所谓“冠礼”,指男子成年时举行的一种加冠的礼仪。
从加冠这天起,冠者便被社会承认为已经成年。
日本仿我国旧礼制,始行加冠制度在天武天皇十一年(公元683年)。
2、男孩节(端午节):5月5日。
在这一天,有儿子的家庭门前均悬挂着祝男孩子健康成长、出人头地的“鲤鱼旗”。
日本以阳历5月5日作为端午节。
端午节与男孩节同日,所以这天家家户户门上还摆菖蒲叶,屋内挂钟馗驱鬼图,吃去邪的糕团(称“柏饼”)或粽子。
“鲤鱼旗”表示鲤鱼跳龙门。
鲤鱼旗是用布或绸做成的空心鲤鱼,分为黑、红和青蓝三种颜色,黑代表父亲、红代表母亲、青蓝代表男孩,青蓝旗的个数代表男孩人数。
3、海之日:7月20日。
制定于1941年,从1996年起成为国民纪念日。
日本四面环海,为了感谢得自海洋的恩典,并祈祷能成为国运昌隆的海洋国家而制订。
4、敬老节:9月15日。
日本人到42岁时才可以称“寿”做生日,通常被称为“初老”。
到60岁时称为“还历”。
77岁时为“喜寿”,88岁时为“米寿”,99岁为“白寿”,即百字少一,活到百岁就是“百寿”了。
每年9月15日,日本各地都要开展敬老活动,为老人体检、整理修缮房屋、敬赠纪念品、组织慰问等。
老人则根据自己的爱好,开展有益身心的活动。
日本厚生省在这一天还要发布“长寿者名单”,登载在各地报纸上,只有百岁以上高龄者才能入闱。
5、体育节:10月第2个星期一。
纪念1964年第十八届奥运会在日本东京开幕。
6、女孩节(偶人节):3月3日。
这是日本女孩子的节日。
这个节日起源很早,要上朔到700年前的平安时代。
如今的庆祝方式是从江户时代传下来的。
有女孩子的家庭都要供出小巧的偶人(也叫“雏人形”),祝愿家中女孩成长与吉祥。
这种小偶人价格昂贵,女孩的父母,尤其是外祖父母,差不多都要为她买一套精美的小偶人。
少的摆一层,多的用“偶人架”摆上好几层,最多的可摆七、八层,而最上的一层,大多是一个皇帝和一个皇后。
日本传统节日日本作为一个充满着丰富文化传统的国家,拥有着许多独特的传统节日。
这些节日在日本人的日常生活中扮演着重要的角色,不仅代表着对祖先的敬意和感激之情,同时也是人们放松身心、享受生活的机会。
在下面的文档中,我们将介绍一些具有代表性的日本传统节日。
1. 春分(Shunbun)春分是一年中的两个昼夜时间相等的日期,也是日本传统农历上春季的第一个节气。
在这一天,人们会前往祖先的墓地,清扫和整理墓地,并且祭奠祖先的灵魂。
人们还会祈祷丰收和健康,许多人会在家里摆放丰盛的祭品,如食物、花卉和艺术品。
2. 樱花节(Hanami)樱花节是日本春天最受欢迎的节日之一,也是日本的国花樱花盛开的季节。
人们会在公园、街道和庭院里欣赏樱花的美丽,这也是一种传统的赏花活动,被称为“花见(Hanami)”。
人们会带着食物、饮料和朋友一起前往樱花树下野餐,畅享樱花的美景。
很多人还会在夜晚参加“夜樱(Yozakura)”,在灯光下赏花,创造出幻想般的氛围。
3. 端午(Tango)端午是一个庆祝儿童成长和保护健康的节日。
这一天,人们会在家里准备一种叫做“端午粽(kashiwamochi)”的米糕,这是一种用树叶包裹着的甜味食物。
人们还会佩戴传统的五彩丝带,用于驱赶邪恶和保护儿童的健康成长。
此外,端午也是一种庆祝丰收和驱除恶灵的机会,在一些地方还会有舞龙舞狮和划船比赛等庆祝活动。
4. 盂兰(Obon)盂兰节是一个用于纪念祖先灵魂的传统节日。
在这一天,人们认为亡灵回到人间,并且会为他们准备食物和鲜花。
人们还会在家里挂起精心制作的灯笼,烛光将亡灵引导回家。
在一些地方,还会有盂兰盆舞和盂兰盆火焰节等庆祝活动。
此外,人们也会拜访墓地,祭拜祖先。
5. 新年(Shogatsu)新年是日本最重要的节日之一,也是一个庆祝新年到来、祈求来年好运和健康的时刻。
人们会在12月31日的晚上打磬,以驱除邪恶。
在新年的第一天,人们会前往神社或寺庙祈求神灵的保佑,并且用鞭炮和锣鼓声来驱赶邪恶。
七五三(十一月十五日)読み方:しちごさん三歳の男女、五歳の男子、七歳の女子が11月15日にお宮参りをし、子供の成長を祝う行事です。
子供たちは晴れ着に身を包み、子供自身にもその自覚を与えるためのものです。
、子供が元気によく成長するよう、また長生きするように、という願いがこめられています千歳飴〔ちとせあめ〕を持って家族に連れられ、各地の神社にお参りし、記念撮影するのが一般的です。
体育の日の由来(十月第三个星期一)『体育の日』の由来は、1964年に開催された東京オリンピックの開会式から来ています。
ゕジゕ圏で、初めてのオリンピック開催日が10月10日だったため、その日を記念して体育の日が作られました。
体育の日は、その名の通り、スポーツに関係する記念日で、運動会がよく開催される日でもあります。
ちなみに10/10は、晴れる日が多いのです。
3月のひな祭り__もろみや(三月三日)女の子にとっては、春に祝う大きな行事は「ひな祭り」である。
「ひな祭り」は「桃の節句」とも呼ばれ、これも中国の行事から始まったもので、日本の宮中にあった野に出て紙人形で遊ぶ「ひいな遊び」と結びついたものである。
昔から桃には邪気をはらう力があるとされ、この桃の信仰と宮中で行われたひな祭りが結びついたのは、旧暦の3月3日の頃が桃の花の季節だったためだろう。
昔のひな祭りは紙や木などで作った人形の体をさすり、身のけがれや厄をうつして、それを川に流すことで無病息災を願うという行事だった。
最近は住居スペースを考えて、小さな5段のひな人形に人気が集まっている。
ひな人形はお節句の一週間前までには飾って、その日が来るのを楽しみに待ち、片づけは3月3日の翌日に、遅くても3月中旬までにすます。
これ以上遅くなると、縁遠くなると言われている。
大晦日(十二月三十一)1年の最後の日を「大晦日〔おおみそか〕」または「大晦〔おおつごもり〕」とも呼びます。
「晦日〔みそか〕」とは毎月の末日のことです。
一方「晦〔つごもり〕」とは、"月が隠れる日"すなわち「月隠〔つきごもり〕」が訛ったもので、どちらも毎月の末日を指します。
"1年の最後の特別な末日"を表すため、末日を表す2つの言葉のそれぞれ「大」を付けて「大晦日」「大晦」と言いいます。
大晦日の風物詩である年越し蕎麦〔としこしそば〕は江戸時代頃から食べられるようになりました。
金箔職人が飛び散った金箔を集めるのに蕎麦粉を使ったことから、年越し蕎麦を残すと翌年金運に恵まれないと言われていますお盆(八月十五日)仏教用語の「盂蘭盆」の省略形として「盆」(一般に「お盆」)と呼ばれる。
盆とは文字どおり、本来は霊に対する供物を置く容器を意味するため、供物を供え祀られる精霊の呼称となり、盂蘭盆と混同されて習合したともいう説もある。
現在でも精霊をボンサマと呼ぶ地域がある。
迎え火 13日夕刻の野火を迎え火(むかえび)と呼ぶ。
以後、精霊棚の故人へ色々なお供え物をする。
地域によっては、「留守参り」をするところもある。
留守参りとは、故人がいない墓に行って掃除などをすることをいう。
御招霊など大がかりな迎え火も行われる。
送り火 16日の野火を送り火(おくりび)と呼ぶ。
京都の五山送り火が有名である。
15日に送り火を行うところも多い(奈良高円山大文字など)また、川へ送る風習もあり灯籠流しが行われる。
山や川へ送る点は、釜蓋朔日で記したとおり故人が居るとされるのが文化的に山や川でありそのようになる。
なお、故人を送る期間であるが、16日から24日までであり、お迎え同様に墓参などをして勤める。
月見月見は、日本では特に旧暦8月15日と旧暦9月13日に月を鑑賞することを指す場合がある。
前者の夜または月の状態を「十五夜」、後者のを「十三夜」と呼ぶ。
中国や日本では、単に月を愛でる習慣であれば古くからあり、日本では縄文時代頃からあると言われる。
中国から仲秋の十五夜に月見の祭事が伝わると、平安時代頃から貴族などの間で観月の宴や、舟遊び(直接月を見るのではなく船などに乗り水面に揺れる月を楽しむ)で歌を詠み、宴を催した。
また、平安貴族らは月を直接見ることをせず、杯や池にそれを映して楽しんだという。
夏祭り日本の夏祭りの多くは、起源的には盂蘭盆会(盆)・七夕・祇園祭などが絡んだものやその周辺的な行事であるものが多い。
したがって、旧暦では6~7月の行事に当たる。
また農村社会では夏季の農事による労働の疲れに関わる行事、都市社会では江戸時代以前の夏季の疫病封じ、その死者を弔う行事を起源とするものが多い傾向にある。
ただし、近代化によって変質したものも多い(従ってその起源はあまり認識されず、夏祭りは一般的に厳粛な行事ではなく華やかな行事とされる傾向が強い)。
また江戸時代以前には起源がなく、専ら近現代的な行事として始まったものや他地域の伝統的な夏祭りを模倣した(またその影響下にある)ものも多い。
とりわけ、8月の旧盆の時期をはさんだ夏祭りは帰省の時期と相まって祭礼中での懐かしい人との再会など感慨深いものがあるとされる。
卒業式(四月)卒業式(そつぎょうしき)は、教育課程を全て修了した事を認定し、そのお祝いをする式典であり、学校教育法施行規則によって定められた日本の学校行事である。
大学・大学院においては「卒業証書」ではなく「学位記」が授与される為、「学位記授与式」または「卒業証書・学位記授与式」となる。
欧米でも大学の学位授与の式典はあるが、各学校の修了ごとに祝う式典は日本と韓国で見られる習慣である。
制服制度のない場合、(校則の範囲内ではあるが)卒業生や出席する在校生の服装が自由であることはいうまでもない。
しかし、多くの卒業生は親などの意向や、慣例の墨守として改まった服装を着用することが多い。
また、その服装文化には、「在校時のフォーマルな服装」場合と、卒業後のフォーマルな(あるいは日常的に着用する)服装に近いものとの2つの文化があるが、後者に近い服装文化が優勢といえる。
入学式(三月)入学式(にゅうがくしき)とは、学校に入学することを許可し、そのお祝いをする式典のことである。
日本では一般に春の行事と考えられているが、欧米では、一般に9月に行われる秋の行事である。
なお、就学年齢に達した日から学校に通うなど、制度上、入学式が行えないところもある。
また、幼稚園などに入園するときは「入園式」と称される。
学習指導要領では、「その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と定められている。
入学式(及び卒業式)における日章旗の掲揚、君が代の斉唱については、さまざまな問題が発生している。
式の進行1新入生入場 2新入生の氏名読み上げ3校長による式辞4新入生代表による宣誓 5校歌斉唱6対面式花見(三月-五月)桜の木は日本全国に広く見られその花は春の一時期にある地域で一斉に咲き、わずか2週間足らずという短い期間で散るため毎年人々に強い印象を残し、日本人の春に対する季節感を形成する重要な風物となっている。
その開花期間の短さ、そしてその花の美しさはしばしば人の命の儚さになぞらえられる。
そのためか古来、桜は人を狂わせるといわれ、実際花見の席ではしばしば乱痴気騒ぎが繰り広げられる。
一方で花を見ながら飲む酒は花見酒と呼ばれ、風流だともされている。
陰陽道では、桜の陰と宴会の陽が対になっていると解釈する文化の日文化の日(ぶんかのひ)は、日本の国民の祝日の一つで、日付は11月3日である。
国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」)では「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としている。
この日皇居では文化勲章の授与式が行われる。
また、この日を中心に、文化庁主催による芸術祭が開催される。
また、この日は晴天になる確率が高く、「晴れの特異日」として有名である。
博物館の中にはこの日に入館料を無料にしたり、様々な催し物を開催する所もある。
憲法記念日(けんぽうきねんび)昭和22年(1947)5月3日、日本国憲法が発布されました。
それを記念して昭和23年7月の「国民の祝日に関する法律」で、この日が祝日と定められました。
その後今年でもう50年にわたってこの憲法は全く改正を加えられることなく継続し、天皇象徴制・三権分立・民主主義・人権尊重・平和主義などをうたっています。
成人の日(せいじんのひ)1月の第2月曜日。
「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」趣旨の国民の祝日。
1948年(昭和23)制定。
従来は1月15日であったが、2000年から1月の第2月曜日となる。
社会成員の認知を受ける通過儀礼ともいえる。
20歳に達した青年男女を対象に成人式を催し記念品を贈る市区町村が多いが、地方では都会に出た若者が帰郷する8月に成人式を行う所もある。
こどもの日5月5日。
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨とした国民の祝日。
1948年(昭和23)制定。
この日から11日まで児童福祉週間が行われる。
古来、男児の節供とされる端午(たんご)の節供にあたるため、女児の桃の節供雛祭(ひなまつり)の3月3日も祝日にすべきだという主張が一部では出されている。
端午の節句(たんごのせっく)「端午の節句」は5月5日にあたり、「菖蒲〔しょうぶ〕の節句」とも言われます。
強い香気で厄を祓う菖蒲やよもぎを軒(のき)につるし、また菖蒲湯に入ることで無病息災を願いました。
また、「菖蒲」を「尚武〔しょうぶ〕」という言葉にかけて、勇ましい飾りをして男の子の誕生と成長を祝う「尚武の節句」でもあります。
男の節句とされていたので昔は鎧や兜はお父さんやおじいちゃんが飾るのが習わしでしたが、現在では特にこだわる必要はないそうです。
4月中旬までには飾りの準備を終わらせ、当日か前日の晩には両家両親や知人を招き、縁起物のご馳走でもてなします。
また、今でも「強い香気による厄払い」という意味が込められた「菖蒲湯」には性別年齢関係なく入浴しています。
七夕(たなばた)7月7日あるいはその前夜の行事。
本来は陰暦で行っていたが、現在は陽暦の7月7日に行う所が多い。
東北地方などでは月遅れの8月7日に行っている。
七夕は織女祭(しょくじょさい)、星祭(ほしまつり)などともいい、中国伝来の行事と、日本古来の伝承、さらに盆行事の一環としての行事など、さまざまな要素が入り混じって今日に伝承されている。
クリスマスクリスマスは多くの国で祝日となっているが、日本でも祝日にしようという話がある。
日本においても、かつてこの[[12月25日]]が大正天皇祭として休暇日であった時期がある。